滋賀で地震に強い家を建てたい方へ|強い家の特徴・適した工法・工務店の選び方を解説
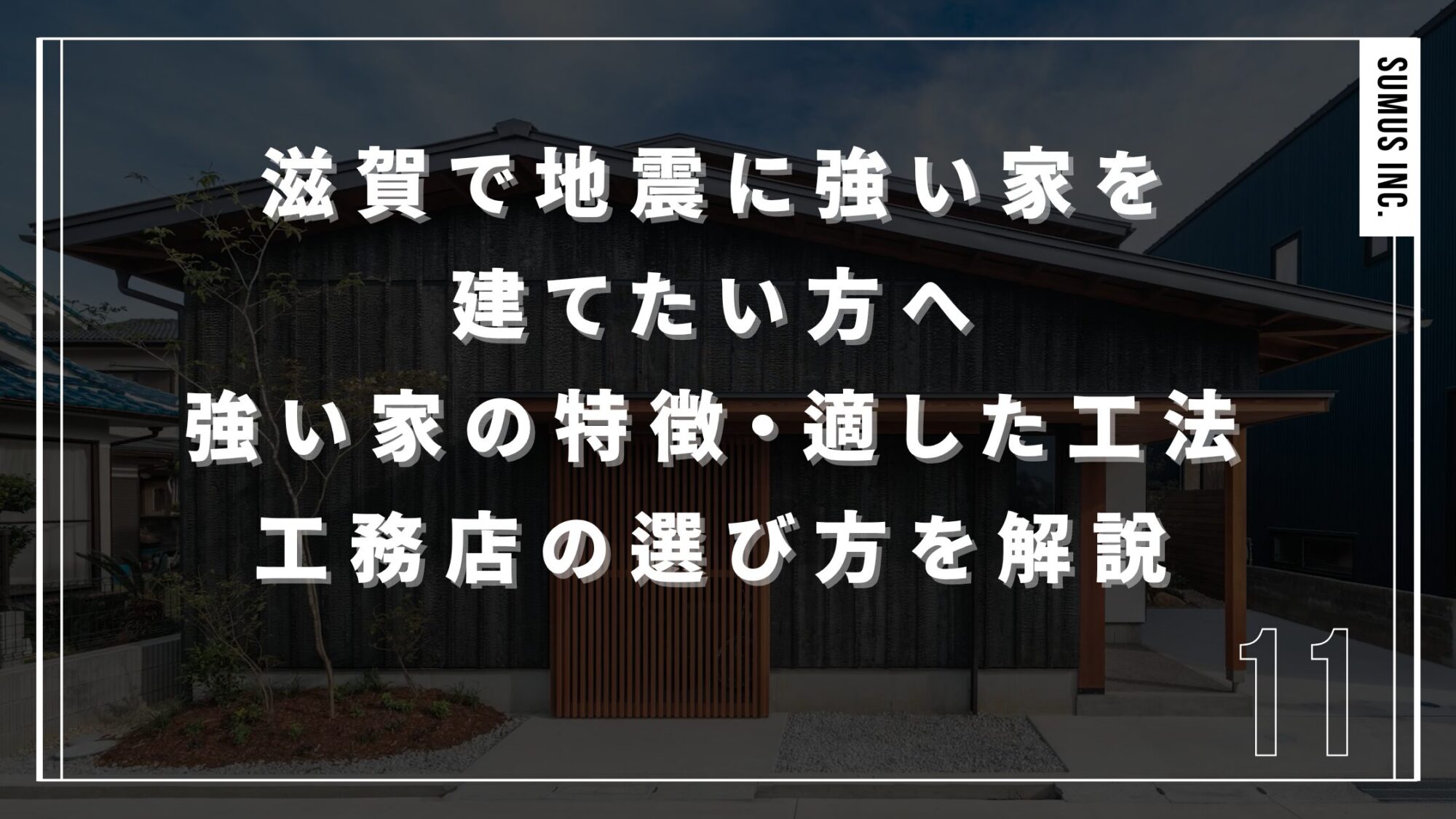
近年、ゲリラ豪雨や大型台風などの自然災害が全国で頻発しており、特に注意すべき災害のひとつが地震です。最大震度7の揺れが予想される南海トラフ地震も、今後30年以内に高確率で発生するといわれています。「ここは大丈夫」と言い切れる地域は、もはや存在しません。
こうした背景から、家づくりにおいて「耐震性」や「地盤の安全性」など、地震に強い住宅への関心が高まっています。この記事では、滋賀で地震に強い家を建てるために押さえておきたい基礎知識から、適した工法、住宅の構造、工務店選びのポイントまで、わかりやすく解説します。
はじめに理解しておきたい地震に強い家の定義

「地震に強い家」とは、大規模な揺れが起きた際にも倒壊や大きな損傷を防ぎ、家の中で安全を確保できる住宅のことを指します。具体的には、建築基準法で定められた耐震性能を満たすだけでなく、より高い安全性を実現するために「耐震」「制震」「免震」の技術が組み合わされていることが望ましいとされています。
中でも、住宅の耐震性能を客観的に評価する「耐震等級」は重要な指標で、最も高い耐震等級3の住宅は、震度6強~7クラスの地震でも倒壊しない強度を備えています。家づくりにおいては、これらの観点から構造・工法・設計バランスを総合的に検討することが、「本当に地震に強い家」をつくる第一歩となります。
木造住宅は地震に強い?他の家との違い
![]()
地震に強い家かどうかを判断する指標のひとつに「耐震等級」がありますが、そもそもこの等級はどのように決まるのでしょうか。一般的には、鉄骨や鉄筋コンクリート造の方が強い印象がありますが、実際のところ木造住宅はどうなのでしょうか。
近年は自然素材や住まいの快適性を重視する声も多く、木造住宅への関心も高まっています。ここでは、鉄骨造との違いや木造住宅の耐震性能について詳しく見ていきます。
鉄骨造住宅との違い
鉄骨造は、柱や梁に鋼材を使用した構造で、変形しにくい高い剛性を持つのが特徴です。地震時には建物の揺れを抑え込む強さがあり、特に大空間を確保したい建物に適しています。ただし、鋼材は重量があり、地盤や基礎への負荷が大きくなりやすい点には注意が必要です。
一方、木造は構造自体が軽く、揺れによる負荷を低減できるうえ、木材のしなやかさが振動を吸収・分散しやすいという利点もあります。鉄骨造が「固さ」で耐えるのに対し、木造は「柔軟さ」で衝撃を逃がす構造ともいえます。
耐震設計の考え方や使われる素材の特性をふまえると、コストパフォーマンスと地震への実効性を両立できる木造住宅は、一般的な戸建てにおいて非常に現実的で優れた選択肢といえるでしょう。
木造住宅の耐震性
木造住宅は「地震に弱い」というイメージを持たれがちですが、実際には設計次第で高い耐震性能を確保することが可能です。現行の建築基準法に則って適切に構造設計された木造住宅であれば、耐震等級3(建築基準法の1.5倍の耐震性)を取得することも十分に可能です。これは鉄骨造であっても同じで、構造そのものの素材よりも、耐力壁や接合部の設計、計算方法(例:許容応力度計算)の精度などが等級の取得可否を大きく左右します。
木材は軽量かつ粘りがあるため、揺れの力を受け流す構造が実現しやすく、適切な工法と設計を組み合わせることで、地震に強く、かつ心地よい住空間を両立することができます。構造の選択に迷ったときは、「木造=弱い」と決めつけず、設計内容まで踏み込んで確認することが大切です。
関連記事:失敗しない工務店の選び方|滋賀で家を建てる人が知っておくべき7つのポイントと設定ステップ
地震に強い木造住宅を選ぶなら「工法」もポイント

前述の通り、耐震性能は「木造だから弱い」「鉄骨だから強い」といった素材の違いだけで決まるものではありません。実際には、建物の構造設計や採用する「工法」によって耐震性は大きく左右されます。
とくに木造住宅では、選ぶ工法によって揺れに対する強さや設計の自由度に差が出るため、地震に強い家を建てたい方にとっては重要な検討ポイントです。ここでは代表的な3つの木造工法について、その特徴や耐震性への影響を解説していきます。
木造軸組工法|設計の自由度を重視した構造
木造軸組工法(在来工法)は、日本の伝統的な住宅建築に広く使われている構造で、柱・梁・筋交いなどで骨組みを形成する工法です。最大の特徴は、設計の自由度が高いことです。間取りの変更や将来的なリフォームにも柔軟に対応しやすく、敷地形状や家族構成に合わせた住まいを実現できます。
耐震性の面では、構造部材の配置や耐力壁のバランス、接合部の補強が品質を左右するため、設計力と施工精度が重要になります。耐震等級3を取得することも可能ですが、筋交いの配置や構造計算が不十分だと強度にバラつきが出る点には注意が必要です。信頼できる施工会社とともに、構造設計までしっかり確認することが地震に強い家づくりの鍵となります。
木造枠組壁工法|面で支える揺れに強い構造
木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は、壁・床・屋根といった各部位を「面」で構成し、6面体で建物を支える構造です。パネル全体で外力を受け止める構造のため、地震時にも揺れの力が分散しやすく、耐震性に優れているのが大きな特長です。また、あらかじめ工場で構造部材を規格化することで品質の安定が図れ、施工ミスも抑えやすいという利点もあります。
一方で、開口部や間取りの自由度がやや制限されるため、設計の柔軟性を重視する方には不向きと感じることもあるでしょう。ただし、耐震性を第一に考える方にとっては非常に合理的な工法であり、設計条件が合えば優れた選択肢となります。
ハイブリッド工法|自由度と耐震性を両立した構造
ハイブリッド工法は、木造軸組工法の「自由度」と枠組壁工法の「面で支える耐震性」を融合させた、近年注目されている新しい構造工法です。従来の在来工法では点や線で支えていた部分に、構造用合板やパネル材を適切に組み合わせることで、建物全体の剛性を大きく向上させます。
これにより、間取りや開口部の自由度を維持しながら、耐震等級3や許容応力度計算にも対応可能な高い耐震性能を実現することができます。さらに、断熱性や気密性、耐久性といった住宅性能もバランス良く向上させやすく「設計の自由」も「地震への強さ」も妥協したくない方に最適な工法といえるでしょう。高性能な木造住宅を目指すなら、非常に有力な選択肢です。
地震に強い家の特徴

耐震性能は、建物の構造や使用される工法・素材によって左右されますが、それと同じくらい「どのような形・設計の家にするか」も強度に大きく影響します。特に注文住宅のように、自分たちで間取りや外観をある程度自由に決められる場合は、地震に強い家の“形”や“設計の工夫”を理解しておくことが重要です。
ここでは、建物の形状や高さ、重量、さらには建てる場所の地盤といった「家そのものの特徴」に注目して、地震に強くするためのポイントを解説します。
構造や形がシンプルで凹凸が少ない形状
地震に強い家の基本は、建物全体の形状がシンプルであることです。正方形や長方形に近い形は、各面で揺れの力を均等に分散できるため、構造に偏りが生じにくく、地震エネルギーに対して安定性を発揮します。
一方で、L字型やコの字型のように凹凸の多い建物は、揺れが特定の部分に集中しやすく、構造的な弱点をつくるリスクが高まります。特に1階の一部がガレージなどで壁がない「ピロティ構造」は、地震時に崩壊の危険が増します。見た目のデザインや使い勝手も大切ですが、耐震性を優先するなら、構造はできるだけシンプルにまとめることが基本といえるでしょう。
低層設計で重心が安定している
建物の高さは、地震の揺れに対する安定性に直結します。一般的に、高層になるほど重心が上がり、揺れの影響を受けやすくなります。ビルの高層階で大きく揺れを感じるのもこのためです。戸建て住宅においても、3階建てより2階建て、2階建てより平屋の方が重心が低く、地震時の振動を受けにくくなります。
とくに平屋は重心が最も安定し、構造的にバランスが取りやすいため、地震に強い住宅形態とされています。ただし、建物の強さは高さだけで決まるものではありません。地盤の状況や設計上の補強計画といった総合的な判断も重要です。
軽量な建物構造
地震時に建物へ加わる力は「質量(重さ)」に比例します。つまり、建物が軽ければ軽いほど、揺れによる負荷が小さくなり、構造へのダメージも抑えやすくなります。木造住宅は鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)に比べて構造材が軽量であるため、耐震性の面で優位性があります。
特に、屋根材や外壁材に軽量な素材を使うことで、建物全体の重心を下げることができ、揺れへの耐性をさらに高めることが可能です。ただし、いくら軽くても構造や施工に不備があれば本末転倒です。軽さと構造強度のバランスが取れた設計こそが、地震に強い家の理想形といえるでしょう。
地盤の安定性が高い立地
どれだけ耐震性の高い家を建てても、建っている地盤が不安定では本末転倒です。地盤が軟弱なエリアでは、地震時に地盤が揺れを増幅したり、建物が沈下する「不同沈下」が発生したりするリスクがあります。特に河川沿いや埋立地、田畑の転用地は注意が必要です。
一方、岩盤層に近い強固な地盤であれば、建物への揺れの伝達が抑えられ、耐震設計の効果を最大限に発揮できます。現在は地盤調査が義務化されており、建築前にしっかりと地盤の強度を確認し、必要があれば地盤改良を行うことで安全性を高められます。安心できる家づくりは、まず土地選びから始まるという意識が重要です。
地震に強い家の選び方

ここまで、地震に強い家の定義や工法、構造の特徴について解説してきましたが、実際に家づくりや購入を検討する際に、それらをすべて自分で見極めるのはなかなか難しいものです。「どこを見れば安全性を判断できるのか分からない」と感じる方も多いでしょう。
この章では、専門的な知識がなくても、家の耐震性を見極めるために押さえておきたい具体的なチェックポイントを紹介します。家を建てるとき、また購入を検討する際の参考にしてみてください。
耐震等級で住宅の強さを確認する
「耐震等級」は、住宅がどの程度の地震に耐えられるかを示す客観的な指標です。等級は1~3に区分され、数字が大きいほど耐震性能が高いことを意味します。
・耐震等級1:建築基準法の最低基準。震度6強程度の地震でも倒壊しないレベル。
・耐震等級2:等級1の1.25倍の耐震性能があり、学校や病院など避難所にも求められるレベル。
・耐震等級3:等級1の1.5倍の強度を持ち、消防署など防災拠点にも使われる最高ランク。
注文住宅の場合、工務店や設計士に確認すれば等級の有無や想定レベルを教えてもらえますが、より正確に知りたい場合は「建設住宅性能評価書」の有無を確認するのがおすすめです。建売住宅では、不動産会社に評価書の有無や等級の記載があるかを尋ねるとよいでしょう。評価書が交付されていれば、第三者のチェックを経た安心材料になります。
構造と工法の違いを理解して選ぶ
構造や工法によって耐震性に差が出ることはすでに解説したとおりです。実際に確認する際は、「構造種別(例:木造軸組、枠組壁、鉄骨造など)」と「採用している工法」がパンフレットや設計図に明記されているかをチェックしましょう。工務店や住宅メーカーに、「この工法は耐震等級3に対応しているのか」「許容応力度計算で設計しているか」などを質問すると、地震への配慮度合いも判断できます。
地盤の状態を把握し必要な対策を行う
どれだけ耐震性の高い家でも、地盤が弱ければ揺れが増幅され、倒壊や沈下のリスクが高まります。そのため、建築前に行う地盤調査の内容をしっかり確認することが重要です。注文住宅の場合は、工務店に「地盤調査はいつ、どの方法で行うのか」「その結果に応じた地盤改良の必要性があるか」を確認しておくと安心です。
建売住宅であれば、不動産会社に調査済みかどうか、調査結果の内容、改良工事の有無を確認しましょう。地盤が軟弱な場合は、表層改良・柱状改良・鋼管杭工法などで補強されているかもポイントになります。地盤の安定性は、耐震性の土台となる部分。土地選びの初期段階からしっかり確認しておくことが、安心できる家づくりにつながります。
柱や壁の配置バランスに注目する
柱や壁の配置は、建物の揺れに対する強さに直結する重要な要素です。耐震性を高めるためには、柱が適切に分散されて荷重が偏らないこと、そして耐力壁がバランスよく配置されていることが欠かせません。特に1階部分に壁が少ない間取りや、大きな吹き抜けがある場合は、構造上の補強がなされているかどうかを確認する必要があります。
注文住宅の場合は、間取り図とともに「耐力壁の配置計画」や「構造計算書」が提示されることがあるため、設計担当者に説明を求めるとよいでしょう。建売住宅では、住宅性能評価書に記載された耐震等級や構造の説明内容から、バランスの取れた設計になっているかを確認することができます。
地震に強い家を建てるメーカー・工務店の選び方

地震に強い家を建てるうえで、最も重要なのが工務店や住宅メーカーの選定です。最低限の基準はどの会社でも満たしていますが、どこまで構造計算にこだわるか、どの工法を採用するかといった姿勢は会社によって大きく異なります。見た目や価格だけで選ぶのではなく、「構造の中身」に真剣に向き合っているかを見極めることが大切です。
ここでは、安心して任せられる依頼先を選ぶための具体的なチェックポイントを解説していきます。
「耐震等級3」や「許容応力度計算」などの耐震性能
耐震性能に本気で取り組んでいる工務店かどうかは、「耐震等級3を標準仕様としているか」「許容応力度計算を実施しているか」で見極めることができます。どちらも任意項目であり、法的には義務ではないため、こだわりのない工務店では採用していないことも少なくありません。
見学会や相談時には、単に「耐震等級3を取得できますか?」と聞くだけでなく「どのような構造計算で設計しているか」「設計者が構造専門か」「計算書は提示可能か」などを具体的に質問してみましょう。答えに曖昧さがない会社は、構造への姿勢が真剣である証拠です。
また、設計段階で許容応力度計算を導入しているかは、見積書や仕様書にも反映されることがあります。料金内訳や構造欄に「許容応力度計算含む」といった記載があるかどうかも確認のポイントです。
木造住宅なら「ハイブリッド工法」がおすすめ
木造住宅で耐震性と設計の自由度を両立したい場合、ハイブリッド工法を採用している工務店を選ぶのがおすすめです。従来の在来工法と異なり、柱と梁に加えて構造用合板やパネル材を組み合わせることで、揺れに強く、かつ間取りの自由度も高くなります。
ただし、ハイブリッド工法を名乗っていても内容は会社によって異なるため、見極めが重要です。面談時には「どのような面材を使用しているか」「耐力壁の配置はどう設計しているか」「在来工法との違いを具体的に説明できますか?」といった質問をしてみましょう。
さらに「その工法で耐震等級3を取得した実績があるか」を聞けば、経験と実力のある工務店かどうかがより明確になります。単なる呼び名ではなく、構造的な裏付けがあるかどうかが判断の分かれ目です。
「長期優良住宅」や「劣化対策等級」の内容
工務店選びでは、住宅性能の“継続性”に注目することも大切です。その指標のひとつが「長期優良住宅」や「劣化対策等級3」の取得実績です。これらの基準は、構造躯体の耐久性やメンテナンス性など、地震後も安心して暮らし続けられる家かどうかを評価するものです。
工務店を選ぶ際には、「長期優良住宅の認定取得は可能ですか?」「劣化対策等級は標準でいくつを想定していますか?」と聞いてみましょう。あわせて、提出する申請書類や仕様書を見せてもらうことで、性能評価に対する取り組み姿勢も見えてきます。補助金や税制優遇を受けるうえでも関係する項目ですので、「制度の取得支援をしているかどうか」も含めて確認すると、より見極めやすくなります。
関連記事:滋賀県のおすすめ工務店はこう見つける|信頼できるパートナー選びのポイントと注意点
地震に強い家を滋賀で建てる場合は「スムース」にお任せください

株式会社スムースは、滋賀・草津に拠点を持つ自然素材の家づくりにこだわる工務店です。国産材や珪藻土など素材の心地よさを追求する一方で、断熱・気密・そして耐震性能にも徹底的に力を入れています。当社では、構造の強さにも妥協せず、デザイン性や住み心地も大切にした家づくりを行っています。ここでは、スムースがどうやって「地震に強く、長く安心して住める家」を実現しているのか、そのポイントを詳しくご紹介します。
「許容応力度計算」+「耐震等級3」で高水準の耐震性能を実現
スムースでは、全棟において許容応力度計算を実施し、原則として耐震等級3の取得を標準としています。震度7クラスの大地震が繰り返し発生しても耐えられる構造を目指し、初回プランから構造の安全性を徹底的に検証しています。
設計段階で作成する構造計算書は数百ページに及び、柱や梁、接合部などあらゆる部位にかかる力を一つひとつ確認します。設計や検証には時間も労力も必要ですが、安全性に妥協せず、本当に信頼できる家をお届けするために欠かせない工程だと考えています。ご家族の命と暮らしを守る住まいをつくること、それが私たちスムースの基本姿勢です。
「ハイブリッド工法」で耐震性と設計の自由度を両立
「地震に強くて、デザインの自由度もある」そんな住まいを実現するために、スムースでは「ハイブリッド工法」を採用しています。これは在来軸組工法と2×4工法を組み合わせたもので、柱と梁で空間の自由度を確保しつつ、壁や床で揺れの力を分散させる構造です。
広いLDK、大きな窓、吹き抜けやスキップフロア。そういった希望を叶えながらも、地震に強い家を成立させることができます。しかも、これらの設計はすべて許容応力度計算に基づいて構造を確認済みです。自由さと強さをどちらも妥協したくない方にこそ、スムースの家を選んでほしいと本気で思っています。
制振・耐久性能まで考え抜いた「長く安心して住める家」
耐震性能だけがあればいい、私たちはそうは考えていません。揺れを吸収して負担を減らす「制振性能」、そして建物そのものを長持ちさせる「耐久性能」も、スムースではすべて標準レベルでしっかり対応しています。たとえば、構造の補助として制振装置「evoltz(エヴォルツ)」の導入も可能です。これは震度1レベルから揺れを吸収してくれる高性能な装置で、繰り返す地震に対しても建物の損傷を最小限に抑えてくれます。
また、1階構造材には腐らない木「緑の柱(ハウスガードシステム)」や、耐久性の高いデュラルコート金物を使用。建てたときの耐震性能をずっと維持できるよう、素材レベルからしっかり守り抜く体制を整えています。
スムースではこの他にも、白蟻被害を防ぐ「緑の柱」や床下防蟻処理、気密性を高める全棟気密測定、自然素材による調湿設計など、耐久性・快適性を支える細部にまでこだわっています。性能は日当たりや室温なども含めてシミュレーションで“見える化”し、納得して選んでいただける家づくりを心がけています。滋賀周辺で家を建てたいと考えていましたら、お気軽にご相談ください。
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)