家の断熱材は何がいい?種類一覧と性能ランキングで徹底比較
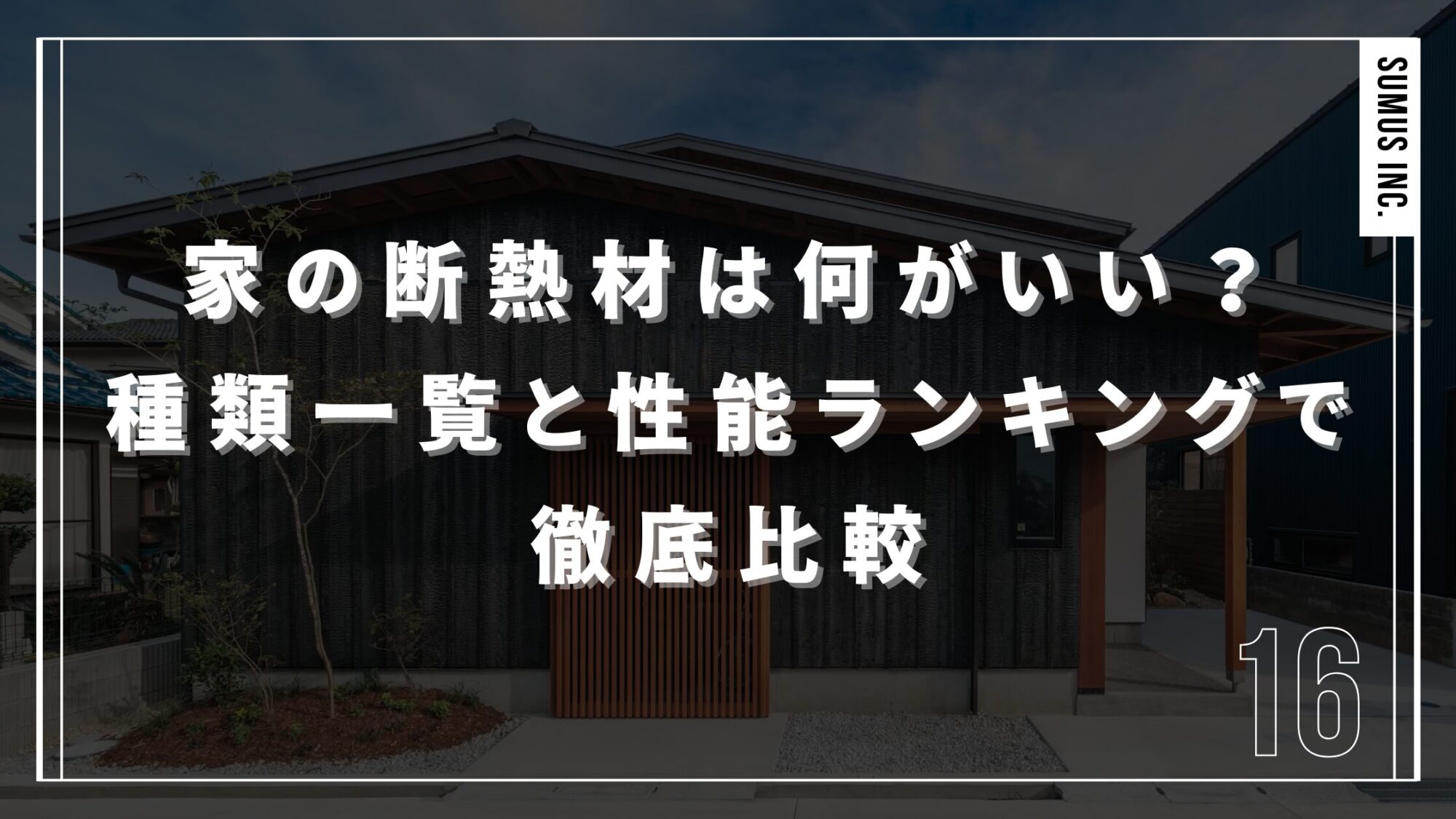
家を建てる際に欠かせない要素のひとつが「断熱性能」です。断熱性を高めれば、夏は外気の熱を遮り涼しく過ごせ、冬は暖気を逃さず室内を快適に保てます。その結果、冷暖房の使用を減らし光熱費の削減にもつながるでしょう。さらに、室温差を小さくすることでヒートショックなど健康リスクの軽減にも役立ちます。
ただし断熱材にはさまざまな種類があり、性能などには大きな違いがあるため事前に理解しておく必要があります。この記事では、代表的な断熱材の特徴や性能、コスト面を比較しながらわかりやすく解説していきます。
家に使用される断熱材の重要性

家づくりにおいて断熱材は、外壁・屋根・床下といった外気と接する部分に設置されます。これらは温度変化や湿気の影響を最も受けやすく、断熱材を入れることで外気の影響を遮り、室内環境を安定させる仕組みとなっています。とくに屋根や壁は日射や冷気が直接伝わるため、適切な断熱材が欠かせません。断熱材が担う主な働きは以下の通りです。
・外気の熱や冷気を遮断し、室内温度を一定に保つ
・隙間からの熱の出入りを防ぎ、気密性を高める
・壁内や床下の湿気をコントロールし、結露やカビを防止する
・部屋ごとの温度差を抑え、家全体の快適性を向上させる
・冷暖房の効率を高め、光熱費の削減につなげる
・温度差によるヒートショックや健康リスクを軽減する
仮に建物の構造が頑丈でも、断熱材が不十分だと夏は暑く冬は寒い家になり、冷暖房費も膨らみやすくなります。一方で良質な断熱材を適切に施工すれば、四季を通じて快適で健康的に暮らせる住宅となり、光熱費や修繕リスクの低減にもつながるでしょう。
【自然系・木質繊維系】家に使用される断熱材の種類と特徴

一口に断熱材といっても種類は幅広く、自然素材を用いたものから鉱物系、石油系まで大きく三つに分類されます。それぞれ性能やコスト、環境への影響が異なり、家づくりにどのように生かすかを考える上で重要な判断材料となるでしょう。ここでは、自然由来の原料を使った「自然系・木質繊維系」の断熱材に注目し、その種類や特徴を解説します。
セルロースファイバー|調湿・防音・断熱性に優れた自然素材
セルロースファイバーは、新聞古紙を再利用した自然素材の断熱材で、壁や屋根の空洞に吹き込み、配線や配管まわりまで隙間なく埋められるのが大きな特長です。木質繊維は湿度変化に応じて吸放湿するため、壁体内の結露を防ぎやすく、結果としてカビの発生リスクを抑える効果も期待できます。
調湿性によって室内の乾燥や過剰な湿気を和らげ、快適な住環境を維持できる点は他の断熱材にない魅力です。さらに繊維が絡み合った構造は高い防音性を発揮し、外部騒音の侵入や生活音の響きを軽減します。安全性についてもホウ素系薬剤で難燃化され、万一の火災時には延焼を遅らせる性能を備えています。自然素材でありながら断熱・調湿・防音・安全性をバランスよく備えた断熱材と言えるでしょう。
ウール|高断熱で湿度調整に強い天然素材
羊毛を原料とするウール断熱材は、天然素材ならではの調湿性と断熱性を併せ持っています。湿度が高いときは水分を吸収し、乾燥時には放出するため、壁内の結露を防ぎやすく、カビの抑制にもつながるでしょう。また繊維自体が空気を多く含むため断熱性能が高く、寒冷地でも一定の快適性を維持できます。
さらに防音性も一定水準があり、生活音や外部の騒音を和らげてくれます。天然由来でありながら、防虫加工を施すことで耐久性も確保されています。ただし、コストが比較的高い点や、国内での流通量が限られる点には注意が必要です。自然素材にこだわりたい方には選択肢となる断熱材です。
炭化コルク|防虫・調湿・吸音性を兼ね備えた高性能素材
炭化コルクは、コルク樫の樹皮を高温で炭化処理した断熱材で、自然素材ながら多機能性を備えているのが特徴です。内部は多孔質構造となっており、断熱性能に加えて優れた吸音性を発揮し、住まいの静けさを保ちやすい点が魅力です。調湿機能もあり、湿度変化を緩和することで結露やカビの発生を抑えやすい点も安心です。
また、炭化処理によって防虫性・耐久性が高められており、長期間安定した性能を維持できます。さらに燃えにくく、火災時にも延焼を遅らせる特性を持つことが知られています。ただし、他の断熱材に比べて入手性やコスト面でハードルがあるため、採用はこだわり派や自然素材志向の住宅に多く見られます。
【鉱物系】家に使用される断熱材の種類と特徴

鉱物系とは、ガラスや岩石といった無機素材を原料とした断熱材です。最大の特徴は不燃性に優れている点で、火災時にも燃え広がりにくい安心感があります。ここでは代表的な「グラスウール」と「ロックウール」について解説します。
グラスウール|低コストで断熱・防火性能に優れる
グラスウールは、ガラスを高温で溶かして繊維状に加工した断熱材で、日本の住宅で最も普及している素材のひとつです。細かな繊維が空気を含むことで断熱効果を発揮し、比較的安価で手に入りやすいため、多くのハウスメーカーや工務店で採用されています。
不燃性に優れており、火災時に燃え広がりにくい点も安心材料でしょう。また、防音性も一定水準あり、生活音や外部の騒音を和らげます。ただし、施工時に隙間が生じると断熱性能が低下しやすく、正確な施工品質が求められる点には注意が必要です。コストと性能のバランスに優れた、代表的な鉱物系断熱材です。
ロックウール|耐火・防音に優れた高性能断熱材
ロックウールは、玄武岩や高炉スラグといった鉱物を繊維状に加工した断熱材です。耐火性が非常に高く、高温にさらされても燃えにくいため、火災安全性を重視する建物で多く採用されています。繊維の密度が高いため防音性能にも優れ、外部からの騒音対策や室内の音響改善にも効果的です。断熱性能も安定しており、寒冷地や集合住宅など幅広い用途で利用されています。
一方で、吸湿性があるため適切な防湿層との組み合わせが必要で、施工には一定の知識と技術が求められます。コストはグラスウールよりやや高めですが、耐火性と防音性を重視する場合には有力な選択肢となる断熱材です。
【石油系】家に使用される断熱材の種類と特徴

石油系の断熱材は、石油を原料とした樹脂を加工してつくられるタイプで、断熱性能に優れているのが大きな特徴です。ただし種類ごとに特性は異なり、耐水性や耐久性、コスト面で差があります。ここでは代表的な石油系断熱材について解説します。
高反発ポリエチレンフォーム|軽量で耐水性・施工性に優れる
高反発ポリエチレンフォームは、石油由来の樹脂を発泡させた断熱材で、非常に軽量で扱いやすいのが特徴です。カッターなどで簡単に加工できるため、現場での施工性に優れ、DIYや部分的な断熱補修にも使われています。また、耐水性が高く湿気を通しにくいので、床下や水まわりなど湿気の影響を受けやすい場所にも適しています。
断熱性能は安定していますが、他の高性能断熱材と比べると厚みを多く必要とする場合があります。コストは比較的抑えやすいため、手軽さと使い勝手を重視する場面で選ばれることが多い断熱材です。
ポリエステル|安全性が高くリサイクル可能な断熱材
ポリエステル断熱材は、衣類やペットボトルにも使われるポリエステル繊維を加工してつくられています。ホルムアルデヒドなど有害物質を含まないため、健康や環境への影響が少なく、安全性の高さが評価されています。また、リサイクル原料を利用できる点から、循環型社会に適した断熱材として注目されています。
吸水性が低くカビの心配が少ないため、壁内の結露対策としても有効でしょう。繊維が柔らかく扱いやすい反面、施工時にはしっかりと固定しないと隙間ができやすい点には注意が必要です。コストはやや高めですが、安全性や環境配慮を重視する住宅で採用されるケースが増えています。
ビーズ法ポリスチレンフォーム|断熱性とコスパのバランスが良い
ビーズ法ポリスチレンフォームは、発泡スチロールと同じ原料を小さな粒状に発泡させて固めた断熱材です。軽量で加工しやすく、断熱性とコストのバランスに優れているため、戸建住宅から集合住宅まで幅広く使われています。耐水性が高い点も特徴で、床下や基礎部分など湿気の影響を受けやすい場所でも安心して利用できます。
断熱性能は安定していますが、外気温の変化に弱く厚みが必要になる場合があるため、十分な設計と組み合わせて使うことが大切です。施工のしやすさと価格の手頃さから、コストパフォーマンスを重視するケースで選ばれる代表的な石油系断熱材といえるでしょう。
硬質ウレタンフォーム|高断熱で気密性も高い高性能素材
硬質ウレタンフォームは、発泡させたウレタン樹脂を用いた断熱材で、非常に高い断熱性能を発揮するのが特徴です。現場で吹き付けて施工する工法が多く、隙間を埋めながら一体化するため気密性も確保しやすい点が強みです。複雑な形状の部分にも対応でき、全体を効率的に断熱できるのは他の素材にはないメリットでしょう。
一方で、紫外線に弱く、露出部分では劣化が進みやすいため適切な仕上げ材で保護する必要があります。価格はやや高めですが、断熱等級の高い住宅や省エネ基準を満たす家づくりを目指す場合に多く採用される高性能な断熱材です。
押出法ポリスチレンフォーム|耐久性が高く安定した性能を発揮
押出法ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂を押し出し成形してつくられる断熱材で、内部の気泡が均一で密度が高いのが特徴です。そのため強度や耐久性に優れており、長期間にわたり安定した断熱性能を維持できます。吸水性も低いため、床下や基礎部分など湿気の多い場所でも劣化しにくい点が安心材料です。軽量で施工性も良く、扱いやすさも兼ね備えています。
ただし、燃えやすさがあるため使用部位によっては防火対策が必要です。コストは比較的手頃で、耐久性と断熱性能をバランスよく求める住宅で広く利用されています。
フェノールフォーム|最も断熱性が高く耐火性にも優れる
フェノールフォームは、フェノール樹脂を発泡させて成形した断熱材で、断熱材の中でもトップクラスの熱伝導率の低さを誇ります。薄い厚みでも高い断熱性能を発揮できるため、壁厚を抑えつつ高断熱を実現したい住宅に適しています。また、不燃材料としての性能が高く、火災時にも延焼を防ぎやすい点は大きな安心要素です。
耐久性にも優れており、長期間安定した性能を維持できます。一方で価格は他の断熱材より高めであり、コスト面では導入のハードルがあります。しかし、省エネ基準や高断熱住宅を目指す場合には有力な選択肢といえる断熱材です。
スムースの家は、UA値0.37〜0.44という国基準を大きく上回る断熱性能を備えています。自然素材のセルロースファイバーを採用し、結露やカビを抑えて快適な住環境を保ちます。さらに全棟で気密測定を行い、C値0.5クラスを達成しています。断熱材・施工・気密性のすべてにこだわり、省エネで快適な暮らしをご提供します。
断熱性能に優れた断熱材ランキング

断熱性能は、カタログに記載される熱伝導率の数値だけで判断できるものではありません。実際の住まいでは、隙間なく施工できるか、壁内結露を防げるか、気密性を確保できるかといった要素が大きく影響します。そのため、ここでは熱伝導率に加えて調湿性や施工性、耐久性なども踏まえた総合評価でランキングを作成しました。
1位 セルロースファイバー
カタログ値の熱伝導率は0.038~0.040W/m・Kと、フェノールフォームや硬質ウレタンフォームより劣ります。それでも実際の住まいにおける快適性や結露対策まで含めて考えると、総合的に最も優れた選択肢といえるでしょう。セルロースファイバーは壁内や屋根裏に隙間なく充填できるため、断熱層の途切れを防ぎます。
さらに木質繊維の特性で吸放湿し、結露やカビのリスクを抑えながら断熱性能を安定させます。断熱を高めるには「気密性」が重要ですが、セルロースファイバーは施工段階で細部まで密に詰められるため、気密と断熱を同時に確保しやすい点でも高く評価できます。
2位 硬質ウレタンフォーム
熱伝導率は約0.024W/m・Kとセルロースファイバーより低く、断熱材の中でも高性能な部類です。吹付施工によって隙間を埋めることができ、気密性の確保に優れています。ただし紫外線に弱いため露出部には仕上げ材が必要であり、施工品質による性能差も大きい点は注意が必要です。
3位 フェノールフォーム
熱伝導率は0.020W/m・Kとトップクラスに低く、薄い厚みでも高断熱を実現できる点が特徴です。さらに燃えにくい性質を持ち、火災時の安心感も高い素材です。ただし価格が高めで、採用できるケースが限られることから、総合的なランキングでは3位としました。
防火性に優れた断熱材ランキング
![]()
断熱材は本来、外気の熱を遮る役割を担いますが、住宅の安全性を考えるうえでは「燃えにくさ」も無視できません。火災時に延焼を抑えられるかどうかは、素材の性質に大きく左右されます。ここでは防火性能を基準に、代表的な断熱材をランキング形式で紹介します。
1位 ロックウール
玄武岩や高炉スラグを溶かしてつくる無機繊維系断熱材で、不燃材料として認められています。耐熱性が非常に高く、1000℃近い高温にさらされても燃えにくい点が大きな特長です。防音性にも優れるため、火災安全性と住環境の両方を重視したい場合に有力な選択肢です。
2位 グラスウール
ガラスを原料とした無機素材で、こちらも不燃材料に分類されます。火災時に延焼しにくく、発煙や有毒ガスの発生も少ないため、住宅用断熱材として長年採用されてきました。コストも手頃で広く普及しており、防火性と扱いやすさのバランスに優れています。
3位 フェノールフォーム
発泡プラスチック系に属しますが、他の石油系に比べて燃えにくく、難燃性能が高いのが特長です。熱伝導率が低く断熱性も優れるため、省エネと防火性を同時に確保したい場合に適しています。ただしコストが高いため、採用は高性能住宅や限られた部位で使われるケースが多いでしょう。
価格に優れた断熱材ランキング

断熱材を選ぶ際には性能だけでなく、コストも重要な判断材料です。材料費や施工費が比較的抑えられるものは、限られた予算のなかでも採用しやすく、多くの住宅で使われています。ここでは価格面を重視した断熱材を3つ紹介します。
1位 グラスウール
最も広く普及している断熱材で、量産効果もあり価格が非常に手頃です。断熱性能や防火性も一定水準を満たしているため、コストと性能のバランスが良く、多くの住宅で標準仕様として採用されています。
2位 ロックウール
グラスウールよりやや高めですが、それでも比較的安価に利用できる部類です。耐火性や防音性が高く、コストを抑えながら安全性や快適性も重視したい住宅に向いています。
3位 ビーズ法ポリスチレンフォーム
発泡プラスチック系のなかでは価格が安く、加工もしやすいのが特長です。耐水性が高く、床下や基礎部分で採用しやすいため、コストパフォーマンスを重視する際に有力です。断熱性能も安定しているため、価格を優先しつつ一定の性能を確保したい住宅に適しています。
家の断熱性能は施工方法も大きく影響する
断熱材の種類や特徴を理解することは大切ですが、実際の住宅で性能をどれだけ発揮できるかは施工方法によっても変わります。同じ素材でも充填の仕方や外張りの有無で快適性や光熱費削減効果は大きく異なります。ここでは代表的な「充填断熱」「外張り断熱」「付加断熱」の3つの工法について解説します。
充填断熱
充填断熱は、柱や梁の間にできる壁の空洞部分に断熱材を詰め込む工法です。日本の住宅で最も広く使われており、グラスウールやセルロースファイバーなど、多くの断熱材に対応できます。比較的コストを抑えて施工できる点もメリットです。
ただし施工精度が低いと柱まわりやつなぎ目に隙間が生じ、気密性が落ちやすくなります。そのため気密シートや防湿シートを正しく施工することが不可欠です。丁寧な施工を前提とすれば、コストと性能のバランスに優れた方法といえるでしょう。
外張り断熱
外張り断熱は、構造体の外側を断熱材で包み込む工法です。柱や梁などの構造材ごと外側から覆うため、木材を通じた熱の出入り(熱橋)が少なく、断熱性能を安定して確保できます。さらに施工性も良く、現場での品質差が出にくい点も強みです。
ただし壁の厚みが増えるため狭小住宅では居住空間が減るケースがあり、断熱材の厚みや固定方法を工夫する必要があります。基礎部分と組み合わせれば、床下環境の湿気を抑えて木材の耐久性を高める効果も期待できます。
付加断熱
付加断熱は、充填断熱と外張り断熱を組み合わせる工法です。柱の間に断熱材を充填したうえで、さらに外側から断熱材を施工するため、断熱層を厚く確保できるのが最大の特長です。外気の影響を受けにくく、熱橋も抑えられるため、断熱等級6や7といった高水準の住宅性能を目指す場合によく採用されます。
気密性や結露抑制にも効果があり、省エネ性能を高めたい住宅には有効な工法です。ただし、充填と外張りを両方行うためコストが高くなりやすく、施工の手間も増える点には注意が必要です。経験豊富な施工会社を選ぶことで、十分な効果を発揮できる工法といえるでしょう。
工務店を選ぶ場合は「C値」を基準に選ぼう

断熱材や工法を理解するのも大切ですが、最終的に性能を左右するのは工務店の施工力です。優良かどうかを判断する目安のひとつが「C値」です。C値とは、建物全体の延床面積に対してどれだけ隙間があるかを示す数値で、㎠/㎡で表されます。数値が小さいほど気密性が高く、断熱材の性能を無駄なく発揮できます。
国の基準は5.0以下ですが、高気密高断熱住宅を目指すなら1.0以下、さらに理想は0.5前後となります。工務店を選ぶ際は「C値を測定しているか」「数値を公開しているか」を確認することが重要です。実測値を出している会社は、気密施工に強い意識を持っていると考えられるでしょう。また、その際にどのような断熱材を使用しているかもチェックしておくと安心です。
株式会社スムースはセルロースファイバー×C値0.5クラスで高断熱住宅を実現します

スムースの家は、国の基準を上回る高い断熱性能を備えています。断熱性能を示すUA値は小さいほど優れており、国の基準が0.87程度のところ、スムースでは0.37〜0.44という水準を実現。これは断熱等級6やHEAT20のG2グレードに相当し、夏の暑さや冬の寒さをしっかり遮断します。その結果、冷暖房の効率が良くなり、年間を通じて快適に過ごせる住宅となっています。
採用している断熱材は、自然素材を活かしたセルロースファイバーです。調湿作用によって壁内結露やカビを抑え、防音や防虫の効果も期待できます。袋詰め断熱材で起こりやすい熱橋を防ぎ、隙間なく充填できるため、性能を安定して発揮します。
さらに全棟で気密測定を行い、C値0.5クラスを達成しております。隙間の少ない施工により断熱材の力を最大限に引き出し、省エネ性や建物の耐久性を高めています。断熱材・施工技術・気密性能のすべてにこだわることで、スムースは高断熱住宅を提供しています。
スムースでは建てた後も「住むサポ」により定期点検を実施し、約40項目をチェックして長期の安心を支えます。住宅瑕疵担保保険は最長20年まで延長可能で、構造や雨漏りの不安にも対応。地盤には環境にやさしい砕石パイル工法を採用し、30年保証を用意しています。さらにシロアリ対策として薬剤に頼らない「緑の柱」を導入し、簡易メンテナンスで最長20年保証。断熱性能だけでなく、暮らし全体を長く守る仕組みを整えています。
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)