高気密・高断熱住宅は気持ち悪いし必要ない?|噂の真相と失敗しないための工務店選び
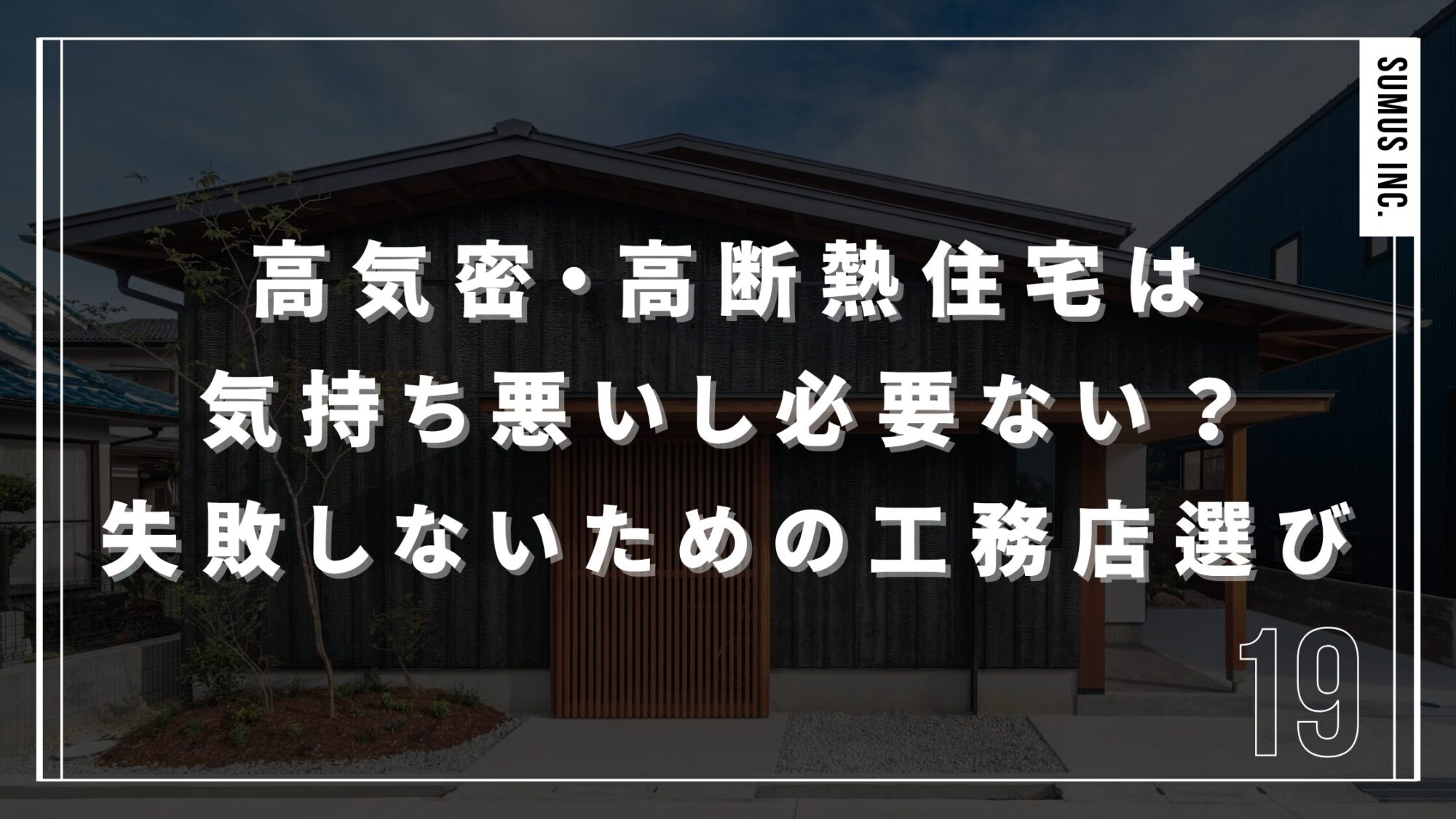
家づくりにおいて欠かせない要素の一つが断熱性能です。近年は「高気密・高断熱」住宅が注目され、省エネや快適性の面から支持されています。しかし、ネット上では「気持ち悪い」「必要ない」といった否定的な意見も散見されます。なぜそうした声が出るのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、高気密・高断熱住宅のメリット、性能を判断する基準、よくある噂の真相、そして失敗しない工務店選びのポイントについてわかりやすく解説していきます。
高気密・高断熱住宅とは断熱性と気密性を高めた省エネ住宅のこと

高気密・高断熱住宅とは、外気の熱や冷気を遮り、室内の空気が外へ漏れにくいように設計された住まいのことです。断熱材を屋根や壁、床にすき間なく施工し、さらにサッシや窓ガラスを高性能なものにすることで、建物全体を断熱の層で包み込みます。あわせて、柱や配管まわりのわずかなすき間も気密シートや専用の部材でふさぐことで、空気の流れをコントロールできる構造を実現します。
この仕組みにより、屋内は外の気温変化を受けにくく、計画的に換気を行うことで安定した住環境を保てるのが特徴です。つまり、高気密と高断熱は組み合わせてこそ効果を発揮し、快適かつ省エネ性の高い暮らしにつながる基盤となっています。
高気密・高断熱住宅に住むメリット5選
![]()
高気密・高断熱住宅は外気の影響を受けにくく、室内の快適さを保ちやすい構造になっています。実際に住んでみると、光熱費の削減や健康面の安心など、さまざまな利点が感じられます。ここでは主なメリットを5つに分けて解説していきます。
冷暖房効率が上がり光熱費を大幅に抑えられる
高気密・高断熱住宅は外気との熱の出入りを減らすため、室温を保つのに少ないエネルギーで済みます。例えば、一般的な断熱性能の住宅と比べると、冷暖房に必要な一次エネルギーはおよそ3〜4割削減できるとされています。
地域や家の大きさによって差はありますが、年間で数万円規模の光熱費削減につながるケースも珍しくありません。夏は冷房の涼しさが逃げにくく、冬は暖房の熱が長く持続するため、エアコンの設定温度を極端に上げ下げせずに快適さを維持できます。
外からの騒音を遮断し室内が静かになる
断熱材は熱を遮るだけでなく音を吸収する性質を持ち、さらに高気密構造によって隙間が減るため遮音効果が高まります。従来の木造住宅では窓を閉めても外の走行音が50〜60デシベル程度で聞こえることがありますが、高気密・高断熱住宅では40デシベル前後に抑えられるケースもあります。
大通り沿いでも会話やテレビ音量を上げずに生活でき、就寝時も外の騒音に妨げられにくい静かな空間が実現します。さらに室内の音漏れも減るため、プライバシーの確保にもつながります。
結露や湿気を防ぎ住宅の寿命を延ばせる
断熱性能や気密性能が不足した住宅では、冬に暖かい空気が冷たい壁や窓に触れて結露が発生しやすくなります。これを繰り返すとカビや木材腐食が進行し、住宅の耐久性を大きく損ないます。高気密・高断熱住宅は外皮全体を断熱材で包むため、壁面や窓の表面温度が下がりにくく、内部結露も起こりにくい構造になります。
実際に、適切に施工された住宅では窓際の表面温度が10℃以上に保たれることがあり、結果的に木材や断熱材の性能を長期間維持できます。長く住むほど修繕費や補修の負担が減るのも大きな利点です。
家中の温度差を小さくしてヒートショックを防げる
従来の住宅では、暖房の効いたリビングが20℃近くある一方で、廊下や浴室は10℃以下という大きな差が生まれることが少なくありません。高気密・高断熱住宅では、建物全体を断熱材で覆い、さらに空気の流れを制御するため、この差を2〜4℃程度に抑えやすくなります。
寒い冬でもトイレや浴室が極端に冷え込むことがないため、血圧の急激な変化が原因で起こるヒートショックの危険性を減らせます。小さな子どもや高齢者が安心して暮らせる住環境が整う点は見逃せないメリットです。
湿度をコントロールし洗濯物が乾きやすくなる
高気密・高断熱住宅は外の湿気や乾燥の影響を受けにくく、計画換気により室内の湿度を一定に保ちやすい特徴があります。例えば冬でも湿度40〜50%を維持できる設計が可能で、室内干しの洗濯物が6〜8時間程度で乾くケースもあります。
梅雨時でも空気が滞らないため部屋干し臭が発生しにくく、花粉や黄砂の季節には外干しを避けても清潔に乾かせます。適切な湿度管理は人の健康だけでなく木材や家具の劣化防止にもつながり、暮らし全体を快適に保ちます。
断熱性能を判断する基準「UA値」と住みやすさの目安

UA値は、屋根や壁、窓など外気に接する部分からどの程度熱が逃げやすいかを示す指標です。数値が低いほど断熱性が高く、夏も冬も快適さを保ちやすい住宅となります。以下に代表的な水準ごとの住みやすさは以下の通りです。
| UA値の目安 | 住み心地の特徴 |
|---|---|
| 約0.87(断熱等級4レベル) | 室温が上がりやすく、夕方以降も蒸し暑さが残りやすい。冷房を強めても効きにくく、涼しさが長続きしないため不快感を覚えやすい。 |
| 約0.60(等級5・ZEH基準) | 外気の影響を抑え、冷房を弱めても一定の涼しさを維持できる。帰宅時の暑さも和らぎ、省エネ性と快適さの両立が可能で家族全員が過ごしやすい。 |
| 約0.46(等級6相当) | 冷房効果が長持ちし、廊下や寝室まで安定した温度に。真夏でも家全体で温度差が小さく、夜も快適さを維持できる水準となる。 |
| 約0.26(等級7相当・最高水準) | 猛暑日でも少しの冷房で快適。外気の暑さをほとんど感じず、夜間も蒸し暑さが残りにくく、安心して深い眠りを得やすい環境が整う。 |
UA値は小さいほど断熱性能が高く、冷暖房の効率や住み心地に直結します。ただし、性能が高いほど建築コストも上がるため、住む地域の気候や家族構成、ライフスタイルに合わせた水準を選ぶことが重要です。
気密性能を判断する基準「C値」と住みやすさの目安

C値とは、建物の延べ床面積に対してどれだけの隙間があるかを示す数値です。数値が小さいほど気密性が高く、外気の影響を受けにくくなります。気密性能が高ければ、断熱材の効果を十分に発揮でき、冷暖房効率や室内の快適性が向上します。各C値ごとの住みやすさの目安は以下の通りです。
| C値の目安 | 住み心地の特徴(体感・暮らしへの影響) |
|---|---|
| 約5.0 ㎠/㎡(旧基準レベル) | すき間が多く、隙間風や冷気の侵入を感じやすい。断熱性能を生かしにくく、冬季や夜間の寒さが強くなる可能性がある。 |
| 約2.0 ㎠/㎡(高気密とはいえないが許容範囲) | 隙間がやや減るため冷暖房効率が改善するものの、外気の影響が残りやすく、快適さを実感しづらい場面もある。 |
| 約1.0 ㎠/㎡(高気密住宅の目安) | すき間が少なくなり、冷暖房効率が明らかに向上。隙間風が入りづらく、温熱環境が安定しやすくなる水準。 |
| 約0.5 ㎠/㎡以下(理想水準) | すき間がごくわずかで、冷暖房効率や温熱の安定性が非常に高い。隙間風や結露のリスクも低く、快適性・省エネ性が最も高まるレベル。 |
住宅性能を比較する際は「数値を提示してくれるか」「実測値を公開しているか」を確認するだけでも判断材料になります。まずは遠慮せずに工務店へ質問してみるのが安心への第一歩です。
関連記事:滋賀県のおすすめ工務店はこう見つける|信頼できるパートナー選びのポイントと注意点
高気密高断熱の住宅は後悔する?主な噂とリアルな住み心地

「高気密・高断熱」で検索すると、快適さや光熱費の削減といった良い点を紹介する情報が数多く出てきます。その一方で「後悔した」「必要ない」「気持ち悪い」といったネガティブな声も少なからずあります。なぜここまで評価が分かれるのか、不安に感じる方もいるはずです。ここでは、高気密高断熱住宅に関してよく言われる噂を取り上げて、その実態をわかりやすく解説していきます。
空気がこもりやすくアレルギーなどの原因になるって本当?
高気密・高断熱住宅は隙間が少ないため、自然換気が期待できず「空気がこもりやすい」と言われることがあります。その結果、ホコリやハウスダスト、カビの胞子などが室内に滞留し、アレルギー症状を悪化させるのではないかと懸念する声もあります。実際に「高気密住宅にしてから喘息が悪化した」といった体験談も一部では見られます。
一方で、専門的な見解では、気密性そのものが問題なのではなく「換気設計や運用が不十分な場合」に空気のよどみが起こるとされています。計画的な換気システムを備えた住宅であれば、外気の花粉や排気ガスの侵入を抑えつつ、室内のハウスダストや湿気を効率的に排出できるため、むしろアレルギー対策として有効といえます。
つまり、空気がこもって健康被害につながる可能性はゼロではないものの、適切な換気計画と機器の維持管理が行われていれば防げる問題といえます。工務店を選ぶ際は「C値と併せて換気システムをどう設計しているか」を確認しておくことが重要です。
内部結露が原因でカビが発生しやすいって本当?
高気密・高断熱住宅は外気との温度差を抑える設計ですが、「壁の中で結露が起きてカビが生えやすいのではないか」と懸念されることがあります。断熱材の隙間や防湿層の施工不良があると、室内の湿った空気が壁内部に入り込み、見えない部分で水滴が発生するケースは実際に報告されています。これを放置すると断熱材の性能低下や木材の腐朽につながり、構造の耐久性を損なうリスクがあります。
ただし、正しく断熱・気密施工が行われ、通気層や換気計画が確保されていれば内部結露は防ぎやすいとされています。むしろ気密性が低い住宅のほうが湿気が入り込みやすく、カビの温床になりやすいといえます。つまり、内部結露のリスクは「高気密だから起きる」のではなく「施工や換気が不十分だから起きる」と考えるのが妥当です。工務店を選ぶ際は、C値やUA値の数値だけでなく、断熱材の施工方法や気密測定の有無も必ず確認しておくことが大切です。
窓が小さくて息苦しいって本当?
高気密・高断熱住宅というと「断熱性能を優先するあまり窓が小さく、閉塞感があるのでは?」と不安に思う人もいます。確かに昔は断熱性能の低いアルミサッシを避けるために窓を減らす設計が見られました。その影響から「窓が小さい=息苦しい」という印象が広まった面もあります。
ただ現在は樹脂サッシやトリプルガラスなど高性能な窓が普及し、大きな窓でも断熱性を確保できるようになっています。そのため採光や眺望を確保しながら、気密性と断熱性を両立することが可能です。実際に住んで「窓が小さくて息苦しい」と感じるのはむしろ少数派で、多くは従来より明るく快適に暮らせるよう工夫されています。設計段階で窓の配置や大きさをどう考えているか、工務店に確認することが安心につながります。
住んでいると気持ち悪い感じがするって本当?
ネット上では「高気密・高断熱住宅に住むと空気が重く感じる」「なんとなく気持ち悪い」といった声も見られます。これは、隙間が少ないことで自然換気が働かず、空気がこもったように感じるケースや、湿度や温度が適切に調整されていないことが原因と考えられます。
一方で、実際には適切な換気システムを備えた住宅であれば空気の入れ替えが計画的に行われ、室内の二酸化炭素濃度や湿度も安定します。その結果、むしろ外気の花粉や排気ガスの影響を受けにくく、快適さを実感しやすいという声が多数です。「気持ち悪い」と感じるのは換気が不十分な場合や、施工不良で結露やカビが発生している場合が多いとされます。
つまり、高気密・高断熱そのものが不快感を生むわけではなく、換気計画や施工精度が不足している住宅で起こりやすい問題です。工務店を選ぶ際は、気密測定の有無や換気設計の内容まで確認しておくことが安心につながります。
関連記事:失敗しない工務店の選び方|滋賀で家を建てる人が知っておくべき7つのポイントと設定ステップ
快適な高気密・高断熱住宅に住むためのポイント5選

前述のとおり、高気密・高断熱住宅に対するネガティブな声の多くは、性能そのものではなく施工や管理の不備が原因といえます。つまり「高気密・高断熱が悪い」のではなく、「工務店の技術や対応力によって差が出る」というのが実際のところです。多くの工務店は基準を満たした施工を行っていますが、中には配慮が不足してトラブルにつながるケースもあります。ここでは、安心して快適に暮らすために押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
断熱・気密性能を数値で示し実測データを公開する工務店を選ぶ
高性能住宅というのは、設計上の数値だけで語るものではありません。本当に大事なのは、実際に建ててから測定した性能を公開しているかどうかです。たとえば、UA値やC値を完成時に測定して数値を出し、それを住まい手に提示できる工務店は、施工体制に自信があるという証拠になります。
家を建てる際には「UA値やC値の設計値だけでなく、実測値を公表していますか?」と必ず質問してみましょう。また、その測定条件(時期、気象、測定機器)も聞くと比較可能性が高まります。
計画換気の方式と風量バランスを適切に設計する
高気密住宅では換気計画がとても重要です。各部屋に空気が行き渡り、給気と排気のバランスがとれているかどうかで住み心地が変わります。確認する際は「換気計画を数値で示しているか」「完成時に風量測定を行っているか」を聞いてみると判断の材料になります。
良い工務店であれば「〇月の施工例では風量差を10%以内に収めています」「引き渡し時に測定結果をお渡ししています」といった具体的な回答が返ってきます。逆に「大丈夫です」「問題ありません」とだけ答える会社は、測定や数値公開をしていない可能性があり注意が必要です。
性能にこだわった断熱材を選ぶ
断熱材を選ぶ際に重要なのは「種類」だけではありません。断熱性能を示す熱伝導率や厚み、湿気に対する強さ、そして施工方法まで含めて確認する必要があります。設計段階で断熱材の種類と性能値を提示してくれる工務店であれば、比較がしやすく安心です。
また、どれほど高性能な断熱材でも、継ぎ目が切れていたり厚みにばらつきがあると性能は大きく落ちてしまいます。そのため、現場での施工精度をどう確保しているか、実際に気密測定を行って断熱効果を検証しているかが重要な判断材料になります。地域の気候や予算に応じて、最適な断熱材を提案できるかどうかが、工務店の力量を見極めるポイントです。
関連記事:家の断熱材は何がいい?種類一覧と性能ランキングで徹底比較
引渡し後も換気点検や保証制度が整った会社を選ぶ
高気密・高断熱住宅では、引渡し後の維持管理が住み心地に直結します。とくに換気システムはフィルター清掃や風量点検を定期的に行うことで本来の性能を発揮します。工務店によっては、1年・3年・5年などの節目で換気点検を実施し、測定結果を記録として残してくれるケースもあります。
保証制度についても、構造や断熱性能だけでなく、換気設備やサッシなど生活に直結する部分まで含んでいるかを確認することが重要です。契約前に「どこまで保証対象になるか」「不具合が起きた場合の対応フロー」を具体的に説明できる工務店なら、長期的に安心して任せられます。過去にその工務店を利用した人の口コミや評判をチェックしてみるのも有効です。
断熱・気密施工に強い経験豊富な工務店を選ぶ
断熱材やサッシそのものが高性能でも、施工精度が低ければ本来の性能は発揮されません。たとえば、断熱材の継ぎ目に隙間があったり、防湿シートがしっかり貼られていなかったりすると、結露や気流の侵入が起きやすくなります。こうした細部の仕上がりは図面からは分からず、施工現場での技術力と経験に大きく左右されます。
工務店を選ぶ際には、過去に高気密・高断熱住宅をどれくらい手がけているかを確認することが大切です。C値測定の実績や、完成した住宅の平均値を公開しているかも施工力を判断する材料になります。また、施工中に第三者検査を受けているか、現場を公開して見学できるかも信頼性の指標です。経験豊富な工務店であれば「この地域で年間〇棟、C値0.5前後を安定して出しています」といった具体的な説明をしてもらえます。
滋賀県の工務店「スムース」の高気密・高断熱へのこだわり
![]()
スムースは滋賀の気候に合わせて、高気密・高断熱を標準仕様とした家づくりを行っています。性能面だけでなく、素材や施工方法にも独自のこだわりを持ち、快適さと安心を両立させることに力を入れております。最後にスムースの高気密・高断熱へのこだわりについて解説します。
UA値0.46以下・断熱等級6を満たす高水準の断熱性能
私たちスムースの家は、草津市をはじめとする地域で HEAT20 G2グレード(断熱等級6) を満たす水準を標準としています。UA値は0.37〜0.44と国の基準を大きく上回り、冷暖房の効率が高く、年間を通して快適に過ごせる性能を実現しています。同じUA値でも敷地条件や日当たりによって暮らしやすさは変わりますが、私たちは地域の気候や環境を考慮した設計を行うことで、数字以上の心地よさを体感できる住まいをつくっています。
セルロースファイバーを活かした断熱と調湿性能
私たちが採用しているセルロースファイバーは、古紙を再利用した環境にやさしい断熱材です。専用の機械で隙間なく吹き込むため、配管まわりや構造材の端部にも均一に充填でき、熱橋と呼ばれる“すき間”を生じさせません。その結果、断熱性能を長く維持できる住まいを実現しています。
さらに、木質繊維ならではの調湿性によって室内の湿度を自然にコントロールし、夏はジメジメ感を抑え、冬は過度な乾燥を和らげます。音を吸収する効果も高いため、快適で静かな暮らしを支える素材としてご提案しています。
全棟で気密測定を実施しC値0.5以下を基準に施工
私たちスムースでは、すべての建物で気密測定を実施し、C値0.5以下を基準として施工しています。C値とは、住宅の延床面積に対してどれだけ隙間があるかを示す指標で、数値が小さいほど気密性が高いことを意味します。
気密性が高い家は、冷暖房の効率を最大限に引き出すだけでなく、壁内に湿気が入り込むのを防ぎ、内部結露や建物の劣化を抑える効果があります。施工段階で測定を行い数値を確認することで、設計どおりの性能をお客さまに確実にお届けできる体制を整えています。
びわこ産材と自然素材を活かした快適な住環境
スムースの家づくりでは、滋賀県の気候に適したびわこ産材をはじめとした自然素材を積極的に取り入れています。無垢の木材やセルロースファイバーなどには、湿度を自動的に調整する働きがあり、夏場の蒸し暑さをやわらげ、冬の乾燥を抑える効果を発揮します。
さらに、自然素材ならではの肌触りや香りが心地よさを生み出し、人工的な建材では得られない落ち着いた空気感を住まい全体に広げます。地域資源を活かした設計により、長く住むほど快適さを実感できる住環境を実現しています。
長期保証と充実したアフターサポート体制
私たちは家を建てて終わりではなく、そこから始まる暮らしを長く支えていくことを大切にしています。お引渡し後は約40項目以上にわたる定期点検を実施し、住まいの状態を細かくチェックします。
さらに、住宅瑕疵担保保険をはじめ、最長20年の構造保証や地盤保証など、安心して暮らし続けられる仕組みを整えています。万一のトラブルにも迅速に対応できる体制を備えているため、入居後も不安なく住み続けていただけます。家づくりだけでなく、その後の暮らしも含めてお客さまをサポートしていくことが、私たちスムースのこだわりです。
スムースでは、性能を数字だけでなく実際に体感いただけるよう、定期的に完成見学会を開催しています。今回の記事では高気密・高断熱についてご紹介しましたが、耐震性や自然素材の活用など、ほかにも私たちのこだわりはたくさんあります。家づくりで気になることがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)