滋賀で耐震住宅を建てるなら?失敗しない工務店選びと地震に強い家づくりのポイント
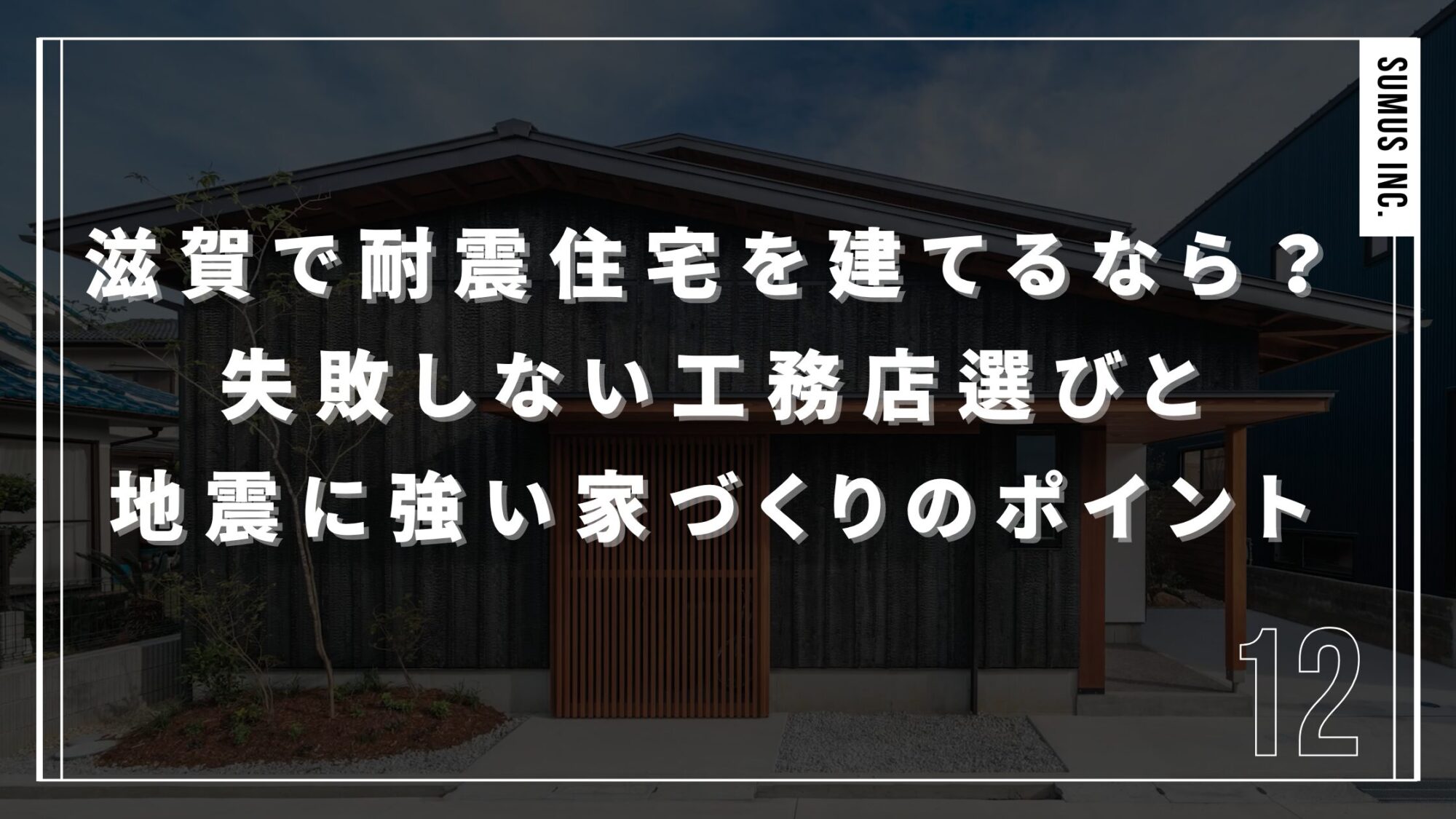
日本は災害が多い国として知られていますが、その中でも特に被害が大きいのが地震です。近年は短いスパンで大きな揺れが起きており、将来的に「南海トラフ地震」が来るとも言われています。これから家を建てるなら、「耐震」は欠かせないポイントといえるでしょう。
しかし、知識がないままでは、地震に強い住まいづくりにこだわることはできません。この記事では、耐震住宅の基本から、地震に強い家づくりのポイント、信頼できる工務店の見つけ方まで、滋賀で家を建てる方に役立つ情報をわかりやすくお伝えします。
耐震住宅とは?まず知っておきたい基礎知識

耐震住宅と聞くと、なんとなく地震に強い家というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。とはいえ、一般的な住宅と何がどう違うのかまで詳しく理解している人は多くありません。まずは「耐震住宅とは何か」を正しく理解することが、後悔のない家づくりの第一歩です。ここでは、地震対策の考え方や耐震等級の基礎について解説します。
耐震・制震・免震の違い
地震対策としてよく聞く「耐震」「制震」「免震」には、それぞれ異なる役割があります。まず耐震は、建物そのものを頑丈にして揺れに“耐える”構造です。柱や梁を強化したり、壁に筋かいを入れたりして、揺れに踏ん張る力を持たせます。
一方で制震は、建物に取り付けた「ダンパー」などの装置が揺れを吸収する仕組みです。特に高層建築では、上の階ほど揺れが大きくなるため、制震によってその揺れを抑える効果があります。
そして免震は、地盤と建物の間に特殊な装置を入れて、揺れ自体を建物に伝わりにくくする構造です。強い地震でも建物が大きく動かず、家具の転倒や内装への被害も軽減されやすくなります。それぞれの特性を理解しておくことが大切です。
耐震等級とは?1・2・3の違いと意味
耐震住宅は、耐震性能に応じて「耐震等級」という指標で評価されます。これは2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくもので、建物の強さを3段階で示す仕組みです。
等級1は建築基準法の基準を満たす水準で、震度6〜7クラスの地震で倒壊しない程度。等級2はその1.25倍の強度があり、主に学校や病院など災害時の避難所にも使われます。最も高い等級3は、等級1の1.5倍の耐震性を持ち、大地震のあとも住み続けられる可能性が高まります。
これから長く暮らす住まいを考えるなら「耐震等級3を標準とする」ことが基本です。希望する工務店がどの等級に対応しているかは、設計前にしっかり確認しておきましょう。
なぜ「耐震等級3」が推奨されているのか
耐震等級3は、現行の建築基準法(等級1)の1.5倍の地震力に耐える最高ランクの性能です。このレベルは、警察署や消防署といった防災拠点にも採用されるほどの強さがあります。大地震のあとも建物の損傷が少なく、避難所に頼らず住み続けられる可能性が高いのが大きな特徴です。
また、修繕費の抑制や資産価値の維持といった面でも有利です。さらに、住宅ローンの優遇や地震保険の割引が適用されることもあり、経済的なメリットも得られます。家族の安全と暮らしを長く守るためにも、新築時は等級3を前提に検討することが推奨されます。
耐震住宅のメリットと魅力

耐震住宅に住む理由として、地震の被害を最小限に抑えることはもちろん重要です。ただ、耐震にしっかりこだわって家を建てることには、それだけではないさまざまなメリットがあります。安全性の向上に加えて、経済面や暮らしの安心にも関わるポイントがあるため、総合的に考えることが大切です。
ここでは、耐震住宅の主な魅力や得られる効果についてわかりやすく紹介していきます。
万が一の地震でも命と財産を守れる
耐震住宅の最大のメリットは、大きな地震が起きたときに命を守る確率を高められることです。柱や梁、壁の配置を工夫して建物を頑丈にすることで、倒壊リスクを大きく抑えられます。さらに、耐震等級2以上で設計された家であれば、震度6〜7クラスの揺れにも耐えうるとされており、家の中にとどまっても安全性が高いといえます。
また、建物が壊れにくければ、家具や家電などの財産を守ることにもつながります。地震はいつ起きるかわかりませんが、その「もしも」に備えられるのが、耐震住宅の大きな魅力です。
地震後の修繕費を最小限に抑えられる
建物の倒壊や損傷が少なければ、当然ながら地震後の修繕にかかるコストも抑えられます。耐震性が低い住宅では、基礎のひび割れや柱の損傷、外壁の剥落などが起きやすく、修理に多額の費用がかかることもあります。一方、耐震住宅は構造全体で地震力を分散させる設計がされているため、被害を最小限にとどめやすいのが特徴です。
特に耐震等級3の住宅では、大きな揺れを受けても主要構造部が無事で済むケースが多く、補修費用や仮住まいの負担を減らせます。災害後の生活再建をスムーズに進める意味でも大きなメリットといえるでしょう。
住宅ローン減税や保険料にも好影響があるケースもある
耐震性能の高い住宅には、金銭面でのメリットもあります。たとえば、耐震等級2以上の家は「長期優良住宅」として認定されやすく、住宅ローン減税の控除額が拡大されたり、補助金の対象になったりする場合があります。また、地震保険についても、耐震等級1で10%割引、等級2で30%、等級3では最大50%の保険料割引が適用される制度があります。
これは保険会社が「被害を受けにくい住宅」と判断している証拠ともいえます。建築時のコストはやや上がる場合があるものの、長期的には家計にもプラスに働くのが耐震住宅の利点です。
耐震住宅の注意点とよくある誤解

耐震住宅は、地震に強い安心感がある一方で、すべてが万能というわけではありません。性能が高いからこそ、事前に理解しておくべき注意点も存在します。ここでは、よくある誤解や見落としがちなポイントについて、実際に家を建てる前に知っておきたい視点から解説します。
「耐震等級3」でも揺れはゼロにならない
耐震等級3は非常に優れた性能を持ちますが、「地震の揺れを感じなくなる」というわけではありません。耐震構造は建物自体の強度を高めて揺れに“耐える”考え方なので、地盤からの揺れはそのまま建物全体に伝わります。特に2階建て以上の住宅では、上の階ほど揺れが大きく感じられる傾向があります。
また、家具や家電が転倒する可能性もあるため、室内の安全対策も欠かせません。建物の倒壊は防げても、暮らしの安心を守るには工夫が必要です。家具の固定や転倒防止グッズの活用など、住まいの中でもできる備えをあわせて行うことが大切です。
設計・施工次第で性能に差が出るリスク
耐震住宅は「等級が高ければ安心」と思われがちですが、実際には設計や施工の精度によって性能に差が出ることがあります。たとえば、耐震等級3の家であっても、構造計算が不十分だったり、現場での施工精度が甘かったりすると、本来の強さが発揮されない場合があります。
また、間取りや開口部のバランスによっても、揺れへの耐性が変わってきます。安心して暮らすためには、耐震等級の数字だけでなく、「どのように計算・設計されているか」「誰が施工しているか」にも注目することが重要です。構造計算の内容を説明してくれる工務店や、施工実績が豊富な会社を選ぶと安心です。
建物だけでなく地盤対策も重要
どれだけ建物の耐震性を高めても、弱い地盤の上に建ててしまえば意味がありません。地盤が軟弱な場所では、揺れが増幅されるだけでなく、地盤沈下や液状化といったリスクも高まります。耐震住宅の性能は、しっかりした地盤の上に成り立つものです。そのため、建築前には「地盤調査」を行い、その結果に応じた地盤改良や基礎設計を検討する必要があります。
工務店によっては簡易調査のみで済ませてしまう場合もあるため、調査内容や改良方法まで確認しておくと安心です。耐震性を本当に活かすためには、建物と地盤の両方に目を向けることが欠かせません。
株式会社スムースでは、お客様に安心してご相談いただけるよう、これまでに手がけた住まいの実績をすべて公開しています。また、定期的に見学会やセミナー、体験イベントも開催しております。滋賀周辺で家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。新築だけでなく、リノベーションのご依頼にも対応しています。
耐震性能を高めると価格はどれくらい変わる?

耐震性能にこだわって住宅を建てるうえで、多くの方が気になるのがその費用です。ただ、初期費用の内容について知るだけでなく、それが将来的にどれだけ安心につながるのかという視点も欠かせません。ここでは、耐震性能に関わるコストの内訳と、長期的な価値について見ていきます。
仕様によって変動するコストの内訳
耐震性能を高めるには、構造面の強化だけでなく設計・評価・施工の各工程にコストがかかります。たとえば耐震等級3を取得する場合、まず「構造計算」に20〜40万円ほど、次に「住宅性能評価」の申請費用が10〜40万円程度かかります。そして実際の補強工事費用として、構造用合板の追加や梁の強化などに数十万〜数百万円が上乗せされることもあります。
これらをすべて合計すると、1棟あたりの相場はおおよそ100万〜150万円前後が目安とされています。プラン内容や施工会社によって前後するため、事前に詳細な見積もりを確認することが大切です。
高コストでも安心が長く続くコストパフォーマンス
耐震性能を高めるには一定の費用がかかりますが、それによって得られる安心と価値は長期的に見て非常に大きなものです。たとえば、耐震等級3の住宅は地震後も住み続けられる可能性が高く、修繕費や仮住まい費用を抑えられます。また、地震保険の割引や住宅ローン控除など、経済面での優遇も受けられることがあります。
さらに、将来的に売却や相続を考えたとき、耐震性能が高い家は資産価値の面でも有利です。初期コストは確かに上がりますが、それは「災害に備えた投資」であり、命や暮らし、資産を守る保険のような役割を果たします。長い目で見れば決して高い買い物ではありません。
耐震住宅のコストを抑えるには補助金制度の活用がおすすめ

耐震住宅にこだわって家を建てると、一般的な住宅に比べて100〜150万円ほどコストが上がることがあります。ただし、補助金制度を上手に活用すれば、こうした費用を抑えることも可能です。実際、国や滋賀県、各市町村では、耐震性能や長期優良住宅などを対象とした支援制度が用意されています。
ここでは、どんな補助金があるのか、また申請時に気をつけたいポイントなどを解説します。
国や滋賀県・市町村の支援制度とは
耐震や住宅に関する支援制度は複数あり、国が支援するものとして「グリーン住宅支援事業」があります。
□制度内容
省エネ性能に加え、長期優良住宅・ZEHなどの高性能住宅を対象とした補助制度。
□対象・条件
・耐震等級2以上を取得することが補助の条件の一つ。
・完成戸建て1戸あたり、省エネや耐震など複数要件を満たす必要があります。
□補助金額
最大 160万円/戸(高性能住宅の条件を満たした場合)。
※耐震性能の向上と省エネ住宅化を同時に補助してくれます。
このほかにも、各自治体独自の補助制度や、子育て世帯・高齢者世帯向けの優遇措置などが設けられている場合があります。また、住宅政策や防災対策の見直しによって、新たな支援制度が創設されることも十分に考えられます。最新の情報をこまめにチェックし、自分に合った制度を見逃さないことが大切です。
関連記事:GX志向型住宅とは?補助金の条件・申請方法・必要な設備までわかりやすく解説
関連記事:自然素材の家に使える補助金制度とは?|制度の種類・条件・注意点まで分かりやすく解説
補助金を活用するための申請の流れ
補助金制度は内容によって申請方法や時期が異なりますが、実際の手続きは多くの場合、施工を担当する工務店が代行してくれます。たとえば国のグリーン住宅支援事業では、登録事業者である工務店が申請主体となり、必要書類の準備や提出までを一括で対応します。そのため、施主が煩雑な手続きを行う必要はほとんどありません。
ただし、制度を利用するには事前の準備や工事のタイミングに条件がある場合もあるため、打ち合わせの際に「補助金の活用を考えている」と一言伝えておくとスムーズです。予算枠が限られている制度もあるので、早めに相談するのがおすすめです。
耐震住宅を建てる際の工務店選びのポイント

耐震住宅を建てるうえで、最も重要といえるのが工務店選びです。優れた耐震設計があっても、それを形にするのは工務店の技術と対応力です。土地の状態に応じた設計や、現場での施工の丁寧さが、地震に強い家づくりには欠かせません。ここでは、安心して任せられる工務店を選ぶためのポイントを紹介します。
耐震等級3の取得実績があるか
耐震等級3とは、国が定めた「住宅性能表示制度」によって認定される耐震性能の指標です。この制度では、設計図面や現場の施工状況をもとに、第三者機関が耐震性を評価し、等級1〜3のいずれかが付与されます。つまり、等級3を取得するには、設計段階での「設計性能評価」と、完成後の「建設性能評価」の両方を受け、その結果として「住宅性能評価書」が交付されている必要があります。
工務店を選ぶ際は、「これまでに等級3を正式に取得した建物を何棟建てているか」を確認しましょう。施工事例に評価書の有無が書かれていたり、見学会で現物を見せてもらえたりする会社であれば信頼できます。また、「全棟で等級3を標準化しているのか」「申請はオプション扱いなのか」といった運用面の違いも、事前に確認しておくことが大切です。
構造計算や地盤調査をどこまで行っているか
耐震性の高い住宅を建てるには、設計上の「構造計算」と土地の状態を調べる「地盤調査」の精度が極めて重要です。構造計算には、簡易な「壁量計算」と、構造部材ごとの応力を精密に検証する「許容応力度計算」の2種類があります。耐震等級3を取得するには原則として後者が必要ですが、木造住宅では法的義務がないため、簡易計算で済ませている工務店もあります。
地盤調査についても、方法(スウェーデン式/ボーリング)や調査深度、解析の正確性によって、適切な基礎設計ができるかが決まります。調査が甘いと不同沈下や建物の揺れ増幅などのリスクを高める原因になります。
工務店を選ぶ際は「全棟で許容応力度計算を実施しているか」「地盤調査の方法は何か」「その結果をもとに基礎設計を行っているか」といった点を具体的に聞いてみましょう。また、地盤保証制度への加入の有無もあわせて確認が必要です。こうした技術的な部分を“標準仕様”として扱っている工務店であれば、安心して任せることができます。
第三者機関による認定・証明を受けているか
工務店を選ぶ際は「第三者機関による評価を受けた住宅の実績があるか」「評価書の写しを提示できるか」といった点をしっかり確認しましょう。具体的には、住宅性能表示制度に基づく「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」や「長期優良住宅の認定通知書」などの取得実績があるかを尋ねることがポイントです。
こうした情報は、見学会や相談時に「この物件は住宅性能評価を取得していますか?」「認定の根拠となる評価書を見せてもらえますか?」と聞くことで確認できます。また、工務店の公式サイトや施工事例ページで「耐震等級3取得済み」「評価機関による検査済」などの記載があるかをチェックするのも有効です。
評価機関名や発行年月日まで開示できるかが、信頼性の目安になります。曖昧な説明に終始する工務店は、慎重に検討すべきです。
過去の施工事例・お客様の口コミや評判
工務店の信頼性を判断するうえで欠かせないのが、これまでに手がけた「施工事例」と「施主の声」です。いくらカタログ上で立派な説明がされていても、実際に耐震等級3の住宅をどれだけ建てたのか、どんな仕上がりになっているのかを確認しなければ、本当の実力はわかりません。
施主のインタビューや口コミも重要な判断材料です。「契約前にどんな説明があったか」「完成後に評価書がきちんと交付されたか」「地震の揺れに実際どう感じたか」など、リアルな声に目を通してみましょう。GoogleクチコミやSNS、第三者サイトでの評判もチェックし、悪い評価にも目を通すことが大切です。
特に「施工後の対応が丁寧だった」「耐震性に関する説明が明確だった」といった声が多ければ、信頼できる工務店である可能性が高いでしょう。見学会に参加し、直接質問してみるのも有効な手段です。
関連記事:失敗しない工務店の選び方|滋賀で家を建てる人が知っておくべき7つのポイントと選定ステップ
関連記事:滋賀県のおすすめ工務店はこう見つける|信頼できるパートナー選びのポイントと注意点
滋賀県で耐震住宅を建てるなら「スムース」にお任せください

滋賀県にある工務店「スムース」は、自然素材と丁寧な設計にこだわり、家族が心地よく暮らせる住まいを提案しています。無垢材や漆喰といった国産素材を用い、時を重ねるごとに味わいが深まる家を追求。素材の選定から環境への配慮まで、次世代につなぐ視点を大切にしています。ここでは、そんなスムースが取り組む住まいの耐震へのこだわりをご紹介します。
全棟で「許容応力度計算×耐震等級3」を初回プランから標準化
私たちスムースでは、全棟で許容応力度計算による耐震等級3の取得を、初回提案から標準化しています。これは、構造部材にかかる力を一つずつ解析する高度な構造計算であり、建築基準法の最低基準を大きく上回るものです。2016年の熊本地震では、震度7クラスの地震が短期間で2度発生しました。この実例から、繰り返しの大地震にも耐えられる構造こそが本当に安心できる家だと確信し、私たちはこの計算手法を全棟で採用しています。
震度7が繰り返されても耐える設計思想と構造検証
震度7の地震が1回だけではなく、複数回発生する可能性を前提とした設計が、これからの家づくりには欠かせません。スムースでは、熊本地震の被害調査を通じて「繰り返す強震」に備える重要性を強く認識しました。そのうえで、単に耐震等級3を満たすだけでなく、構造のバランスや破壊の起点になりにくい設計を心がけています。一度の揺れだけでなく、繰り返される衝撃に耐えるための根拠ある設計思想と構造検証が、私たちの強みです。
柱・梁ごとの応力まで精密に確認する高度な構造計算
許容応力度計算は、柱・梁・耐力壁など、すべての構造部材ごとに力の流れと応力を個別に検証する計算手法です。多くの住宅で採用されている「仕様規定」や「性能表示計算」と比べて、解析範囲が格段に広く、数百ページに及ぶ詳細な構造計算書を作成します。安全性の裏付けが明確で、耐震等級3の根拠を可視化できる点も特徴です。スムースでは、設計に手間とコストをかけてでも、この高精度な構造計算を全棟で実施しています。
耐震性と自由な間取りを両立するハイブリッド工法を採用
耐震性と設計自由度は、どちらかを優先すればもう一方が犠牲になるとされがちです。スムースではその両立を目指し、在来軸組構法と2×4工法を融合させた「ハイブリッド工法」を採用しています。面で力を分散させる構造的な強さを持ちながらも、開口部を大きく確保しやすく、間取りの自由度が高い点が特長です。暮らし方や将来の変化に柔軟に対応できるこの工法により、許容応力度計算で構造バランスを確保しながら、住まい手の希望に沿った空間づくりを実現しています。
「劣化対策等級3」で耐震性能を長期間維持
いかに耐震性能が高くても、それが長く保たれなければ意味がありません。スムースでは、住宅性能表示制度における最上位の「劣化対策等級3」を取得し、構造材の耐久性にもこだわった設計・施工を行っています。湿気や腐朽による劣化を防ぐため、通気や防腐処理を徹底し、構造材の強度を長期にわたり維持。許容応力度計算で得られた耐震性能を、将来にわたって発揮し続けられる住まいを提供しています。
株式会社スムースでは、お客様に安心してご相談いただけるよう、これまでに手がけた住まいの実績をすべて公開しています。また、定期的に見学会やセミナー、体験イベントも開催しております。滋賀周辺で家づくりをご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。新築だけでなく、リノベーションのご依頼にも対応しています。
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)