断熱等級とUA値で変わる!夏の暑さ対策に強い家を選ぶポイント
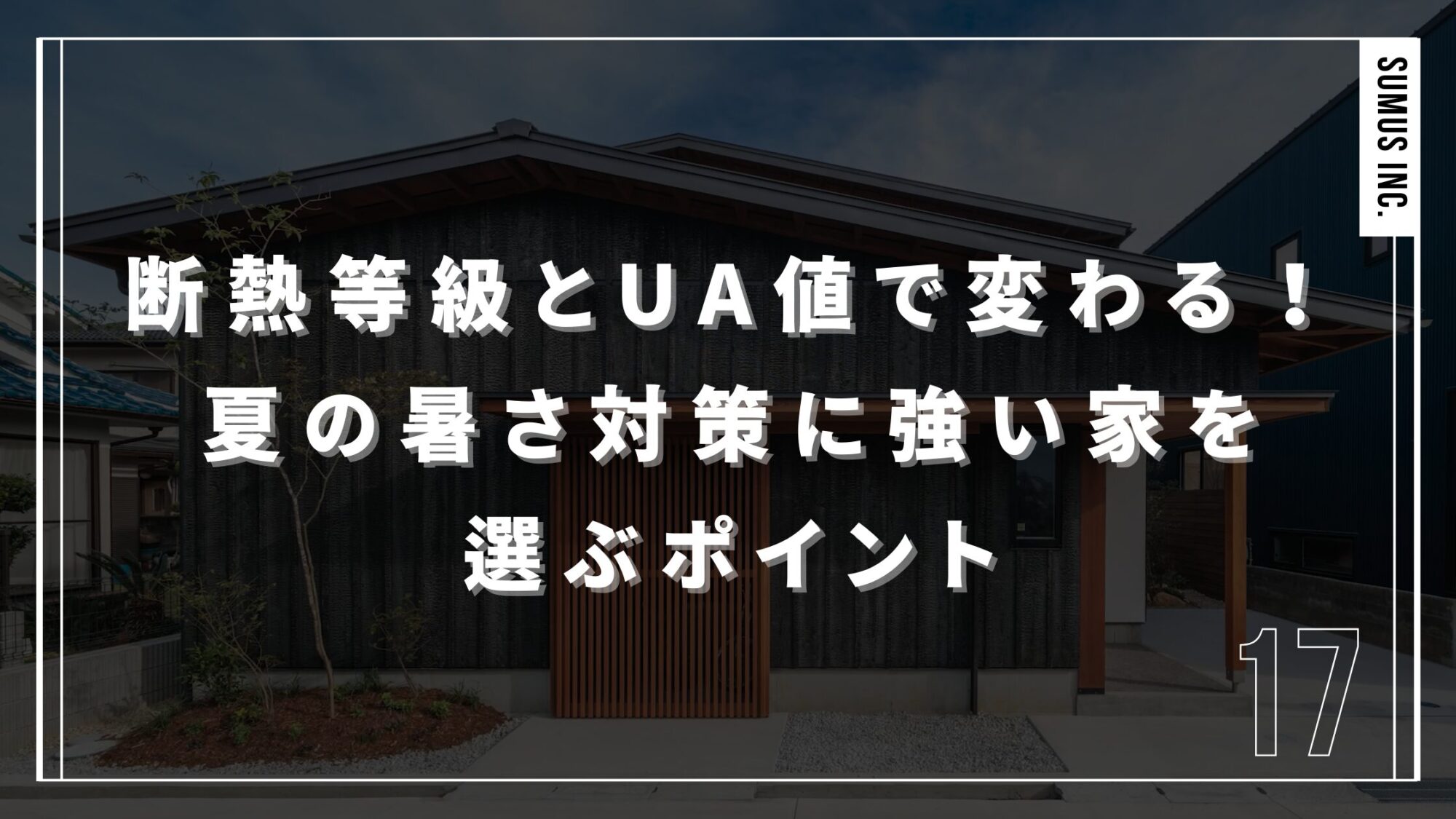
家づくりで多くの方が悩むのが「夏の暑さ対策」です。特に蒸し暑い地域では、外気の熱が室内にこもりやすく、冷房に頼りすぎてしまうケースも少なくありません。そこで重要になるのが家の「断熱性能」です。断熱性を高めれば、夏は涼しく冬は暖かい快適な空間を実現でき、光熱費の削減や健康面にもつながります。
この記事では、断熱等級やUA値をもとに、暑さに強い家を選ぶポイントをわかりやすく解説していきます。
家の中が暑くなる主な原因

家の中が夏場に暑く感じられるのは、外気温だけが理由ではありません。建物のつくりや性能によっても、室内の温度上昇には大きな差が生まれます。ここでは家の中が暑くなる主な原因について解説します。
天井や屋根などの断熱性能が低い
夏の熱は屋根からの影響がとても大きく、天井の断熱が不十分だと室内温度が上がりやすくなります。屋根裏は日中に40~60℃にも達し、夜になっても熱がこもったまま下へ伝わるため、寝苦しさの原因となるのです。冷房を使っても天井表面が熱いと、室温に比べて体感が暑く感じられます。
逆にしっかり断熱されていれば、天井の表面温度も均一に保たれ、28℃程度の室温でも快適に過ごしやすくなるでしょう。睡眠の質低下や熱中症リスクを防ぐ意味でも、屋根部分の断熱は欠かせません。
日差しをうまく遮れていない
室内に侵入する熱の大半は窓からで、特に夏は7割以上がここから入るといわれています。アルミサッシや一枚ガラスの窓は熱を通しやすく、日射が直接差し込むと一気に室温が上昇してしまいます。冷房を強めても、直射日光の影響を抑えない限り根本的な改善は難しいでしょう。
遮熱性の高い窓や、外部からの日差しをコントロールする工夫を取り入れることが、快適さを守るポイントとなります。窓対策を怠ると光熱費が跳ね上がり、省エネ面でも不利になるので注意が必要です。
室内に熱がこもりやすい構造になっている
部屋の暑さは外気だけでなく、内部で発生する熱も大きな要因です。冷蔵庫や照明、テレビなどの家電は稼働中に熱を放出し、締め切った空間ではこもりやすくなります。さらに昼間に受けた日射の熱も加わるため、帰宅時に部屋がむっとするのはそのせいです。
計画的な換気やサーキュレーターで空気を循環させれば、こもった熱を逃がすことができます。断熱や通風設計を工夫することで、室内環境は大きく改善されるでしょう。特に高齢者は体温調整が苦手なため、熱ごもりは健康被害のリスクにも直結します。
家の暑さで悩まないためには「断熱性能」で家を選ぶことが大切

暑さ対策を重視した住まいを実現するうえで、家づくりの段階で最も大切になるのが「断熱性能」です。断熱性の高い家は外気の熱を室内に伝えにくく、冷房の効きが良くなるため、真夏でも快適に過ごしやすくなります。逆に断熱が不十分な家では、室内がすぐに熱を帯びてしまい、冷房を強めても効率が悪く電気代もかさむでしょう。
断熱性能とは、屋根や壁、床、窓といった外気と接する部分を通して、熱がどれだけ出入りしにくいかを示すものです。性能が優れていれば室温が安定し、体感的にも涼しく感じられる効果があります。また断熱材の質や厚み、施工精度、さらには窓の素材やガラスの構造なども性能を大きく左右します。
次の章では、この断熱性能を数値で比較できる「断熱等級」や「UA値」について解説していきます。
関連記事:家の断熱性能と光熱費の関係|光熱費を抑えるための工夫とチェックポイントを紹介
断熱等級別「暑さの感じやすさと室内環境の違い」

断熱性能は家の涼しさに直結しますが、見た目だけでは判断が難しいものです。そこで目安となるのが「断熱等級」です。国の基準に基づいた等級は、数字が大きいほど性能が高いことを示し、快適さの目安になります。ここでは、等級ごとに夏の暑さの感じ方や室内環境の違いを解説していきます。
断熱等級4(昔の省エネ基準)|夏の暑さが残りやすい家
断熱等級4は、1999年に定められた省エネ基準に対応する性能で、当時は一般的でした。しかし現在の猛暑環境では十分とはいえません。夏は昼間に取り込んだ熱が夕方以降も抜けにくく、夜になっても寝苦しさが残りやすいのが特徴です。冷房を強めても効率が悪く、電気代がかさみやすいのもデメリットといえるでしょう。
イメージとしては、夜になっても室内の空気がじんわり重たく、窓を開けてもなかなか涼しさを感じられない状態です。家族の快適さや健康面を考えると、より高い等級を視野に入れる必要があります。
断熱等級5(ZEH水準)|冷房が効きやすく過ごしやすい家
断熱等級5は、ZEH(ゼロ・エネルギー住宅)の普及を見据えて設けられた基準です。等級4と比べると格段に冷房効率が高まり、強く運転しなくても室内を涼しく保ちやすくなります。夏の日差しを受けても夕方には室温が安定しやすく、冷房を切ってもしばらく快適さが続くのが特長です。
冬も暖房が効きやすく、家全体の温度差が小さくなるため、廊下やトイレでも寒暖差を感じにくくなります。標準的な新築住宅で多く採用される水準で、省エネと暮らしやすさを両立できるレベルといえるでしょう。
断熱等級6(高断熱G2相当)|エアコン効率が高く涼しさを保ちやすい家
断熱等級6は、より快適性を求める住まいに適した高性能な基準です。夏は直射日光を受けても室温が上がりにくく、冷房設定を弱めても涼しさが長時間続きます。家全体の温度差が小さいため、廊下や脱衣所でも熱がこもりにくく、どの部屋も過ごしやすいのが魅力です。
真夏に帰宅してもむわっとした暑さが少なく、軽く冷房を入れるだけで快適さが戻るイメージです。冷暖房にかかるエネルギーを抑えつつ健康的な生活がしやすくなる、長期的に見ても安心できる水準といえるでしょう。
断熱等級7(最高水準G3相当)|外気の暑さをほとんど感じない家
断熱等級7は、現在国内で想定される最高レベルの基準です。外気の影響をほとんど受けないため、猛暑日でも冷房を弱めに設定するだけで安定した涼しさを維持できます。例えるなら、魔法瓶のように外の熱を遮断し、室温を穏やかに保てるイメージです。
冬も暖房の熱が逃げにくく、朝まで一定の温度が続くため、ヒートショックなどのリスク低減にもつながります。光熱費を大幅に抑えながら、一年を通して快適で安心できる暮らしを実現できる、先進的な断熱性能です。
家の暑さの感じやすさは「UA値」でも判断できる

家の断熱性能を考えるときには、断熱等級だけでなく「UA値」も大切な目安になります。UA値とは「外皮平均熱貫流率」と呼ばれ、屋根や壁、床、窓など外と接する部分から、どれくらい熱が逃げやすいかを数値で表したものです。UA値が小さいほど熱が伝わりにくく、断熱性能が高い住まいといえます。
断熱等級とUA値は、どちらも断熱性能を示すための指標ですが役割が少し異なります。等級は国が定めた基準をクリアすれば認定される「ランク表示」で、UA値はその裏にある「具体的な点数」です。
イメージすると、学校の成績で「A〜Dの評定」が等級、「テストの得点」がUA値にあたります。両方を見ることで、自分の家がどのレベルで、実際どれほど快適さにつながるかを理解しやすくなるでしょう。
UA値別に見る「夏の暑さの影響度」

UA値は、家の屋根や壁、床、窓といった外と接する部分から、どれくらい熱が逃げやすいかを数値で表したものです。外皮全体の面積をもとに計算されるため、家全体の断熱性能を客観的に示すことができます。ここでは、代表的なUA値の水準ごとに、実際の住み心地や室内環境にどんな違いが生まれるのかを解説します。
UA値0.87前後(断熱等級4)|室温が上がりやすく暑さを感じやすい
UA値0.87前後は、従来の省エネ基準に相当する水準で、現在では最低限の性能といえます。日中に取り込んだ熱が夕方まで残りやすく、夜になっても室内が蒸し暑く感じられることが多いのが特徴です。冷房を強めても効率が悪く、設定温度を下げてもすぐに暑さが戻る傾向があります。
夏場は「部屋が冷えにくい」「涼しさが続かない」と感じやすく、快適な暮らしを求める方には物足りなさが残るレベルです。結果として、家族全員が長時間冷房に頼る生活になりやすいでしょう。
UA値0.60前後(等級5・ZEH水準)|一定の涼しさを保ちやすい
UA値0.60前後は、ZEH水準にあたる性能で、一般的な新築住宅で多く採用されています。この水準では外気の熱がある程度遮られるため、冷房を弱めても室内の涼しさを維持しやすいのが特長です。真夏の午後でも等級4に比べて室温が上がりにくく、帰宅時にむわっとする暑さが軽減されます。
冷房効率が高まることで、家族全員が過ごすリビングだけでなく廊下や寝室も快適に保ちやすくなるでしょう。省エネと快適さのバランスを求める人にはちょうどよい水準といえます。
UA値0.46前後(等級6相当)|冷房効果が長持ちし涼しく過ごせる
UA値0.46前後は、高断熱仕様とされる等級6相当の水準です。外からの熱の侵入が少なく、夏の冷房効果が長持ちするのが大きなメリットです。冷房を弱めても涼しさが続くため、室温が安定して過ごしやすくなります。夕方以降の熱残りも小さく、寝室や廊下など家全体で暑さを抑えやすいのが特徴です。
等級4の家では冷房を切るとすぐに暑さが戻りますが、この水準では体感温度がゆるやかに変化し、快適さを保てる時間が長くなります。長く住むほど違いを実感できる断熱性能といえるでしょう。
UA値0.26前後(等級7相当)|外気の暑さをほとんど感じないレベル
UA値0.26前後は、最高水準の等級7に相当し、外気の影響をほとんど受けにくい性能です。猛暑日でも冷房を少し運転するだけで室内の涼しさが保たれ、家全体が穏やかな温度に保たれます。窓を閉め切っていても蒸し暑さを感じにくく、夜間も快適に眠れる住環境が実現するでしょう。
断熱性能が高い分、冷房に頼る時間が大幅に減り、体への負担も小さくなります。家族の健康や長期的な暮らしやすさを重視するなら、最も安心できるレベルです。
スムースの家は、断熱等級6(HEAT20 G2)・UA値0.46以下を確保しており、国の基準を大きく上回る性能です。冷房効率を高めて涼しさを長く維持できるほか、断熱材には再生紙を活用した「セルロースファイバー」を採用。隙間なく充填できるため熱橋を防ぎ、調湿性や防音性にも優れています。
家づくりで暑さを抑えるための工夫5選

断熱等級やUA値は、家全体の断熱性能を表す大きな指標です。ただ、実際の住み心地を左右するのは屋根や壁、窓といった部位ごとの性能や設計の工夫でもあります。つまり「全体評価」を高めることはもちろん大切ですが、より細かくこだわれば、夏の暑さをさらに和らげることも可能です。ここでは、家づくりの中で特に注目したい5つの工夫を紹介します。
高断熱材を選んで室内の暑さを防ぐ
断熱材は屋根や壁の内部に施工され、外気の熱を家に伝えにくくする役割を持ちます。種類によって熱を通しにくい性能や調湿性が異なり、グラスウールやセルロースファイバー、発泡プラスチック系などがあります。断熱性能が不足すると、屋根裏の熱が室内に伝わり、冷房の効率が大きく下がってしまいます。
実際に家づくりで検討する際は、工務店に「どの断熱材を採用しているか」「厚みや施工方法は基準を満たしているか」を確認してみましょう。既存住宅なら天井裏や床下に断熱材を追加するリフォームも可能です。隙間なく施工されているかどうかも快適さを左右するため、施工精度について質問するのも大切です。
関連記事:家の断熱材は何がいい?種類一覧と性能ランキングで徹底比較
窓とドアの断熱・遮熱性能を高める
夏の熱は窓から多く入り込みます。冷房時に屋外から入る熱の約73%が開口部由来というデータがあり、優先的に対策すべきは窓まわりです。複層ガラスやLow-E複層ガラス、樹脂サッシへ変更すると熱の出入りを大きく抑えられます。さらに、外付け日よけや庇で直射日光そのものを遮ると、冷房の効きが安定して室温も落ち着きやすくなります。
実際に家づくりで検討する際は、工務店やハウスメーカーに「選べる窓の種類は?」「Low-E複層や樹脂枠は標準仕様か?」を確認すると安心です。既存住宅であれば、内窓の追加や外付けスクリーン、すだれの設置といったリフォームで効果を得られます。国の補助制度が利用できるケースもあるため、相談時にあわせて確認してみると導入しやすいでしょう。
気密性を上げて熱気の侵入を防ぐ
どれほど断熱材が優れていても、家に隙間が多ければ外の熱気が入り込み、冷房の涼しさが逃げてしまいます。気密性とは家全体の「すき間の少なさ」を示し、気密性能が高いほど室温を安定させやすくなります。特に夏場は屋根裏や壁の隙間から熱が入り込みやすいため、断熱と気密はセットで考える必要があります。
実際に検討する場合は、工務店に「気密測定(C値測定)を実施しているか」を尋ねてみましょう。測定を行っていない場合は性能が保証されにくいため注意が必要です。既存住宅では、サッシまわりや配管部分の隙間を塞ぐ簡易リフォームでも効果があります。
日差しをコントロールするパッシブ設計を取り入れる
建物の形状や窓の位置によって、日差しの入り方は大きく変わります。夏は直射日光を遮り、冬は日差しを取り込む設計を「パッシブ設計」と呼びます。庇やルーバー、植栽を組み合わせることで、冷房に頼りすぎずに快適さを得られるのがメリットです。
家づくりの際は、間取りの打ち合わせ時に「南向きの窓に庇をつけられるか」「日射シミュレーションに対応しているか」を確認してみましょう。既存住宅では、すだれや外付けシェードを取り入れるだけでも直射日光を和らげられます。小さな工夫でも体感温度は大きく変わるため、早めの対策がおすすめです。
省エネ冷房設備を効率的に活用する
いくら断熱や遮熱を高めても、冷房の使い方が非効率では室内は快適になりません。省エネ型のエアコンや換気システムを適切に利用することで、少ない消費電力で涼しさを保てます。また、サーキュレーターと併用すれば冷気が循環し、室内全体の温度差を小さくできます。
検討段階では「最新の省エネ性能を持つ機種を導入できるか」「換気設備と冷房を連動させられるか」を確認してみると安心です。既存住宅でも、エアコンのフィルター清掃やサーキュレーターの設置など、手軽にできる工夫で効率が大きく改善します。
すでに建っている家でできる暑さ対策5選
![]()
家を建てる際には断熱性能を高めることが暑さ対策の基本ですが、すでに住んでいる家でも工夫次第で快適さを高めることは可能です。また、断熱リフォームを組み合わせれば効果はさらに高まります。ここでは、今ある住まいでもすぐに取り入れやすい暑さ対策を5つ紹介します。
カーテンやスクリーンで直射日光をカットする
夏の強い日差しは、窓から直接室内に入り込み、室温を一気に上げる原因となります。特に南向きや西向きの窓では、冷房を効かせても追いつかないほど熱がこもりやすくなります。そこで有効なのが、遮熱効果のあるカーテンやロールスクリーンです。一般的なレースカーテンでも直射日光を和らげますが、遮熱加工のある生地を選ぶとより効果的に熱の侵入を防げます。
実際に取り入れる際は、「窓枠全体をしっかり覆えるサイズか」「床まで届く長さか」を確認することがポイントです。隙間があると熱が入り込むので、幅も高さも余裕を持って選ぶと安心です。また、日差しが強い時間帯だけ閉めるのではなく、日が当たり始める前から使うことで効果を最大限発揮できます。
グリーンカーテンやすだれで外から熱を遮る
グリーンカーテンとは、ゴーヤやアサガオなどのつる性植物をネットに這わせてつくる「植物のカーテン」のことです。直射日光を葉でさえぎると同時に、植物が水分を蒸発させる蒸散作用によって周囲の温度を下げる効果があります。人工的な遮熱材ではなく自然を利用する方法として注目されています。
実際に設置する際は、窓から少し離して風が通るようにするのがポイントです。グリーンカーテンなら、夏の日差しが強い時期にぐんぐん成長する植物を選ぶと手入れも簡単です。すだれを使う場合は外壁や窓枠にしっかり固定し、隙間を減らすことで効果が高まります。外側で光を遮ると、冷房の効率が上がり省エネにもつながります。
エアコンとサーキュレーターを併用して効率を上げる
冷房を強くしても空気が循環しなければ、部屋の中に温度のムラが生まれ、涼しさを感じにくくなります。サーキュレーターを併用することで冷気が部屋全体に行き渡り、設定温度を上げても快適さを保ちやすくなります。結果的に電気代の節約にもつながります。
使う際は、エアコンから出た冷気を部屋全体に広げるように、壁や天井に向けて風を送るのがポイントです。上方向に風を当てることで空気が循環し、冷気が床付近まで行き渡ります。寝室では足元に扇風機を置き、空気をかき混ぜるだけでも効果が感じられます。
除湿機で湿気を減らし体感温度を下げる
同じ気温でも湿度が高いと体感温度は上がり、蒸し暑さを感じやすくなります。除湿機は空気中の水分を取り除くことで、体感温度を下げて快適さを高める効果があります。冷房の設定温度を下げすぎなくても涼しさを感じやすくなるのがメリットです。
取り入れる際には、部屋の中央や空気がこもりやすい場所に置くと効率的です。特に梅雨時や寝室では効果が出やすく、エアコンの除湿機能と併用すればさらに快適になります。タンクの容量や排水方法も確認し、生活スタイルに合った機種を選ぶことが大切です。
天井や屋根裏に断熱材を追加して熱ごもりを防ぐ
築年数の経った住宅では、天井や屋根裏の断熱材が不足していることがあり、真夏には屋根裏が高温になって室内まで熱が伝わります。断熱材を追加すれば熱の侵入を抑え、冷房効率が上がり夜の寝苦しさも軽減できます。
費用の目安は工法によって異なり、屋根裏に吹き込む非破壊工法なら20〜50万円、天井を解体して入れ直す工法では50〜90万円ほどが一般的です。30坪前後の住宅全体では60〜70万円前後になるケースもあります。まずは工務店に既存の断熱材の状態を調べてもらい、厚みや施工精度を確認しながら最適な方法を選ぶことが大切です。
セルロースファイバーやグラスウールなど種類も複数あるため、性能とコストのバランスを比較して検討すると安心です。
株式会社スムースは「断熱等級6 × UA値0.46」で夏の暑さを感じにくい家を実現
家の中が暑くなる大きな要因は、屋根や窓から入り込む日射や、室内にこもる熱気です。これを根本的に防ぐには、家全体の断熱性能を高めることが欠かせません。断熱等級やUA値はその性能を示す代表的な指標で、数値が優れているほど外気の影響を受けにくく、夏も涼しく快適な住まいを実現できます。
スムースの家は、断熱等級6(HEAT20 G2)に相当し、基準となるUA値0.46以下クラスとなります。国の基準を大きく上回る水準で、冷房効率を高めて快適さを長く維持します。さらに、新聞紙を再利用した断熱材「セルロースファイバー」を採用し、細部まで隙間なく充填できるため熱橋が生じにくく、調湿性や防音性にも優れています。滋賀の気候に合わせた高性能住宅を検討するなら、ぜひスムースにご相談ください。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)