焼杉は本当に後悔するのか?外壁材のメリットや注意点・価格までプロが解説
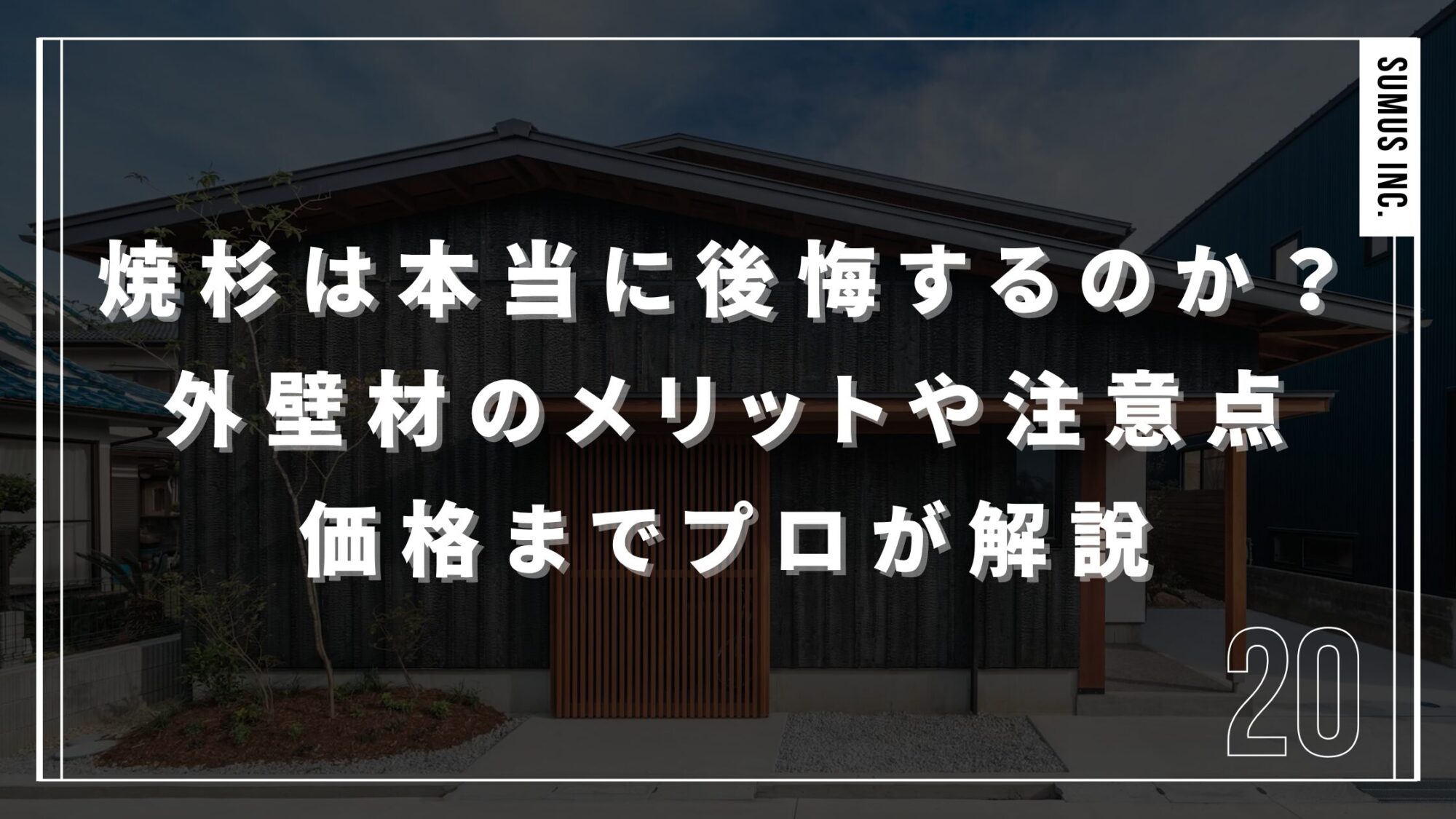
家の外壁は雨風から建物を守るだけでなく、住まいの印象を決める大切な要素です。近年は木材だけでなく、タイルや金属、サイディングなど多様な素材が使われており、デザインの幅も広がっています。その中でも「焼杉」は、表面を焼いて耐久性を高めた日本の伝統技法であり、自然素材ならではの美しさと機能性を両立できるとして再評価されています。
とはいえ、特性や注意点を理解しないまま採用すると「思っていた仕上がりと違う」「手入れが大変」と後悔につながる場合もあります。この記事では、焼杉のメリット・デメリット、価格の目安、種類や施工のポイントまでわかりやすく解説していきます。
焼杉とは表面を焼いて耐久性を高めた日本伝統木材のこと

焼杉とは、杉板の表面をあえて焼くことで耐久性を高めた外壁材です。焼くことで炭の膜ができ、腐朽や虫害を防ぎながら独特の風合いを生み出します。近年はタイルや金属など多様な外壁材がある中で、自然素材ならではの質感を活かせる素材として再び注目されています。
地域によって形や焼き方が異なり、昔ながらの手法から現代的な加工まで種類も豊富です。ここでは、焼杉がどのように発展してきたのか、その歴史と「三角焼き」など代表的な作り方について詳しく解説します。
焼杉の歴史
杉は日本で育ちやすく、古くから家の外壁や板張りに使われてきました。特に瀬戸内のような湿気の多い地域では、腐りにくく長持ちさせるために杉を焼く方法が考え出されます。試行錯誤の中で「表面を炭にすると虫や雨に強くなる」とわかり、焼杉という技術が定着しました。やがて地域ごとに焼き加減や仕上げの工夫が生まれ、独自の景観をつくる文化として発展します。
しかし工業製品のサイディングが広まると、手間のかかる焼杉は使われにくくなりました。一方で自然素材への関心が高まったことで、風合いや環境性が評価され、近年はデザイン性の高い外壁として再び注目されています。
焼杉の作り方
焼杉の作り方は大きく2種類あり、現在主流なのはバーナーを使った工業的な製法です。工場で杉板を並べ、高温のバーナーで表面を均一に炭化させるため、量産しやすく品質を一定に保てます。仕上げも調整しやすく、炭を残すものから塗装を加えるタイプまで幅広く加工できます。
一方、昔ながらの伝統技法が「三角焼き」と呼ばれる手焼きです。杉板を三枚合わせて三角形の筒状に組み、内部で火を燃やすことで煙突効果を起こし、内側を一気に焼き上げます。この方法は手間と技術が必要ですが、炭化層が厚く硬くなり、はがれにくいという特徴があります。近年はデザインや耐久性の違いを活かすため、用途に応じて製法や仕上げを選ぶケースが増えています。
関連記事:岡山の旅
焼杉の外壁の施工価格

焼杉の外壁にかかる費用は「材料の種類」「施工方法」「防火対策」の違いによって大きく変わります。一般的なサイディングと比べて初期費用が高いと言われるため、どれくらいの価格になるのか具体的に知りたい方も多いでしょう。ここでは、材料費の目安から1棟あたりの概算、コストを左右するポイントまで詳しく解説します。
材料費の目安
焼杉の材料費は、1㎡あたり5,000~12,000円前後が一般的です。ただし「どのように焼くか」「仕上げをどうするか」によって価格が大きく変わります。同じ焼杉でも、素焼き・塗装仕上げ・伝統的な手焼き(三角焼き)では性能も見た目も異なるため、詳細は工務店へ確認する必要があります。
| 価格帯(1㎡あたり) | 主な仕上げ・製法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 5,000〜8,000円 | 素焼き(炭を残す) 機械によるバーナー焼き |
量産しやすく比較的安価で品質が一定。 費用を抑えたい人に向いている。 |
| 8,000〜12,000円 | 炭を軽く落とすタイプ 色を整える塗装仕上げ |
見た目がきれいで均一。 デザイン性と扱いやすさのバランスが良い。 |
| 12,000円〜以上 | 伝統的な三角焼き(手焼き) | 炭化層が厚く耐久性が高い。 職人の手作業で生産量が限られる。 |
上記のように、焼杉は「どのように焼くか」「どこまで仕上げるか」で価格も性能も大きく変わります。単に“高い・安い”で判断するのではなく、見た目の好み・メンテナンス性・耐久性のどれを重視するかによって最適なグレードを選ぶことが大切です。また、ほとんどの人が㎡単価よりも「結局1棟でいくらかかるのか?」を知りたいと感じるため、次の項目では一般的な住宅を例に総額の目安も紹介します。
施工内容や防火対策で価格が大きく変わる
焼杉の外壁は材料費だけでなく、施工方法や防火基準への対応によって総額が大きく変わります。同じ焼杉を使っていても、「どこに建てるか」「どんな仕様で張るか」で費用が数十万〜100万円以上変動することも珍しくありません。
| 影響する要素 | 内容・理由 |
|---|---|
| 外壁の面積や形状 | 凹凸や窓が多いほどカットや調整が必要になり、施工手間が増えて費用が上がる。 |
| 張り方・施工方法 | 横張り・縦張り・本実張りなどで工数が変わる。通気層の有無でもコストが異なる。 |
| 役物(やくもの)部材 | コーナー材や見切り材などの専用部材が必要。素材によって価格が上下する。 |
| 足場・下地・撤去費 | 外壁リフォームでは足場代や既存外壁の撤去費が発生。新築とは費用構成が大きく異なる。 |
| 防火地域での仕様 | 準防火地域や法22条区域では不燃下地・大臣認定構成などが必要となり、材料・施工費が大きく増える。 |
戸建てのおおよその費用については、工務店に相談してみるとよいでしょう。そのうえで、さらに素材や工法にこだわったり、コストを下げたりすることも可能です。
初期費用は高めだが長期的には安くなることもある
焼杉はサイディングより初期費用が高くなる傾向がありますが、耐久性やメンテナンスの少なさを考えると、長期的にはむしろコストを抑えられる場合があります。表面の炭化層が雨や紫外線による劣化を防ぎ、虫や腐朽にも強いため、張り替えの時期を大きく延ばせます。特に三角焼きによる焼杉は炭化層が厚く、40年以上ほとんど傷んでいない例もあるほどです。
一方で窯業系サイディングは約10年ごとに再塗装が必要で、30年前後で張り替えるケースが一般的です。塗装費や足場代を何度も支払うことを考えると、初期費用の差が将来的に逆転することも珍しくありません。外壁は家の寿命を左右する部分です。短期の価格だけで判断せず、「どれくらい長く快適に暮らしたいか」という視点で比較することが大切です。
関連記事:滋賀の安い工務店は本当にお得?後悔しない選び方と注文住宅の賢い建て方を解説
焼杉が外壁材として選ばれる8つのメリット

外壁に焼杉を採用するか迷う際は、素材の特性を正しく知ることが重要です。ここでは、暮らしに直結する実利とデザイン面の強みを、根拠とともに解説します。
黒く深みのある質感で高い意匠性を演出できる
焼杉の外壁は、表面を焼いて炭化させることで生まれる独特の黒さと深みが最大の魅力です。塗装のような均一な黒ではなく、光の当たり方で表情が変わり、建物全体に奥行きや重厚感を与えます。表面の凹凸によって木目も自然に浮かび上がり、素材そのものの存在感を楽しめるのも特徴です。
さらに時が経つほど色味が落ち着き、風景になじむような味わいが増していくため、経年変化を楽しみたい方にはぴったりです。和風だけでなく、ガルバリウムやコンクリートなど無機質な素材との相性も良く、シンプルな住宅でも外観に個性と高級感をプラスできます。
炭化により防虫・防腐効果が高く長持ちする
木材は本来、湿気や虫に弱く、外壁に使うには劣化が心配されがちです。しかし焼杉は、表面を炭化させることで木の弱点を大きく改善しています。炭化層には栄養分がなく乾燥しているため、シロアリや腐朽菌が寄りつきにくく、カビの発生も抑えられます。さらに炭化層は雨をはじき、紫外線のダメージから素地を守る役割も果たします。
特に三角焼きなどの手焼き製法では炭化層が厚く、表面が硬く締まることで、傷がつきにくく長期間美しさを保ちやすい点が特徴です。結果として張り替え時期を大きく延ばすことができ、自然素材でありながら耐久性に優れた外壁として選ばれています。
炭化層により燃え広がりにくい耐火性がある
「木だから燃えやすいのでは?」と心配されやすいですが、焼杉は表面が炭化しているため、むしろ一般的な木材よりも火が広がりにくいという特性があります。炭は熱を通しにくく、断熱材のような役割を果たすため、炎が当たっても内部まで一気に燃え進まないのが大きなポイントです。実際に、火災時に焼杉の外壁が“表面だけが黒く焦げ、内部は無傷”だったという例もあります。
ただし、完全に不燃ではないため、防火地域では下地材や構造で性能を補う設計が必要です。それでも「延焼を遅らせる」という点で安心感があり、安全性とデザイン性を両立できる外壁材として高く評価されています。
湿度を調整し結露を防ぐ「木材ならではの調湿効果」
焼杉は木材ならではの“呼吸する外壁”とも言われ、周囲の湿度に合わせて水分を吸収・放出する性質があります。湿気の多い季節には余分な水分を吸い込み、乾燥時にはゆっくり放出するため、外壁内部に湿気がこもりにくく、結露やカビの発生を抑える効果があります。
特に日本のように梅雨や夏の湿度が極端に高くなる気候では、通気層と組み合わせることで内部の構造材まで守れる点が大きな強みです。また、外壁全体で空気の流れをつくることで、室内の温度ムラを抑え、年中快適な住環境を維持しやすくなります。素材の美しさだけでなく、住みやすさにも貢献する、機能的な自然素材といえます。
一般的な外壁材より軽く建物への負担が少ない
焼杉は木材を加工した外壁材のため、窯業系サイディングやタイル外壁に比べて非常に軽いことが特徴です。外壁が軽いと建物全体の重量が抑えられ、基礎や構造材への負担を軽減できます。特に地震時には、建物が重いほど揺れの影響を受けやすくなるため、軽量な焼杉は耐震性の面でも有利です。
また、施工時に扱いやすく、職人が板を持ち上げたり調整したりする作業もスムーズになるため、作業効率の向上にもつながります。素材が軽いぶん、将来的に張り替えや部分補修を行う際にも扱いやすく、長く住むほどそのメリットを実感しやすくなります。デザイン性だけでなく、構造の安定性やメンテナンス性にも配慮された外壁材です。
熱を伝えにくく夏でも表面が熱くなりにくい高断熱性
焼杉の表面にできる炭化層は、見た目だけでなく“熱を伝えにくい膜”としても働きます。金属系サイディングのように日差しを受けて表面が高温になることが少なく、真夏でも手で触れられるほど温度上昇が抑えられます。表面が熱くなりにくいということは、外壁から室内への熱の侵入も抑えられるため、冷房効率の向上にもつながります。
また、木材自体が空気を含んだ構造をしているため、断熱材のような役割を持つ点も見逃せません。「黒い外壁=暑い」というイメージとは逆に、実際はむしろ涼しさを保ちやすい素材です。季節による温度差が大きい日本の気候において、焼杉はデザイン性だけでなく“暮らしやすさ”の面でも優れた外壁といえます。
上塗りや張り替えがしやすくメンテナンス性に優れる
焼杉は「お手入れが大変そう」と思われがちですが、実はメンテナンスのしやすさも大きな魅力です。表面が炭化しているため汚れが目立ちにくく、多少の色あせも味わいとして自然になじみます。もし色味を整えたい場合は、上から塗装を重ねることができ、塗料の密着性も良いため再仕上げも比較的簡単です。
また、板状の素材であるため、傷んだ部分だけを一枚単位で張り替えることができ、全面交換しなくても見た目を保ちやすい点もメリットです。サイディングのようにコーキングの劣化を定期的に直す必要も少なく、結果的にメンテナンス費用と手間を抑えられます。「手がかかる素材」ではなく「必要なときにだけ手を入れやすい素材」として、長く安心して使える外壁材です。
CO₂を蓄える環境素材で癒し効果も高い
焼杉は杉そのものを使うため、製造段階で大量のエネルギーを必要とせず、コンクリートや金属に比べて二酸化炭素の排出量が少ない素材です。木材は成長過程でCO₂を吸収しており、建材として使われている間はその炭素を内部に蓄え続けるため、環境負荷の少ない“カーボンストック材”としても注目されています。
また自然素材ならではの温かみや香りがあり、視覚的にも心理的にも落ち着きやすい空間をつくれる点も魅力です。無機質な外壁に比べて周囲の景観となじみやすく、住む人だけでなく周囲の人にもやさしい印象を与えます。SDGsやサステナブルな住宅づくりが重視される中で、焼杉は“環境性能”と“癒し”の両方を兼ね備えた外壁材として選ばれています。
関連記事:自然素材の家はデメリットも味方にできる!?後悔しないための考え方
焼杉で後悔しないために知っておきたい5つのデメリット
![]()
焼杉は魅力の多い外壁材ですが、自然素材だからこそ注意すべき点もあります。事前にデメリットを理解しておくことで、「思っていたのと違った」「手入れが大変だった」と後悔するリスクを減らすことができます。ここでは、実際に起こりやすい5つのポイントを解説します。
自然素材のため木目や色のばらつきがある
焼杉は天然の杉を使っているため、一本一本で木目や色味に違いが出ます。さらに表面を焼く工程でも火の当たり方や炭化の度合いに微妙な差が生まれるため、仕上がりが均一にはなりません。工場で規格通りに仕上げられるサイディングと比べると、色ムラや濃淡が気になる場面もあるでしょう。
ただし、これは“欠点”である一方、焼杉ならではの深みや味わい、唯一無二の風合いにつながる魅力でもあります。もし均一な仕上がりを求めるなら、炭を落として塗装したタイプを選べば色をそろえやすくなります。自然素材らしさを楽しむか、デザインを優先するかによって仕上げを選べば、大きな不満なく採用できます。
乾燥や環境によって割れ・反りが起こることがある
焼杉は木材を使っているため、湿度や気温の変化によって膨張・収縮を繰り返します。その際に内部へ力がかかり、表面に細かな割れや反りが生じることがあります。特に南面や西日が強く当たる場所、風雨にさらされやすい面では変形が起こりやすく、長年使用するほど差が出やすくなります。
ただし割れが入っても炭化層が素地を守るため、見た目ほど性能が落ちない点は焼杉の強みです。また、施工時に通気層をしっかり確保したり、適切な厚みの板を使ったりすることで変形を最小限に抑えることができます。自然素材である以上、多少の動きは避けられませんが、正しい施工とメンテナンスによって大きなトラブルは防げます。
塗装で色を固定しにくく経年で退色しやすい
焼杉は表面が炭で覆われているため、一般的な塗料が密着しにくく、色を長期間固定することが難しい素材です。特に素焼きのまま使用する場合は、紫外線や風雨の影響で徐々に色が薄くなり、グレーやシルバーに変化していきます。これを「味わい」と感じる人も多い一方で「イメージしていた黒を保てない」と不満に感じる人もいます。
色をできるだけ維持したい場合は、炭を落として塗装してあるタイプを選ぶか、耐候性の高い塗料を定期的に再塗装する方法が有効です。焼杉は経年変化を楽しむ素材であるという前提を理解し、自分が「どんな色の変化を許容できるか」を考えて仕上げを選ぶことが、後悔を防ぐポイントになります。
表面が炭のため触ると汚れやすい
素焼きの焼杉は、表面に炭化層が残っているため、触れると手や服に黒い粉がつくことがあります。特に玄関まわりや人がよく触れる場所に使うと「汚れが気になる」「子どもが触ってしまう」といった不満につながることもあります。また、雨や風で炭が少しずつ落ちることで、周囲の白い外壁やサッシに色移りするケースもゼロではありません。
ただし、これはあくまで“炭を残した素焼きの場合”の話であり、炭を削って仕上げる「浮造り」や「塗装タイプ」を選べば触っても汚れにくくなります。焼杉を採用するときは、デザインだけでなく設置場所や生活動線も考慮し、「どの仕上げならストレスが少ないか」を選ぶことが大切です。
防火規制により使える地域が制限されることがある
焼杉は木材を使った外壁であるため「防火地域では使えないのでは?」と思われがちです。実際、都市部には「防火地域」「準防火地域」「法22条区域」といった規制があり、素材単体では基準を満たせない場合があります。そのため、焼杉を使うには石膏ボードなどの不燃下地を組み合わせたり、大臣認定を取得した構成で施工したりする必要があります。
これにより、仕様が複雑になったり、費用が上がったりするケースもあります。ただし「焼杉が使えない」というより、「使い方に工夫が必要」と捉える方が正確です。実際、設計力のある工務店であれば、規制に合わせた構成で焼杉を採用することは可能です。事前に相談しながら進めれば、デザインと安全性の両立も十分に実現できます。
焼杉の種類とそれぞれの仕上げの特徴

焼杉の仕上げは大きく「炭を残すタイプ」と「炭を落として塗るタイプ」に分かれます。見た目だけでなく、触り心地やメンテの考え方も変わります。ここでは特徴に加え、どんな人に向くのかも具体的に解説します。
クロ塗装(素焼き)|炭を残した伝統的な仕上げ
素焼きの“クロ”は表面に炭を残し、黒の深みと荒々しい質感が魅力です。ここにクリア塗装を薄くのせたのが“クロ塗装”です。炭を凝固させ、手や服への色移りを抑えます。それでも強く触れる場面では粉が付く場合があり、雪圧で炭が削れやすい環境は不向きです。
玄関まわりや室内は用途選定に注意しましょう。伝統の表情を最大限に活かしたい方、経年の味わいを楽しみたい方に向きます。外装の要所に使うと、陰影が際立ちます。
モダン・ブラック|炭を落として黒く塗装した現代的な仕上げ
炭をブラッシングで落とし、黒塗装で整える仕上げです。触っても手が汚れにくく、均一な黒でモダンな外観に仕上がります。和風にも無機質素材にも合わせやすく、玄関や通学動線など“触れる機会が多い場所”でも扱いやすいのが利点です。色を維持したい場合の選択肢としても有効ですが、塗装ゆえに将来の再塗装計画は前提になります。デザインの統一感、実用性、メンテのバランスを取りたい方におすすめです。
焼杉に関するよくある質問

焼杉の歴史や施工メリット・デメリットについて解説してきましたが、実際に依頼するかを決めるうえで、まだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、焼杉に関する3つのよくある質問に答えていきます。
焼杉はホームセンターでも買える?
焼杉は一部のホームセンターで販売されていることはありますが、外壁用として使える長さ・厚み・品質のものはほとんど流通していません。DIY向けの薄い板や装飾用が中心で、耐久性や寸法が住まいの外壁には不十分な場合が多くあります。実際の住宅に使う場合は、建材メーカーや製材所、焼杉を扱い慣れている工務店を通して注文するのが一般的です。品質にばらつきが出ないため、結果的に安心で長持ちする仕上がりになります。
焼杉の寿命は?
焼杉の寿命は仕上げや環境によって異なりますが、適切に施工された場合は30〜50年以上使えると言われています。特に三角焼きなど伝統的な手法で作られた焼杉は炭化層が厚く、40年以上ほとんど劣化していない実例もあります。サイディングのように10年ごとの再塗装が不要なケースも多く、長期的にはむしろ寿命の長い外壁材です。
50年を超える頃からは部分的な張り替えや上塗りを検討することもありますが、構造自体が傷んでいなければ再利用できるケースもあり、定期的な点検が長持ちの鍵になります。
焼杉はシロアリがきても大丈夫?
焼杉の表面は炭化しており、栄養分が少なく乾いているため、シロアリが好む環境ではありません。炭化層によって食害を受けにくいのは事実です。ただし「絶対に来ない」わけではなく、土台や床下など他の部分から侵入する可能性はあります。自然が多い地域や不安がある場合は、シロアリ対策や保証制度が整っている工務店を選ぶと安心です。「焼杉+適切な防蟻対策」の組み合わせが、家全体の耐久性を高めるベストな方法です。
滋賀周辺で焼杉を採用するなら株式会社スムースにお任せ
焼杉は見た目の美しさだけでなく、耐久性や経年変化の魅力もあり、外壁材として高い価値を持つ素材です。ただし、仕上げや施工の知識がないまま使うと、反りや色あせ、防火への不安などが生まれることもあります。株式会社スムースは焼杉を使った施工事例が複数あり、素焼きや塗装タイプなど仕上げごとの特徴を理解したうえで、建物の形状や立地に合わせて最適な使い方を提案しています。
また、高断熱・高気密・耐震性といった住宅性能にも力を入れており、自然素材の魅力と暮らしやすさを両立させた家づくりができる点が大きな強みです。焼杉を「ただ貼る」のではなく、「長く楽しめる外壁」として設計できる工務店は多くありません。滋賀周辺で自然素材の家や焼杉の活用を検討されている際はぜひお気軽にご相談ください。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)