【滋賀の家づくり】耐震等級3の家は本当に安心?そのメリットとよくある誤解について解説
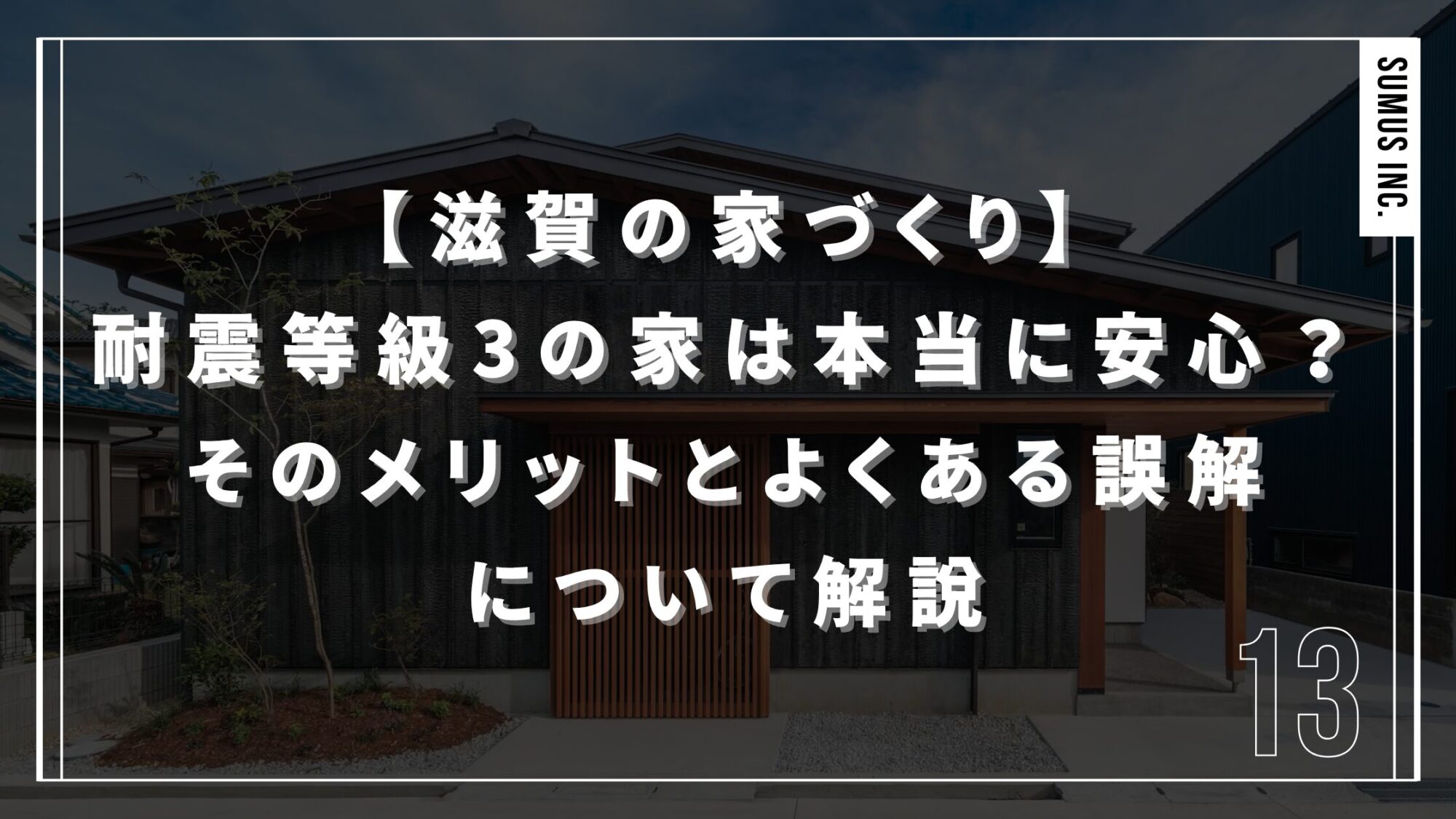
耐震等級3とは?まず知っておきたい基本情報
![]()
耐震等級とは、建物の地震への強さを示す国の基準です。住宅の耐震性を客観的に比較できる指標として使われており、なかでも「等級3」は最高ランクに位置づけられています。ただ、その意味を正しく理解していないと誤解を招くこともあります。ここでは、等級ごとの違いや「等級3」の耐震性、認定にまつわる注意点について解説します。
耐震等級の基準と3つの等級の違い
耐震等級は、住宅の地震への強さを数値で示す国の基準です。建物の耐震性をわかりやすく伝えるため、2000年に施行された「品確法」により導入されました。地震に対する強さの程度に応じて、以下の3段階に分けられます。
・等級1:震度6強〜7程度の地震で倒壊しない性能。ただし、大きな損傷や補修の必要が出る可能性がある。
・等級2:等級1の1.25倍の耐震性能。主に学校や避難所など、災害時の利用を想定した建物で採用されます。
・等級3:等級1の1.5倍の強度。地震後も住み続けられるレベルで、警察署や消防署にも使われる最高ランクの耐震等級です。
耐震等級3はどれほど地震に強いのか
耐震等級3は、住宅性能表示制度において最高レベルの耐震性能とされています。等級1の1.5倍の地震力に耐えることが求められ、大きな地震後でも補修なしで住み続けられる可能性が高いレベルです。実際、消防署や警察署など防災拠点として機能する建物にも、この等級が採用されていることが多く、信頼性の高さがうかがえます。
倒壊を防ぐだけでなく、家族の生活を守り続ける力があるのが等級3の大きな魅力です。
耐震等級3「相当」と「認定」の違いに注意
「耐震等級3相当」という表現には注意が必要です。これは、あくまで等級3と同レベルの設計を目指しているという意味であり、公的な認定を受けた建物とは限りません。認定には構造計算や第三者評価が必要ですが、「相当」の場合はその工程が省略されているケースもあります。
見た目では判断が難しく、耐震性能が明確でないことから、後悔やトラブルにつながる恐れもあります。確かな安心を求めるなら、認定取得済みかを必ず確認しましょう。
関連記事:滋賀で耐震住宅を建てるなら?失敗しない工務店選びと地震に強い家づくりのポイント
「意味ない」「後悔」は本当?耐震等級のよくある誤解

耐震等級について調べていると「意味がない」「後悔した」といった否定的な意見を目にすることがあります。せっかく高い基準で家を建てても、本当に効果があるのかと不安になるのも無理はありません。しかし、そうした声の多くは誤解や情報不足に起因しています。ここでは、よくある勘違いや背景事情を具体的に取り上げながら、正しく理解するためのポイントを解説していきます。
耐震等級3でも壊れる?熊本地震との関連
「耐震等級3でも倒壊した」という話のきっかけになったのが、2016年の熊本地震です。この地震では、震度7クラスの強い揺れが短期間に2度発生し、多くの建物が深刻な損傷を受けました。ただし、実際に全壊した住宅の多くは、耐震等級1以下や未認定の建物だったとされています。
等級3の住宅は倒壊を免れた例が多く、軽微な損傷にとどまったケースも確認されています。一部で被害が出た事例もありますが、その多くは「等級3相当」や設計・施工の不備が原因とされています。
「意味ない」と言われる原因とその誤解
「耐震等級3でも意味がない」と言われる背景には、言葉の誤解と性能への過剰な期待が関係しています。耐震等級3は、どんな地震でも壊れないという保証ではなく、致命的な被害を防ぎ、命を守るための指標です。実際には、倒壊を防ぎつつ、住み続けられる可能性を高める目的で設けられた基準です。
性能を正しく理解していないと、現実とのギャップから「意味がない」と感じてしまうこともあるでしょう。冷静に判断するためにも、制度の正しい意図を知ることが大切です。
「後悔した」という声の背景と回避策
耐震等級3の家にして「後悔した」という声の多くは、耐震性能そのものへの不満ではなく、設計やコスト、間取りへの誤算が原因です。たとえば「窓が小さくなった」「建築費が上がった」「間取りの自由度が減った」など、事前の説明不足や認識のズレが後悔につながるケースが少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐには、取得に伴う設計制約や費用の内訳を事前に理解し、自分たちの要望とのすり合わせを丁寧に行うことが重要です。信頼できるパートナー選びも後悔を避けるカギとなります。
耐震等級3の取得で得られるメリット

耐震等級は、地震による被害を軽減し、命を守るための重要な指標です。とくに等級3は、倒壊リスクの低さを証明できる高水準の基準とされています。ですが、その価値は耐震性だけにとどまりません。実は、住宅の将来性や経済的な面でも意外なメリットがあります。ここでは、耐震等級3を取得することで得られる、さまざまな利点について解説します。
地震保険・固定資産税・ローン優遇などの制度
耐震等級3を取得すると、地震保険の保険料が最大で50%割引される制度があります。これは、耐震性が高いほど被害のリスクが低いと評価されるためです。一方、等級1では割引率が小さく、保険料の負担が重くなる傾向にあります。自治体によっては、固定資産税の軽減措置が設けられている地域もあり、建築時に適用可否を確認しておくと安心です。
また、住宅ローンでは耐震性能の高さが評価され、金利や借入額に差が出るケースもあります。このように耐震等級3は、災害時の安心だけでなく、日常の経済面にも効果を発揮する優れた基準といえるでしょう。
将来の売却価値や資産性の向上
住宅を売却する際、耐震性は買い手が重視する要素のひとつです。なかでも耐震等級3の家は、安全性が数値で証明されているため信頼性が高く、査定で有利になることもあります。反対に、等級が不明な建物や最低限の基準しか満たしていない住宅は、敬遠されやすく資産価値が下がる可能性も否定できません。
また、築年数が経過しても「耐震等級3」の認定が残っていれば、価値維持の根拠として有効に働きます。住み替えや相続を見据えた場合にも、将来的な選択肢を広げてくれる重要な要素といえるでしょう。
長期優良住宅の取得につながる制度的メリット
耐震等級3は「長期優良住宅」の認定条件のひとつに位置づけられています。長期優良住宅とは、国が定めた耐震性や省エネ性、維持管理のしやすさなど、複数の基準を満たす住宅を指します。この認定を受けることで、住宅ローン控除の上限拡大や登録免許税・不動産取得税の軽減措置が適用される場合があります。
さらに、建物の性能が高く評価されるため、資産価値の維持にもつながるでしょう。耐震等級3を満たす家は、認定への第一歩となるだけでなく、制度的にも長期的にも優位性があります。
関連記事:自然素材の家に使える補助金制度とは?|制度の種類・条件・注意点まで分かりやすく解説
関連記事:GX志向型住宅とは?補助金の条件・申請方法・必要な設備までわかりやすく解説
耐震等級3の取得方法と費用の実態
![]()
耐震等級3の家が持つ魅力や安心感について理解を深めた後は「どう取得するのか」「どれくらい費用がかかるのか」など、具体的な仕組みを知っておくことが重要です。制度をよく知らないまま進めると、後から想定外のコストや設計条件に戸惑ってしまうケースもあります。ここでは、耐震等級3の取得に必要な流れや費用、その裏側にある設計や構造のポイントについて、実務に即して解説していきます。
証明書の取得方法と発行までの流れ
耐震等級3を取得している住宅には、第三者機関が発行する「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」が必ず存在します。これらの書類によって、設計段階と建築後それぞれで耐震等級3が認定されたことが証明されます。ただし「等級3相当」と説明する業者もあり、実際には認定を受けていないケースもあるため注意が必要です。
確認すべきタイミングは、契約前と建築完了後の2回です。事前に「性能評価書は発行されますか?」と資料での確認を求めると、無理なく確認できます。また、打ち合わせの際に「等級3相当ではなく、正式な認定かどうかを確認したい」とやんわり伝えるのも有効です。図面や口頭説明だけでは本物かどうか判断できないため、必ず書面で確認しましょう。
建築時にかかる追加費用とその内訳
耐震等級3を取得するには、構造の補強や評価機関による審査に関連した費用が加算されます。一般的に、等級1の家よりも数十万円〜300万円ほど費用が増えるケースが多く、内訳としては構造計算にかかる設計費、性能評価の申請料、必要に応じた柱や梁の補強費などが含まれます。
ただし、これらは建築費全体に上乗せされる形になるため、別途で支払う必要はなく、住宅ローンに組み込めることが一般的です。特別な支払い手続きが増えるわけではないため、過度に心配する必要はありません。むしろ大切なのは、どの内容が耐震等級3の取得に関係しているかを事前に見積もりで確認し、納得したうえで進めることです。不明な項目は早めに業者に聞いておくと安心でしょう。
認定取得に必要な設計・構造上の条件
耐震等級3の家を建てるには、建築基準法を満たすだけでなく、さらに厳密な構造計算が必要です。柱や梁の強度、壁の配置バランス、屋根や吹き抜けの影響なども含めて、全体の構造がしっかり検討されていることが求められます。そのため、間取りの自由度が多少制限されるケースもあります。とはいえ、難しい計算方法を理解する必要はありません。
相談の際は「この間取りで耐震等級3は取れますか?」や「耐震性能に影響が出る部分ってありますか?」と、やわらかく尋ねてみると良いでしょう。その場で丁寧に説明してくれるかどうかも、信頼できる会社を見極めるポイントのひとつになります。不安なまま進めず、納得できるまで質問してみることが大切です。
耐震等級3の家を建てるなら知っておきたいポイント

耐震等級3の内容を理解していても、実際に家を建てるとなると、依頼先の選び方や設計の考え方によって仕上がりに差が生まれます。どの会社に相談すべきか、間取りと耐震性をどう両立させるか、構造計算の内容をどのように確認すればよいかなど、実務的な視点を持つことが重要です。ここでは、家づくりの進行時に押さえておきたい具体的なチェックポイントについて解説します。
ハウスメーカーと工務店の違い
間取りと耐震性の両立は可能か?
耐震等級3を取得する場合、壁や柱の配置に一定の制約が出るため「希望通りの間取りにできないのでは」と不安に感じる方も少なくありません。たとえば大きな吹き抜けや窓の多いプランでは、耐力壁が不足しがちで構造上の調整が必要になることがあります。しかし、早い段階で設計担当と相談すれば、プランの優先順位を整理しながら、安全性とデザインのバランスを取ることは十分に可能です。
大切なのは、間取りの希望を伝えるだけでなく「耐震等級3を前提に、どのような工夫ができるか」を一緒に考えてくれる設計者かどうかを見極めることです。両立には知識と経験が必要ですが、完全に諦める必要はありません。
設計力・構造計算のチェックポイント
耐震等級3の設計力を見極めるには、実績・対応範囲・説明の具体性が鍵です。まずは依頼先のホームページで「許容応力度計算」や「耐震等級3の認定実績」が明記されているかを確認しましょう。掲載例がなければ、国土交通省の「住宅性能表示制度」や、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイトでも、評価機関や登録事例の確認が可能です。
設計提案時には、たとえば「この窓配置だと耐力壁が不足するため、バランスを取るにはここの壁を厚くします」といった、構造と間取りの関係を具体的に説明できるかが重要な判断材料となります。また、構造計算を社内で行っているか、外注かも必ず確認しましょう。資料を見せてもらえるか聞くことも有効です。
滋賀で「耐震等級3の家」を建てるならスムースへお任せください

スムースでは、すべての住宅において初回提案の段階から「許容応力度計算×耐震等級3」を標準で取り入れています。震度7の地震が複数回発生した熊本地震の教訓から、本当に安心できる構造とは何かを見つめ直してきました。命を守るのはもちろん、その後の暮らしや財産も守るために、構造安全を徹底して追求しています。ここでは、スムースの家づくりにおける耐震性能の考え方と取り組みについてご紹介します。
初回提案から「許容応力度計算×耐震等級3」を標準採用
私たちスムースでは、全棟において最初のプラン提案段階から「許容応力度計算」と「耐震等級3」を標準で採用しています。これは構造の安全性を後づけではなく、最初から明確に担保するためです。
設計の自由度と安全性のバランスを取りながら、初期段階から根拠ある構造設計を行うことで、将来的な変更やトラブルのリスクも最小限に抑えることができます。「とりあえず間取りだけ」で進めるのではなく、構造を含めた住まい全体を安心の土台に乗せた提案をお届けする。これが、私たちが大切にしている設計のあり方です。
震度7クラスの揺れを想定した耐震設計と構造検証
スムースが耐震等級3に強くこだわる背景には、熊本地震で起きた「震度7の地震が2度発生する」という現実があります。耐震等級は「1回の地震に耐える」設計が基準ですが、私たちは繰り返し地震にも備えられる住まいをつくるべきだと考えています。そのため、構造計算の結果だけでなく、柱や耐力壁の配置、揺れの力の伝わり方まで想定した構造検証を徹底しています。
数字上の強さだけに頼らず、実際の災害を想定して設計を行うことで、長く安心して暮らせる住まいをご提供しています。
柱や梁の応力を細部まで把握する高度な構造解析
耐震等級3を本当に意味のあるものにするには、構造材1本1本にかかる力を精密に把握する必要があります。スムースでは、すべての構造部材について「許容応力度計算」を実施し、柱や梁、接合部にどの程度の力が加わるかを数値で確認しています。その結果は、数百ページに及ぶ構造計算書としてお客様にご提示可能です。
感覚や経験に頼らず、根拠に基づく設計を徹底することが、命と暮らしを守る構造設計につながると考えています。
耐震性と設計自由度を両立する独自のハイブリッド工法
スムースでは、在来軸組構法と2×4工法の長所を掛け合わせた独自のハイブリッド工法を採用しています。耐震性を面で確保しながら、間取りの柔軟性も実現できる構法です。「大きな開口部を取りたい」「吹き抜けのあるリビングにしたい」といったご要望にも、構造安全を犠牲にすることなく応えることが可能です。
構造とデザイン、どちらか一方を諦めるのではなく、両立を前提とした家づくり。それが、私たちの技術と提案力の強みです。
「劣化対策等級3」により性能を長く保つ住まいづくり
地震に強い構造であっても、それを長期間維持できなければ意味がありません。スムースでは、住宅性能表示制度の中で最高ランクにあたる「劣化対策等級3」を標準で取得しています。これは、構造材の湿気や腐朽、白蟻被害への配慮を徹底し、耐震性能を長く保つための設計・施工が行われている証です。
構造の強さだけでなく、20年後も安心して暮らせる家をつくる。その想いを込めて、一棟一棟ていねいに設計・施工を行っています。
建てた後も安心が続く「住むサポ」と長期保証体制
スムースでは、お引き渡し後の暮らしまで見据えた長期的なサポート体制をご用意しています。定期点検プログラム「住むサポ」では、約40項目以上の点検を通じて住まいの状態を定期的にチェック。住宅瑕疵担保保険は最長20年まで対応し、10年・15年時の点検や必要なメンテナンスも丁寧にご案内しています。
また、地盤保証は30年、構造材の防蟻・防腐には無薬剤で20年対応の「緑の柱」を採用しています。さらに、施工中には第三者機関による10回の現場監査を実施し、その記録をすべてお渡ししています。構造の強さだけでなく、「建てた後の安心」にも責任を持つのが、スムースの家づくりです。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)