「制震」を取り入れた家づくり|滋賀で揺れに強い家を作るポイントや耐震等級との違いを解説
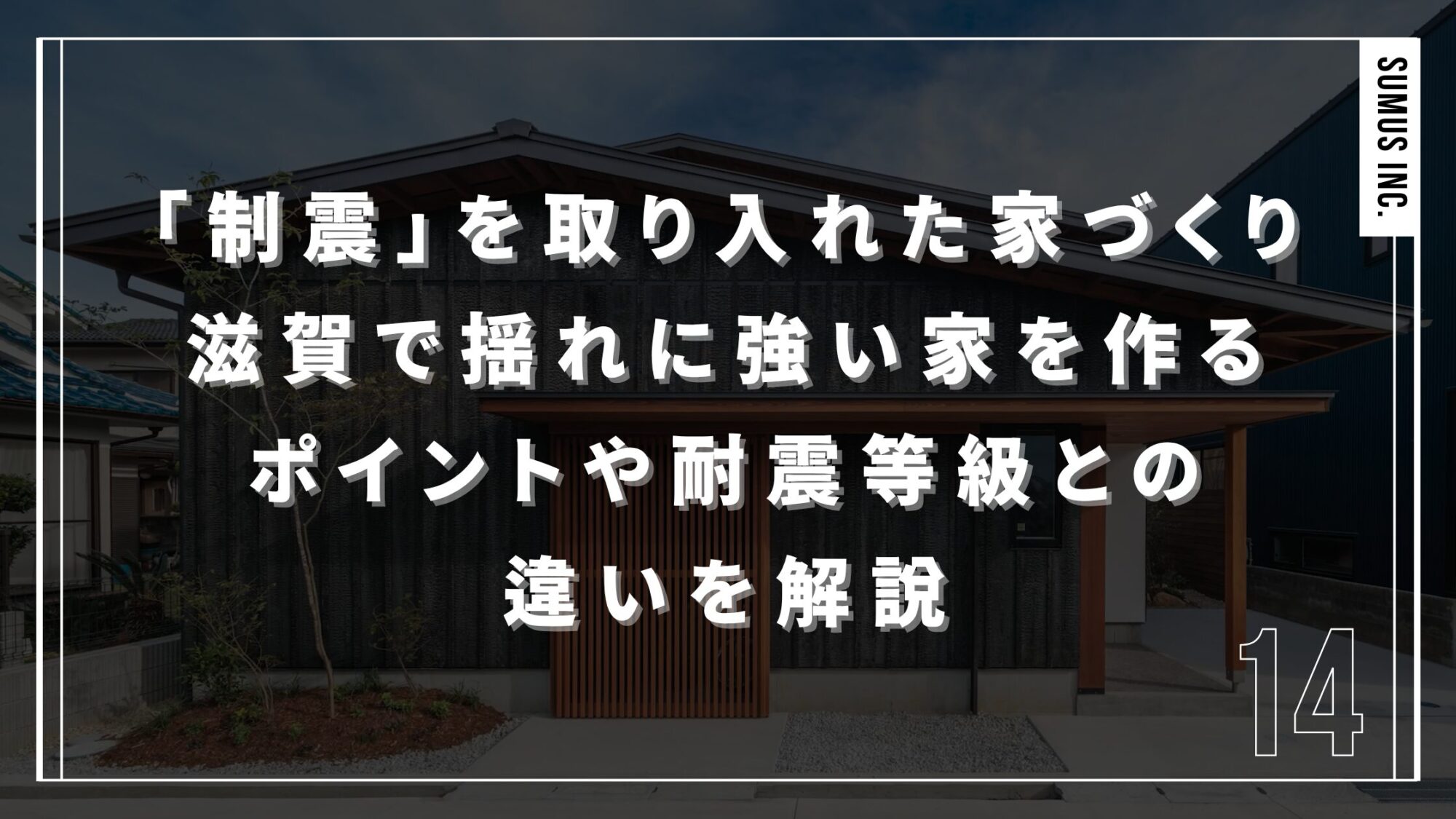
近年は台風や豪雨に加え、各地で頻発する地震被害への備えがより一層重視されるようになりました。とくに滋賀県でも、将来の南海トラフ地震による強い揺れが想定されており、住宅の地震対策はもはや必須といえるでしょう。従来の「耐震」や「免震」に加え、最近では「制震」という考え方にも注目が集まっています。
とはいえ「制震」と聞いても「他と何がちがうのか」「本当に必要なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、制震の基本的な仕組みから耐震・免震との違い、滋賀で制震住宅を建てる際のポイントまで、わかりやすく解説していきます。
「制震」とは?耐震・免震との違いについて

住宅の地震対策として知られているのは「耐震」や「免震」ですが、近年はそれに加えて「制震」という考え方も注目されるようになってきました。どれも地震による被害を軽減する手段であることに変わりはありませんが、仕組みや効果には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較しながら、「制震」とは何かを解説します
制震・免震・耐震の違いとメリット・デメリット
地震対策の基本は「耐震・免震・制震」の3つに分類されます。耐震は柱や壁を強化し、建物そのものの強度で揺れに耐える構造です。一方、免震は建物と地盤の間に装置を入れ、揺れ自体を建物に伝えにくくする仕組みです。
これに対して制震は、建物内にダンパーなどの装置を取り付けて、揺れのエネルギーを吸収・緩和します。耐震はコスト面で導入しやすい反面、大きな揺れでは家具転倒などのリスクが残ります。免震は揺れを最も抑えられる一方で費用が高く、地盤条件にも制限があるのが難点です。制震はコストと性能のバランスが取れており、近年の木造住宅でも多く採用されています。
「どれが一番いいの?」という疑問に回答
「耐震・制震・免震、結局どれが一番安全なの?」という疑問は多くの方が抱くところですが、実は正解は一つではありません。それぞれに役割や特徴があるため、建てる場所の地盤や予算、建物の構造によって最適な選択肢が異なります。たとえば、地盤が軟弱な地域では免震が向いていない場合もありますし、予算や間取りの自由度を重視するなら制震が選ばれるケースも増えています。
また、最近では「耐震+制震」など、複数の技術を組み合わせて設計するハイブリッド型の家づくりも一般的です。単に「強い家」を目指すのではなく、暮らし方や地域特性に合わせて適切な構造を選ぶことが、後悔しない家づくりにつながります。
最近注目されている「制震構造」とは
制震構造とは、建物内に設置された「制震ダンパー」が地震の揺れを吸収・抑制する仕組みのことです。ダンパーは金属やゴム、オイルなどを利用した装置で、建物が揺れる際に振動エネルギーを熱などに変換し、建物の変形や倒壊リスクを抑えます。特に繰り返し地震が発生する場合に効果を発揮し、建物の損傷を軽減できるのが大きな特長です。
耐震構造が「倒れにくい家」を目指すのに対し、制震構造は「揺れにくく、ダメージの少ない家」を目指すアプローチといえます。滋賀県のように内陸部でも揺れの強さが懸念される地域では、制震構造を取り入れることでより安心できる暮らしが実現しやすくなります。
関連記事:滋賀で耐震住宅を建てるなら?失敗しない工務店選びと地震に強い家づくりのポイント
制震装置・制震ダンパーの役割と効果
![]()
住宅の地震対策を調べていると「制震装置」や「制震ダンパー」といった言葉をよく目にするはずです。役立ちそうとは思っても、具体的にどう揺れを抑えるのか、どんな役割を果たすのかは意外と知られていません。ここでは、制震装置の仕組みや効果、後付けの可否、耐久性やメンテナンスの注意点まで順に整理して解決します。
「ダンパーは意味ない」は本当?
「制震ダンパーなんて意味ない」といった声を目にすることがありますが、それは誤解です。実際には大手メーカーや研究機関による実験で、制震ダンパーの有無による揺れ幅や建物の損傷差が明確に示されています。たとえば住友ゴムの制震ダンパー「MIRAIE」は、繰り返しの地震に対して変形量を最大70%抑えると公表されており、熊本地震のような連続地震でも被害軽減に効果がありました。
もちろん設置場所や建物構造によって効果の差はありますが、「意味がない」といわけではありません。正しく設計・施工されていれば、制震ダンパーは非常に有効な地震対策の一つといえるでしょう。
参考:木造住宅用制震ダンパー「MIRAIE[ミライエ]」適用範囲を広げてリニューアル発売 | 住友ゴム工業
後付けも可能?リフォームとの関係性
新築時に限らず、制震ダンパーは既存住宅への後付けも可能です。たとえば耐震補強と合わせて、壁の内部にダンパーを組み込む工法があり、木造住宅を対象にしたリフォーム事例も多数あります。住友ゴムやアイディールブレーンといったメーカーは、後付け用の制震装置を商品化しており、実際に全国で採用が進んでいます。
ただし、設置には構造計算が必要であり、建物の壁配置や状態によっては施工が難しい場合もあるため、信頼できる施工会社による診断が欠かせません。耐震補強とセットで検討すれば、より安心感のある改修が可能になります。
耐久性やメンテナンス面の注意点
制震ダンパーは「一度つければ一生安心」と思われがちですが、実際には使われている素材によって耐久性に差があります。一般的に金属やゴムを使ったダンパーは、20〜30年程度で性能の確認や交換が必要とされることが多く、メーカーも定期的な点検を推奨しています。特に大きな地震のあとには、目に見えない内部の劣化が進んでいることもあるため注意が必要です。
家を建てる段階では「この制震装置はどれくらいもつのか」「点検や交換は将来どうするのか」といったメンテナンスの流れまで確認しておくことが大切です。安心が長く続く家をつくるためには、施工時の性能だけでなく、将来的な維持管理も視野に入れて選ぶ意識が求められます。
関連記事:自然素材の家に使える補助金制度とは?|制度の種類・条件・注意点まで分かりやすく解説
関連記事:GX志向型住宅とは?補助金の条件・申請方法・必要な設備までわかりやすく解説
制震住宅のデメリットと注意点

耐震・免震・制震にはそれぞれ異なる特徴があり、住む人にとって大きなメリットとなる一方で、注意すべき点も存在します。とくに制震構造は導入のしやすさや費用対効果の面で注目されがちですが、必ずしもすべての住宅や土地に向いているとは限りません。ここでは、制震住宅を検討するうえで知っておきたいコストや効果の限界といったデメリット面について解説します。
制震装置の導入にはコストがかかることもある
制震装置は揺れのエネルギーを吸収する役割を持ち、繰り返しの地震にも強い構造を実現できますが、そのぶん初期費用が上がる点には注意が必要です。たとえば木造住宅に制震ダンパーを設置する場合、一般的な耐震構造に比べて数十万円〜100万円程度のコストアップが見込まれるケースもあります。ただし、ダンパーの種類や設置箇所、建物の大きさによって金額は大きく変動します。
長期的には地震被害を軽減し、補修費を抑える効果も期待できますが、導入時には工務店やハウスメーカーとしっかり相談し、コストと性能のバランスを見極めることが大切です。予算に応じて、必要最低限の箇所に絞って設置する方法も検討できます。
地盤や構造によっては効果が限定的なケースもある
制震装置は多くの住宅で揺れを抑える効果を発揮しますが、すべての建物で同じように効果が出るわけではありません。たとえば建物の形状が極端にいびつだったり、壁の配置に偏りがある場合、揺れの力が一部に集中してしまい、十分な減衰効果が得られにくくなることがあります。
また、地盤が非常に柔らかく長周期の揺れが起きやすいエリアでは、免震構造のほうが適している場合もあります。制震が「万能」ではないという前提を理解し、自分の建てたい家と土地の条件に合っているかどうかを、設計段階で専門家と十分に確認することが重要です。構造計算や地盤調査をもとに、最適な構造を選ぶ姿勢が後悔しない家づくりにつながります。
制震住宅が向いている家庭・立地とは?

前述の通り、制震住宅は繰り返しの揺れに強く、建物へのダメージを抑えられる点で多くのメリットがあります。一方で、家族の暮らし方や土地の特性によっては、他の構造のほうが適しているケースもあります。そのため、自分たちの生活スタイルや建築予定地の状況をふまえて判断することが大切です。ここでは、どんな家庭や立地に制震住宅が向いているのかを具体的に見ていきます。
家族構成・ライフスタイル別に見る向き不向き
制震住宅は、とくに子育て世帯や高齢者と同居する家庭におすすめです。地震の際に建物の揺れを抑えられるため、家具の転倒リスクや室内の混乱を最小限にでき、避難行動が難しい家族にも安心感があります。また、共働きで日中に家を空けがちな家庭にとっても、建物が無人のときに被害を抑える点でメリットが大きいといえます。
一方で、初期費用をなるべく抑えたい単身者や、将来的に建て替えを検討している家庭では、制震にこだわりすぎず、基本的な耐震性能を重視する選択も現実的です。自分たちの暮らし方に合ったリスク対策を取ることが大切です。「全世帯に必須」と考えるのではなく、ライフスタイルに合わせた選択肢の一つとして検討する姿勢が大切です。
滋賀の中でも揺れやすいエリア・地盤と制震の相性
滋賀県内でも、地盤の特性によって地震時の揺れ方に差が出ることがあります。たとえば一部の湖岸エリアや埋め立て地などでは、地盤が柔らかく、揺れが増幅されやすい傾向があるといわれています。そうした地域では、建物の損傷を抑える手段として制震構造が効果的とされることもあります。
ただし、これはすべての住宅に当てはまるものではなく、地盤の状態や建物の構造によって効果の度合いは異なります。そのため、建築予定地の地盤調査を行ったうえで、制震を導入すべきかを判断することが大切です。「揺れやすい土地かどうか」という視点を持つだけでも、より安心できる家づくりに近づけます。
滋賀で制震住宅を建てる際に押さえておきたいポイント

制震住宅に興味を持っていても、実際に建てるうえで「どの会社が対応しているのか」「設計に制約はあるのか」といった疑問が出てくるはずです。とくに滋賀で家づくりをする場合、地域の施工実績や地盤との相性も気になるところです。ここでは、制震住宅を検討する際に知っておきたい実務的なポイントを紹介します。
ハウスメーカーや工務店ごとの対応状況
制震住宅を建てる際は、依頼先によって対応できる工法や装置の種類が異なるため、事前確認が欠かせません。たとえば大手ハウスメーカーの中には、独自の制震システムを標準採用している会社もあります。一方、工務店では自由設計の柔軟さを活かし、住まい手の要望に合わせた制震提案を行っているところも少なくありません。実際に滋賀県内でも、設計段階から構造解析を取り入れ、信頼性の高い制震装置を導入する工務店が増えてきています。
対応の有無はもちろん、「どのメーカーの制震装置を採用しているか」「構造計算や検証をどの程度行っているか」といった点も、打ち合わせ時に丁寧に確認すると安心です。地域密着型の工務店だからこそできる、個別対応の強みを活かすことが成功のカギになります。
間取りの自由度と制震の両立は可能か?
制震装置を入れると「間取りが制限されるのでは」と不安になる方も多いですが、実際には吹き抜けや大開口のある空間でも、工夫次第で対応可能です。大切なのは、設計と構造を同時に考えられるパートナーに相談することです。とくに自由設計に強い工務店であれば、「この間取りでも制震を入れられる」「どう配置すれば効果を最大限に活かせるか」といった実例をもとに提案してくれます。
もし家づくりの希望が具体的にあるなら、相談時にそのイメージをしっかり伝えることで、構造との両立を前提にした設計が可能になります。制震だからといってデザインをあきらめる必要はありません。希望に寄り添ってくれる建築会社かどうかを見極めるのが、自由度と安心を両立させるポイントです。
滋賀県で「制震住宅」を建てるならスムースにお任せください

地震に備えた家づくりを考えるなら、構造や計算方法、将来の安心までしっかり見極めたいところです。スムースでは、耐震・制震それぞれの考え方をふまえたうえで、より安心して暮らせる住まいを目指した取り組みを行っています。ここでは、私たちが大切にしている構造や設計の考え方について、いくつかご紹介させていただきます。
「許容応力度計算×耐震等級3」を初回提案から採用
私たちスムースでは、すべての住宅において初回プランの段階から「許容応力度計算」による耐震等級3を確保した設計をご提案しています。これは、建築基準法で定められた最低基準(仕様規定)とは異なり、構造部材ごとに受ける力を数値で検証する、より厳密な構造計算です。熊本地震では震度7クラスの地震が2度発生し、多くの建物が繰り返しの揺れに耐えきれませんでした。私たちはその教訓を重く受け止め「一度の大地震」に耐えるだけでなく、「何度も襲う地震」にも耐えうる住まいを標準で設計することを大切にしています。
震度7を想定した制震・耐震設計
大規模な地震が発生した際、耐震だけで建物を守るには限界があります。スムースでは、強固な耐震構造に加えて「制震」という考え方を取り入れることで、繰り返しの揺れに対するダメージを最小限に抑える設計を行っています。たとえば、揺れを吸収する「制震装置evoltz(オプション扱い)」は、震度1のような小さな揺れから反応し、建物への負荷を軽減します。
これは耐震等級3の構造を補完する役割を果たし、住まいの損傷リスクを大幅に抑えるものです。「壊れない」だけでなく「傷みにくい家」を目指すのが、私たちの地震対策の基本姿勢です。
柱・梁の応力を把握する精密な構造解析
どれだけ耐震性が高いとされる設計でも、柱や梁にどのような力がかかるのかを把握していなければ、本当の意味で安心とは言えません。スムースでは、構造計算ソフトを用いて各部材ごとの応力(力のかかり具合)を細かく解析し、強度や変形の許容範囲を一棟一棟検証しています。
これにより、建物全体のバランスを保ちながら無駄のない補強が可能となり、強さと効率を両立した構造設計が実現します。「どこがどう強いのか」を説明できる、見える安全性を追求しています。
制震と自由設計を両立するハイブリッド工法
間取りにこだわりたい方にとって、制震性能と自由設計の両立は気になるポイントです。スムースでは、在来軸組工法と2×4工法の特性を掛け合わせた「ハイブリッド工法」を採用。大きな開口や開放的な空間を実現しつつ、耐力壁によって地震エネルギーを面で受け止める安定性も確保できます。
さらに、制震装置との相性も良く、希望の間取りを叶えながら、安全性を妥協しない設計が可能になります。デザインと強さのどちらも大切にしたい方にとって、理想的な構造です。
「劣化対策等級3」で性能を長期間維持
住まいの耐震性は、年月とともに劣化してしまっては意味がありません。スムースでは、住宅性能表示制度における最上位の「劣化対策等級3」を標準で確保しています。これは、構造材の湿気・腐朽・白蟻被害などに対して、60年以上にわたり強度を保てるよう設計されていることを示すものです。
また、緑の柱による防腐防蟻対策や、20年保証のシロアリ対策、地盤保証など、構造体の長寿命化にも力を入れています。長く快適に、安全に住み続けられる家づくりを支えるための、見えない部分への配慮こそ、私たちの品質基準です。
「住むサポ」による定期点検と長期保証で安心をサポート
家は建てたあとが本当のスタートです。スムースでは、お引き渡し後も安心して暮らしていただけるよう、独自のアフターサポート「住むサポ」をご用意しています。約40項目にわたる点検内容をもとに、定期的な住まいの健康チェックを実施。さらに、構造や雨漏りに関わる部分については、通常10年の瑕疵担保保証に加え、点検とメンテナンスを行うことで最長20年まで延長保証が可能です。
地盤保証や防蟻処理(緑の柱)も含め、将来を見据えた仕組みを整えることで、「万が一」に備える体制を整えています。構造の強さだけでなく、その性能を長く守り続けるサポート体制も、私たちが大切にしている家づくりの一部です。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)