木製サッシは後悔する?価格・メリット・注意点・メーカーまで徹底解説
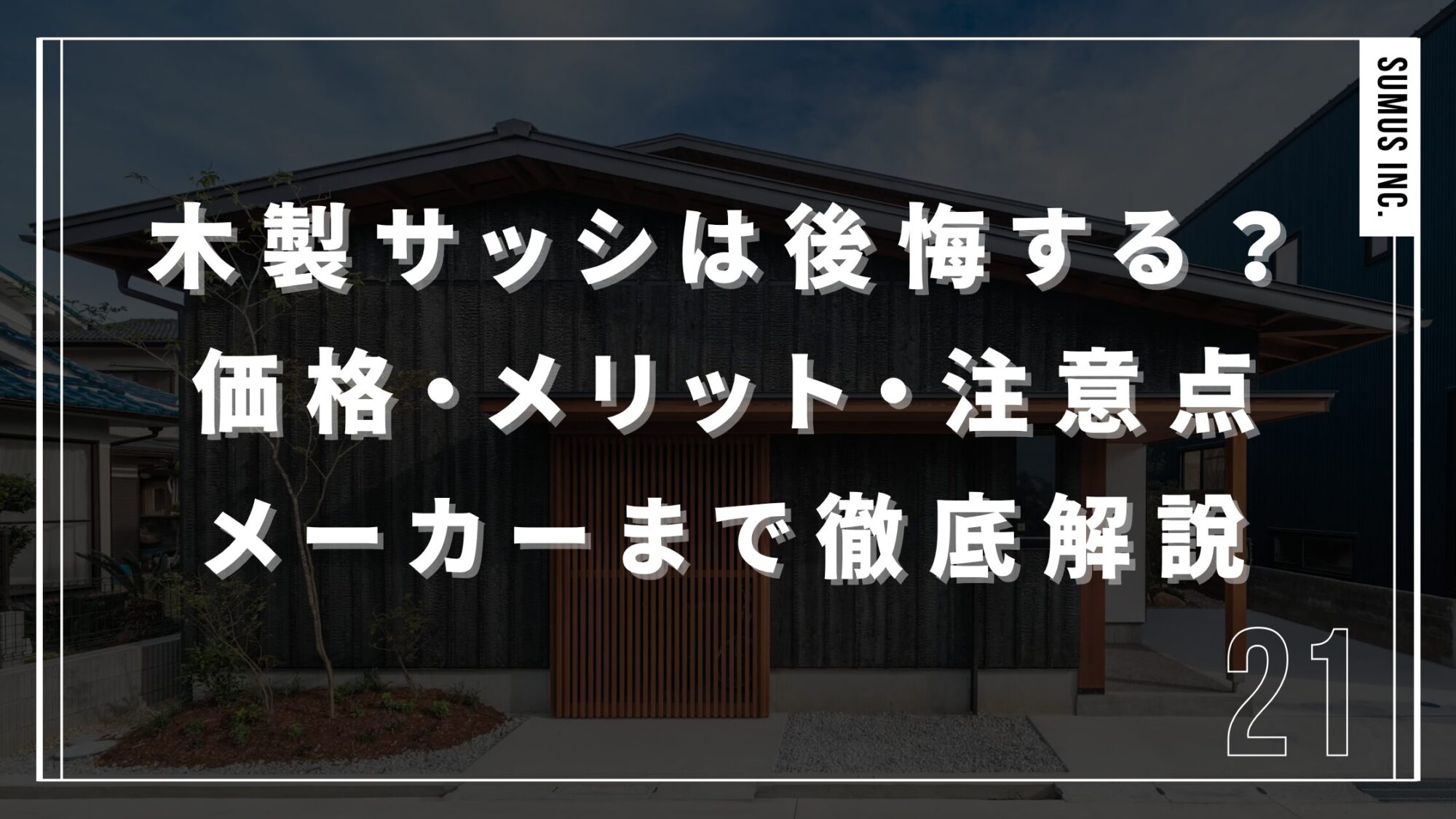
近年、無垢材の床や漆喰の壁を用いた自然素材を活かした家づくりを選ぶ人が増えています。室内の空気質や調湿性、木のぬくもりが感じられる空間が、暮らしの質を高める要素として評価されています。そんな中で、特にこだわりを持つ人が多いのが、木の温もりと高断熱性を兼ね備えた「木製サッシ」です。
木製サッシは、外観の風合いを格上げするだけでなく、断熱・結露防止・デザイン性でも優れた選択肢となります。この記事では、木製サッシの価格相場やメリット、後悔しないために重要な注意点、国内メーカーまで、木製サッシを導入する前に知っておくべきポイントについて解説していきます。
木製サッシとは木の温もりと高断熱を兼ね備えた窓枠のこと

木製サッシとは、窓の枠に金属ではなく木材を用いたサッシのことです。木が持つ自然な風合いや手触りを活かせるため、室内に暖かさと落ち着きをもたらします。冷たい金属枠と違い、触れたときに“ぬくもり”を感じられるのが特徴です。断熱性にも優れ、冬の冷気や夏の暑気を遮るため、窓際でも快適に過ごせます。
実際に「窓の近くでも寒さを感じにくい」と話す人も多く、結露を防ぎやすい点も魅力です。さらにデザインの自由度が高く、素材を丁寧に選び適切に手入れすれば、年月とともに味わいを増し、住まい全体の印象を高めてくれる窓枠となります。
木製サッシの価格相場

木製サッシの価格は、使用する木の種類やサイズ、ガラスの性能、開閉の仕組み、そして施工条件によって大きく変わります。たとえば、同じ大きさでもトリプルガラス仕様にしたり、大開口の特注サイズを選んだりすると費用は上がります。また、輸入サッシの場合は為替や輸送費の影響を受けるため、国内製より高くなる傾向です。以下に代表的な条件別のおおよその価格帯をまとめました。
| 種類・条件 | 1窓あたりの目安価格 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 標準的な引き違い窓(ペアガラス仕様) | 約6万~30万円 | 最も一般的な仕様。樹種や塗装で変動 |
| トリプルガラス・高断熱仕様 | 約20万~40万円 | 断熱・遮音性を重視した住宅向け |
| 特注形状・大開口タイプ | 60万円以上 | デザイン性重視。輸入木製サッシも含む |
※価格は本体のみの目安で、施工費やガラス交換費は別途発生します。
住宅全体の窓を木製サッシで全部統一した場合、10〜20枚ほどで300万〜500万円程度になるケースもあります。見た目や断熱性に優れる一方で、想定より費用が高く感じる人も多いため、見積もり時に「樹種・ガラス・メーカー・開閉方式」を明確にして比較検討することが大切です。
木製サッシが選ばれる理由

木製サッシは、見た目の美しさだけでなく、住まいの快適性や耐久性を高める建材として注目されています。ここでは、多くの人が木製サッシを選ぶ具体的な理由を紹介します。
結露しにくくカビやダニを防げるから家を長持ちさせられる
木製サッシは、アルミや樹脂に比べて熱を伝えにくい性質があります。外気の冷たさが室内に伝わりにくく、窓まわりの温度差が小さくなるため結露が発生しづらくなります。結露が少ないことでカビやダニの繁殖を防ぎ、室内の空気環境を清潔に保てます。さらに、湿気が原因で起こる窓枠や壁紙の劣化を抑えられるため、住まい全体を長持ちさせる効果があります。
とくに冬場でも窓まわりが乾いた状態を保ちやすく、クロスのはがれや木部の変色を防げる点は大きな魅力です。見た目の美しさが続くだけでなく、建物の耐久性や衛生面の安心感を得られるのが木製サッシの強みです。加えて、結露によるカーテンや家具のカビ臭さも軽減でき、快適な空気を保ちながら暮らしの質を高めてくれます。
アルミの約1200倍も断熱性が高く室内の温度を守れる
木は金属に比べて熱を伝えにくく、アルミの約1200倍もの断熱性を持つといわれています。アルミサッシでは外の冷気や熱がそのまま室内に伝わりやすいのに対し、木製サッシは外気の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保ちやすいのが特徴です。
冬は暖房の熱を逃しにくく、窓際でも冷えを感じにくいため、部屋全体が均一な暖かさになります。夏は外の熱気を遮ることで冷房効率が上がり、エアコンの設定温度を下げすぎなくても快適に過ごせます。結果的に光熱費の節約や省エネにつながるうえ、四季を通して穏やかな室温を保てる点が木製サッシの魅力です。
木は火に弱いは誤解!アルミより長く形を保ち安全性が高い
「木は燃えやすいから危険」と思われがちですが、実際には火災時にすぐ崩れる素材ではありません。木は表面が炭化すると内部まで燃え進みにくくなる性質があり、一定の厚みを持つ構造材は強度を長く保てます。アルミは熱に弱く、約660℃で溶け始めるのに対し、木は炭化層が熱を遮るため、形を維持する時間が長いのです。
そのため、火災時にいきなり変形して窓が落ちる心配が少なく、避難経路の確保や延焼の遅延に役立つ場合もあります。実際に耐火試験でも、一定厚の木枠は構造保持時間がアルミより長い結果が示されています。木製サッシは、見た目の温かさに加えて、安全面でも信頼できる建材といえます。
樹脂にはない木のデザイン性で住まいの印象を高められる
木製サッシは、自然素材ならではの質感と存在感が魅力です。樹脂やアルミでは再現できない木目の表情や色合いがあり、光の当たり方や経年変化によって少しずつ深みが増していきます。そのため、新築時だけでなく、時間の経過とともに味わいが増す点も人気の理由です。室内側の窓枠をフローリングや家具の色に合わせることで、空間全体に統一感が生まれ、ナチュラルで落ち着いた印象になります。
また、木の柔らかな質感が壁や天井の硬さを和らげ、リビングや寝室などの居心地を高めてくれます。最近では外側をアルミ、内側を木で仕上げたハイブリッドタイプも増えており、デザイン性とメンテナンス性の両立が可能です。素材そのものが持つ美しさで、家全体の印象を上質に引き上げられるのが木製サッシの大きな魅力です。
サイズや形を自由にオーダーでき理想のデザインを叶えられる
木製サッシは、職人やメーカーの手作業によって1枚ずつ製作されるため、サイズや形状を自由に設計できます。規格寸法が多いアルミや樹脂サッシとは異なり、アーチ状・丸窓・天井いっぱいの高さなど、空間デザインに合わせた特注対応が可能です。外観デザインを重視する建築家や自然素材の家づくりでは、木製サッシの柔軟性が大きな魅力となっています。
特に木の加工はミリ単位での調整がしやすく、窓枠と内装材を一体化させるようなデザインも実現できます。既製品に制限されず、住まいに「自分らしさ」を取り入れたい人に選ばれています。さらに、木材の色味や塗装も自由に選べるため、空間全体のトーンを揃えやすく、細部まで統一感を持たせた住まいをつくることができます。
大開口を実現できるから景色と光を最大限に取り込める
木製サッシは強度の高い集成材や構造設計によって、大開口の窓を安全に実現できる点も魅力です。金属に比べてたわみが少なく、精度の高い加工ができるため、幅の広い窓や高さのある開口部でも安定した性能を維持します。リビングの掃き出し窓を大きく取ることで、外との一体感を感じられ、自然光が部屋の奥まで届きます。
断熱性も高いため、広い窓でも室温を保ちやすく、眺望と快適さを両立できます。加えて、視線が抜ける開放的な空間は、心のゆとりや日々のリラックス効果にもつながり、暮らしをより豊かにしてくれます。
適切に手入れすれば100年以上使えるほど耐久性が高い
木製サッシを含む自然素材は「劣化が早い」と思われがちですが、実際はメンテナンス次第で非常に長持ちします。北欧では100年以上前の木製窓が今も現役で使われており、塗装の塗り替えや定期的な点検を行えば、半永久的に使うことも可能です。木は紫外線や湿気の影響を受けやすい一方で、部分補修や再塗装が容易で、金属や樹脂よりも「直して使う」ことに向いています。
また、樹種や塗料の選び方によっても耐久性は大きく変わります。耐水性に優れたオークやヒバなどを選び、浸透型塗料で定期的に保護しておけば、変形やひび割れを防げます。適切なメンテナンスを行うことで、経年変化を楽しみながら長く使えるのが木製サッシの魅力です。年月を重ねるほどに色艶が深まり、家とともに成長する素材としての価値を感じられます。
関連記事:焼杉は本当に後悔するのか?外壁材のメリットや注意点・価格までプロが解説
関連記事:家の断熱材は何がいい?種類一覧と性能ランキングで徹底比較
木製サッシで後悔する人がいるのはなぜ?知っておきたい注意点

木製サッシにはさまざまな魅力がありますが、ネット上で調べると「後悔した」「デメリットが多い」といった声も少なからず見られます。こうした内容は、事前に正しく理解しておけば防ぐことができます。ここでは、木製サッシを導入する際に知っておきたい4つの注意点を解説します。
初期費用が高くガラスも高性能にすると値段が高くなる
木製サッシは、アルミや樹脂サッシに比べて初期費用が高くなる傾向があります。標準的な木製サッシ1窓あたりの価格は約6万〜30万円ほどで、同等サイズのアルミサッシ(2〜10万円前後)と比べると2〜3倍になることもあります。特注サイズですと100万円以上あがることもあります。さらに、ガラスをトリプルやLow-E仕様に変更すると追加費用が発生し、1窓で数万円〜10万円ほど上がるケースもあります。
このため、家全体に採用すると総額が想定より大きく膨らむことがあります。価格だけを重視して中途半端な仕様を選ぶと、性能差を実感できずに後悔する人も少なくありません。事前に本体・ガラス・施工費の内訳を確認し、必要な性能を明確にしたうえで検討することが重要です。
3〜5年ごとの塗装メンテナンスが必要
木製サッシは自然素材のため、紫外線・雨・湿気の影響を受けると塗装面が徐々に劣化します。表面の塗膜が薄くなると防水性が低下し、ひび割れや変色の原因になるため、3〜5年ごとを目安に塗装メンテナンスが必要です。
再塗装では、まず表面の汚れや古い塗膜をサンドペーパーで研磨し、塗装面を整えます。その後、浸透性の保護塗料(オイルステインなど)をハケやウエスで均一に塗り込み、乾燥後に2度塗りするのが一般的です。この工程を定期的に行うことで、木部内部への水の侵入を防ぎ、腐食や反りを抑えられます。
費用は窓1枚あたり1〜2万円前後が目安ですが、部分補修をこまめに行えば大掛かりな塗り替えを避けられます。放置してからの修繕よりも、早めの手入れのほうがコストを抑えやすく、結果的に長く美しい状態を保てます。
輸入サッシはサイズが合わず部品交換も難しいことがある
輸入サッシを採用する場合、施工面の心配は工務店が対応しますが、注意すべきは「メンテナンス時の対応」です。海外製の木製サッシは、金物やパッキン、ハンドルなどの部品形状が国内製と異なるため、交換部品の入手が難しいことがあります。特に北欧や欧州メーカーでは、在庫や輸送に時間がかかるケースも多く、修理の際に数週間〜数か月待ちになることもあります。
また、メーカーによっては国内代理店が撤退するとサポートを受けられなくなることもあり、長期的な維持管理に不安が残ります。デザインや質感の良さに惹かれて選ばれることも多い輸入サッシですが、将来的な交換や修繕を見据えて、国内メーカーとの比較検討をしておくと安心です。
大開口タイプは開け閉めが重く使いにくいと感じる人もいる
木製サッシは気密性と断熱性を高める構造になっているため、どうしても枠やガラスが重くなります。特に大開口タイプは、ガラス面積が広くなるほど重量が増し、片手ではスムーズに動かしにくいと感じる人もいます。引き戸の場合はレールや戸車の精度次第で操作感が変わるため、施工品質も重要です。
また、経年によって木がわずかに膨張・収縮すると、動きが固くなることがあります。これは木の特性によるもので、定期的な調整や潤滑剤の塗布で改善できますが、メンテナンスを怠ると開閉が重く感じられる原因になります。
最近は、軽い力で動かせるスライド金具やソフトクローズ機構を備えた製品も登場しており、操作性の課題は徐々に改善されています。それでも「軽さを重視したい」「頻繁に開け閉めする場所に使いたい」という場合は、開口部の大きさや設置位置を工務店と相談しながら決めるのがおすすめです。
関連記事:自然素材の家は後悔する?よくあるデメリット・失敗例と対策をわかりやすく解説
国内の木製サッシメーカー5選

国内には、木製サッシを専門に扱うメーカーがいくつもあり、それぞれ独自の技術やデザイン性を持っています。ここでは、品質や施工実績に定評のある代表的な5社を紹介します。
ユニウッド株式会社
ユニウッド株式会社は、木製サッシをはじめとした木製建具を自社工場で一貫製造しているメーカーです。外部委託を行わないため、コストを抑えながらも高品質な製品を安定的に供給しています。サイズ・材質・カラーまで自由にオーダーでき、窓一つからの注文にも対応できる柔軟さが特徴です。
これまでにリゾートホテル、病院、一般住宅、山荘など多様な施工実績を持ち、幅広いニーズに応える経験と技術を蓄積しています。特にカナダ桧(米ヒバ)を用いた製品は断熱性・気密性・水密性に優れ、アルミや樹脂サッシと比べても性能面で劣らないとされています。木の温もりと上質な雰囲気を求める住まいに最適なメーカーです。
株式会社 アイランドプロファイル
株式会社アイランドプロファイルは、北欧・デンマークの「PROFIL VINDUET」社との技術提携から誕生した木製サッシメーカーです。北欧の厳しい気候で培われた断熱・気密技術をベースに、国内向けの高精度な木製サッシ「プロファイルウインドー」を製造しています。
木が持つ断熱性を最大限に活かし、Low-Eトリプルガラスを標準仕様として高い省エネ性能を実現。冷暖房の効率を高め、年間の光熱費削減にも貢献します。また、高気密構造により結露やカビの発生を抑え、遮音性にも優れているため、静かな住環境を保てるのが特長です。さらに、防火窓認定を取得しており、防火地域や準防火地域でも使用可能。自然塗料「オスモカラー」による塗装で、環境や人にやさしい設計を実現しています。
株式会社 川上製作所
株式会社川上製作所は、木製サッシブランド「JOYWOOD」を展開し、学校建具から一般住宅まで幅広く手がける老舗メーカーです。創業は約100年前にさかのぼり、手づくりによる建具製作の技術を代々受け継いできました。設計者や施主の希望を細部まで反映させるオーダーメイド性の高さが特長で、輸入サッシや大手メーカーでは対応が難しい自由なデザインにも柔軟に対応しています。
手加工による精密な仕上がりと、豊富な経験から生まれる設計提案力で、機能性とデザイン性を両立した製品を提供。木の質感を活かした美しいサッシは、住まいに温かみと上質感を与えます。長年培った技術と職人の手仕事により、唯一無二の窓づくりを実現しているメーカーです。
キマド株式会社
キマド株式会社は、富山県に本社と自社工場を構える国内大手の木製サッシメーカーです。従来の「高価で手入れが大変」という木製サッシの課題を改善し、耐久性・断熱性・防音性に優れた高性能な窓を提供しています。木の温もりを活かしながらも、光熱費の削減につながる高断熱仕様を標準化しており、アルミの約1/1,700の熱伝導率を実現しています。
工場での高精度な塗装システムにより、塗りムラやメンテナンスの手間を軽減。2017年以降は10〜15年再塗装不要の高耐久塗料を採用し、長期にわたって美観を維持できます。また、大開口窓「ドルフィン」やメンテナンス不要の「スマートエコウィンドウ」など、暮らしを快適にする製品ラインナップも展開。防火認定や防音性能にも優れ、デザイン性と実用性を両立したメーカーです。
タミヤ株式会社
タミヤ株式会社は、木製サッシや木製ドアを中心に、多様な建具製品を製作・販売している国内メーカーです。玄関ドアやテラスドア、排煙窓、丸窓など、住宅から商業施設まで幅広い用途に対応しており、木の質感を生かした温かみのあるデザインが特長です。
また、防火性能にも力を入れており、木製防火設備(旧乙種防火戸)認定サッシや木とアルミを組み合わせた複合サッシの製作にも対応。さらに、断熱・遮音性を備えた高級木製内窓の製造も行っており、既存の窓に後付けできる工法でリフォーム需要にも応えています。国内生産ならではの柔軟な対応力と技術力で、安全性と快適性を両立した木製サッシを提供しています。
木製サッシ選びで後悔しないために押さえておくべきこと

木製サッシを選ぶときは、見た目や価格だけで判断せず、素材や塗装、メンテナンスまで含めた総合的な視点が大切です。樹種や塗料の種類によって、耐久性や手入れのしやすさが大きく変わります。ここでは、購入前に確認しておきたい選び方のポイントを紹介します。
樹種によって見た目も性能も変わる|無垢か集成材かも要チェック
木製サッシに使われる木の種類によって、見た目や性能は大きく変わります。スギやヒノキなどの国産材は柔らかく、明るく温かみのある印象です。オークや米ヒバなどの輸入材は硬くて丈夫で、重厚感や高級感を演出できます。木目の表情や色味も樹種ごとに異なるため、床や建具との調和を考えて選ぶことが大切です。
素材は「無垢材」と「集成材」に分かれます。無垢材は自然の木そのものを使うため、経年変化を楽しめますが、湿度によって反りやすい傾向があります。集成材は複数の木を貼り合わせており、伸縮が少なく安定性に優れているため、大開口のサッシなどにも適しています。
選ぶ際は、デザイン性だけでなく使用環境も考慮しましょう。日差しや雨を受けやすい南面・西面には耐候性の高い集成材を、室内側には木目や色合いを重視した無垢材を組み合わせるのが理想的です。たとえば「外は性能重視・内は意匠重視」で選ぶと、見た目と耐久性の両立がしやすくなります。
浸透性塗料か塗膜タイプか?色味とメンテのしやすさで選ぶ
木製サッシの塗装は「浸透性塗料」と「塗膜タイプ」に分かれます。浸透性塗料は木の内部に染み込み、木目を活かした自然な仕上がりが特徴です。再塗装や部分補修がしやすく、経年で味わいが増していきます。一方、塗膜タイプは木の表面を覆うため、防水性と耐候性が高く、汚れに強い反面、剥がれた際の補修には下地処理が必要です。
色選びもポイントです。濃い色は紫外線による退色に強く、淡い色は明るくナチュラルな印象を与えますが、日焼けの変化が出やすい傾向があります。屋外側は耐候性を重視して塗膜タイプ、室内側は風合いを楽しめる浸透性塗料を選ぶなど、用途に合わせて使い分けると美しさとメンテナンス性の両立が可能です。
3〜5年ごとの再塗装・メンテナンス負担を理解して選ぶ
木製サッシは自然素材のため、日差しや雨風の影響を受けて徐々に塗膜が劣化します。特に南向きや西日の強い面では、3〜5年ごとの再塗装が必要になる場合があります。塗装が薄くなると防水性が落ち、ひび割れや変色の原因となるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。
再塗装の工程は、汚れを落とし、劣化部分を軽く研磨したうえで塗料を塗り直すのが基本です。浸透性塗料なら表面を整えてから2回塗り重ね、塗膜タイプは下地処理を含めた丁寧な再塗装が求められます。費用の目安は1枚あたり1〜2万円前後です。
また、軒や庇が深い家では紫外線を受けにくいため、塗装の持ちが長くなります。設置環境によってメンテナンス頻度は変わるため、塗料の種類や立地条件を考慮して選ぶと安心です。初期費用だけでなく、長期的な手入れコストも含めて検討することが、後悔を防ぐポイントです。
関連記事:自然素材の家のメンテナンス方法を素材別で紹介!10年後や30年後にかかる費用も解説
木製サッシに関するよくある質問

ここまで木製サッシの魅力や選ぶ際の注意点などについて解説してきましたが、実際に活用するかを検討するうえで、まだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、木製サッシに関する3つのよくある質問に答えていきます。
腐食やカビ・シロアリの心配は本当にないの?
正しく施工し定期的に手入れを行えば、腐食やシロアリの心配はほとんどありません。近年の木製サッシは乾燥・防腐処理された木材を使用し、結露を抑える構造でカビの発生も起きにくくなっています。ただし、塗装が劣化したまま放置すると木部が水分を吸い、腐食の原因になります。3〜5年ごとの塗膜点検と早めの再塗装が重要です。
シロアリは主に床下や基礎部分から侵入するため、防蟻処理された木材や薬剤処理を採用している工務店を選ぶと安心です。特に湿気が多い地域では「緑の柱」や床下防蟻処理を行うハウスガードシステムのような対策を取り入れると、家全体で長く快適に暮らせます。
木製サッシは雨漏りしたり変形したりしないの?
正しく施工されていれば雨漏りや変形の心配はほとんどありません。現在の木製サッシは防水性・気密性に優れた構造となっており、アルミや樹脂製と同等レベルの水密性能を備えています。枠とガラスの接合部にはパッキンやシーリングがしっかりと組み込まれ、豪雨時でも水の侵入を防げる設計です。
また、使用される木材は十分に乾燥処理が施されており、湿気による反りや膨張を抑えられるようになっています。集成材を使ったタイプなら、無垢材よりも寸法の安定性が高く、変形のリスクはさらに低くなります。ただし、経年によってパッキンの劣化やシーリングの隙間ができると、わずかな雨水が侵入することがあります。定期的に窓枠やゴム部の状態を点検し、劣化が見られたら早めに交換することで長く快適に使い続けられます。
防火地域でも木製サッシを設置できるって本当?
現在は防火地域や準防火地域でも使用できる「防火認定」を取得した木製サッシが各メーカーから販売されています。特殊な構造とガラス仕様により、火災時でも一定時間燃え広がりを防ぐ性能が認められています。
木は燃えやすいというイメージがありますが、実際には表面が炭化層をつくることで内部への延焼を遅らせます。アルミのように高温で変形・溶解しにくく、一定時間強度を保つ点も評価されています。
キマド株式会社やアイランドプロファイルなど、防火窓の大臣認定を取得しているメーカーの製品であれば、建築基準法の防火・準防火地域にも設置可能です。設置を検討する際は、認定番号や対応地域を工務店やメーカーに確認し、設計段階で防火仕様を選んでおくと安心です。
滋賀で木製サッシの家を建てるなら株式会社スムースにお任せ
木製サッシは自然素材の家と相性が良く、見た目と性能の両立ができます。ただ、その魅力を活かすには、設計段階から素材や環境を見極めることが大切です。自然素材の家を建てるなら、地域の気候を熟知した工務店に相談するのが安心です。木製サッシの国内メーカーの採用はもちろんのこと、自社で製作も可能です。
スムースは「家族の幸せな暮らし」を目的に、光や風、目線など“暮らしの道”を丁寧に設計。無垢材や漆喰を使った自然素材の家づくりを得意とし、木製サッシを活用した施工実績も豊富です。
また、防蟻処理材「緑の柱」や床下防蟻処理を採用し、滋賀の湿気やシロアリ対策にも万全。断熱等級6(UA値0.46)と太陽熱利用システム「OMX2」により、一年を通して快適な室内環境を実現します。自然素材の家を検討するなら、スムースのモデルハウスにぜひお越しください。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)