自然素材の家はいくらかかる?坪単価や素材別価格・補助金の利用や維持費まで徹底解説
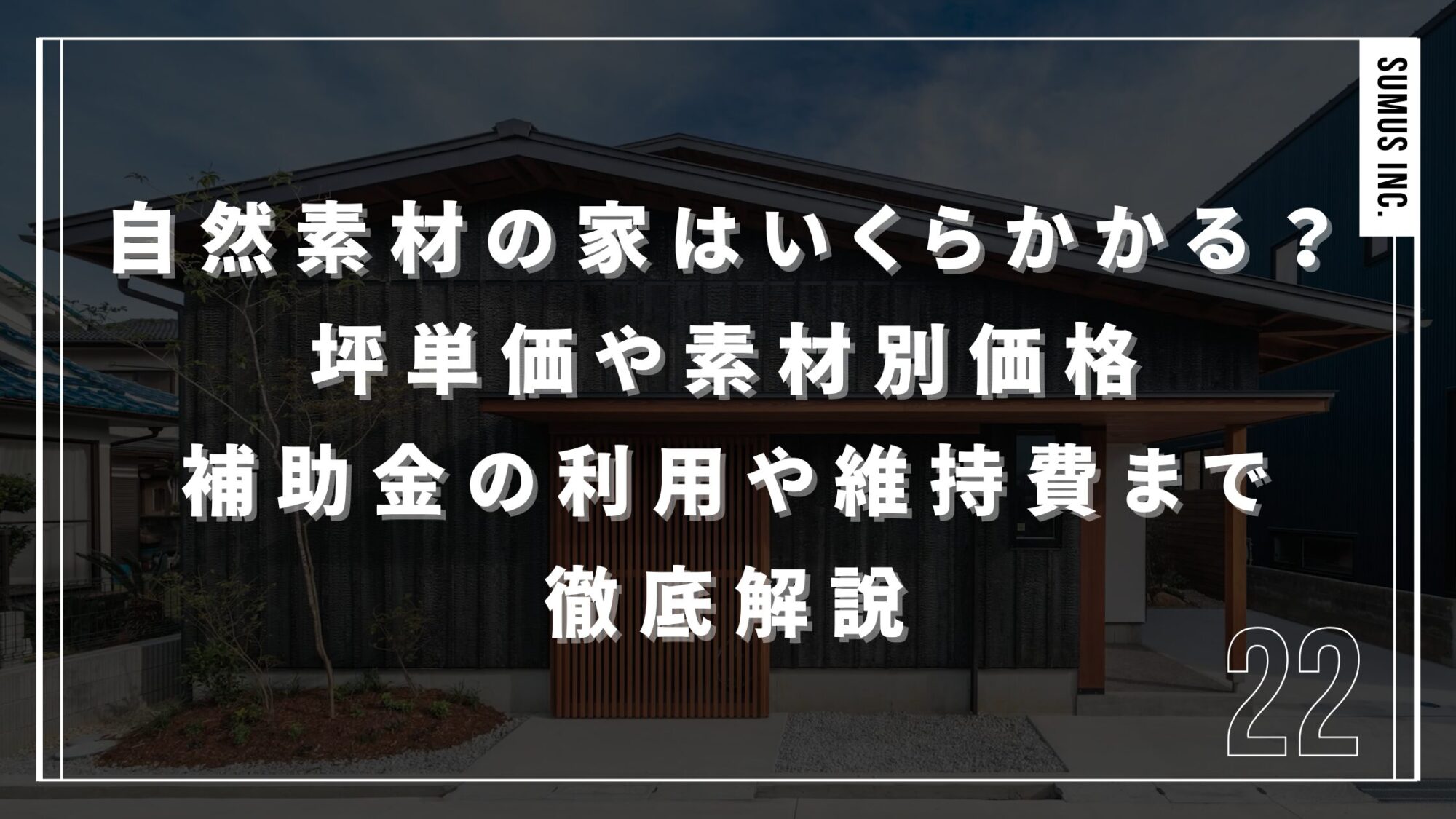
近年では、鉄筋コンクリート造りやプレハブ工法の住宅が当たり前になっています。しかしながら、人工建材の使われた住まいには「室内の空気がこもる」「経年で冷えやすくなる」といった声も少なからず存在します。そのため、木のぬくもりや自然素材ならではの調湿・断熱性能に魅力を感じて、自然素材の家、無垢材や漆喰を取り入れた住まいを選ぶ人が増えてきています。
そこで気になるのが、自然素材にこだわった場合の家の価格です。この記事では、自然素材の家の坪単価や素材別の価格、補助金の活用、維持費に至るまで詳しく解説していきます。
自然素材の家の価格は坪単価70~120万円程度が相場
![]()
結論として、自然素材を使った住まいの価格目安は「坪単価70〜120万円程度」となります。たとえば延床面積が30坪なら、約2,100万円〜3,600万円前後が建物本体の目安です。(※土地代は含まず、別途必要です)
まず「坪単価」とは、1坪(約3.3㎡)あたりの建築費用を示す言葉です。間取りが決まれば坪単価を掛け合わせ、概算の建物費用を把握できます。一般的には基礎や構造、内装、設備などの建物本体工事を含み、土地代や外構工事費、諸費用は別途となっています。
自然素材の家といっても仕様は幅広く、無垢床や一部漆喰を採用した「自然素材を少し取り入れた住宅」であれば坪単価70〜80万円台で検討できます。一方、外壁の塗り壁、焼杉、内部の漆喰、無垢材、造作建具、造作家具などをフルで採用する「本格的な自然素材住宅」の場合は、坪単価100万円以上になるケースが一般的です。
以下は、自然素材を一部取り入れた住宅の参考価格です。仕様のこだわりが増えるほど費用も上がりやすくなるため、予算と希望仕様を整理して検討することが大切です。
| 坪数 | 想定の間取り | 建物本体価格(坪単価70~120万円の場合) |
|---|---|---|
| 30坪 | 3LDK | 約2,100〜3,600万円 |
| 35坪 | 3〜4LDK | 約2,450〜4,200万円 |
| 40坪 | 4LDK+書斎 | 約2,800〜4,800万円 |
| 45坪 | 4LDK+収納充実 | 約3,150〜5,400万円 |
| 50坪 | 5LDK+二世帯対応 | 約3,500〜6,000万円 |
| 60坪 | 二世帯・大空間リビング | 約4,200〜7,200万円 |
自然素材の家の費用項目

自然素材にこだわった住まいに関係なく、家を建てる際には複数の費用項目が必要になります。各項目を正しく理解しておくことで、予算の見通しが立てやすくなります。ここでは「本体工事」「付帯工事」「外構工事」「諸費用」の4つの主要な費用項目について、何が含まれているか、何をすると価格が上がりやすいかもあわせて解説します。
本体工事|建物の費用
本体工事とは、建物の基礎・構造・屋根・外壁・内装・設備など、住宅の“骨格”と“中身”をつくる工事を指します。例えば、使用する木材が無垢材であったり、壁材に漆喰を採用したりすると、素材単価が上がるため本体工事費用に反映されやすいです。また、階数が増えたり、吹き抜け・大開口を設けたりする複雑な設計もコストが高くなる要因です。
逆に、規模をコンパクトに抑え、形状をシンプルにすればコストを抑えやすくなります。
付帯工事|引き込み・設備など
付帯工事とは、電気・ガス・水道・排水といったライフラインの引き込み工事や、エアコン・給湯器・床暖房など住宅設備の取り付けにかかる費用を指します。自然素材の家では、無垢材に適した床暖房方式や自然換気設備などを採用するケースもあり、一般的な仕様より費用が上がる場合があります。
一方で、設備のグレードを標準仕様にしたり、必要最低限の台数に抑えたりすることでコストを抑えることも可能です。また、引き込み配管は敷地条件や地盤の状態によって価格差が出やすいため、早い段階で施工会社に見積もりを依頼しておくとよいでしょう。設備を後付けできるよう設計段階で配線・配管を整えておくのも、無駄な費用を減らすポイントです。
外構工事|庭・駐車場などの費用
外構工事は、駐車場の舗装・フェンス・門扉・植栽・ウッドデッキなど、敷地内の“外まわり”を整える工事を指します。自然素材の家と調和させるため、木製デッキや天然石を使ったアプローチを採用すると、材料費・施工費ともに上がる傾向があります。一方で、駐車スペースだけ簡素に確保する、植栽を後回しにするなど、設計をシンプル化すれば外構費用を抑えられます。
また、外構は「見た目」だけでなく、雨水の排水計画や動線の使いやすさも大切です。建物と同時に設計を進めることで、無駄な掘削ややり直しを防ぎ、トータルコストを抑えられるでしょう。さらに、将来的にDIYで追加できる部分を見極めておくのも、上手なコストコントロールのポイントです。
諸費用|手続き・引っ越しなど
諸費用とは、家づくりに直接関係しない“周辺の費用”のことです。たとえば、建築確認申請料や火災保険、住宅ローンの手数料、引っ越し代のほか、地鎮祭や上棟式などの準備にも費用がかかります。これらは建物を建てるために欠かせないものですが、見落としやすい部分でもあります。
また、自然素材の家は専門知識を持つ設計士や職人の手仕事が多く、設計料や監理料がやや高くなる傾向があります。諸費用を建物本体や外構費用とは別にしっかり見積もっておくことで、後から「思ったよりお金がかかった」とならず、安心して家づくりを進められるでしょう。
無垢材・漆喰など素材別にみる価格差の違い

工事別の費用と同じく、使う素材次第で価格は大きく変わります。どの素材をどの範囲に採用するかで総額も上下します。ここでは「無垢フローリング」「漆喰・塗り壁」の相場感と、費用が高くなりやすい条件、賢い抑え方を解説します。
無垢フローリングの価格相場
無垢フローリングは、選ぶ樹種や幅、仕上げによって価格が大きく変わります。材料と施工を合わせた相場は1㎡あたり約1.2万〜3万円、坪単価に換算するとおよそ4万〜10万円が目安です。手に届きやすいのはパインやスギなどの柔らかい木で、オークやクリは中価格帯、ウォールナットやチェリーなどは高級材に分類されます。
コストを抑えるコツは、無垢材をすべての部屋に使わず、LDKなど体感しやすい空間に絞ることです。寝室や個室は複合フローリングを採用すれば、雰囲気を損なわずに費用を下げられます。さらに、節あり材や乱尺タイプを選ぶ、オイル仕上げにして自分でメンテナンスするなども有効です。
また、階段や巾木など造作部分を最小限にすることで施工費を抑えられます。ハウスメーカーでは標準外オプション扱いになることが多い無垢材も、地域工務店なら地元材の提案など柔軟な対応でコスト調整がしやすいでしょう。
漆喰・塗り壁の価格相場
漆喰や珪藻土などの塗り壁は、自然素材ならではの調湿性や質感が魅力です。材料と施工を含めた相場は、1㎡あたり約3,000〜1.5万円程度で下地の状態や塗る面積、天井や曲面の有無によっても費用が変動します。リビングや玄関など広い範囲をすべて塗り壁にすると高額になりやすいため、アクセントウォールとして一面だけ採用するのもおすすめです。たとえば、玄関ホールやリビングの一角に漆喰を取り入れるだけでも、印象はぐっと自然で上質になります。
コストを抑えるコツは、仕上げパターンをシンプルにすることです。コテ跡を強調したデザインや曲線仕上げは職人の手間がかかり、単価が上がります。腰壁までを塗り壁にして上部をクロス仕上げにするなど、部分的に取り入れる方法も人気です。施工前に照明計画と合わせて検討すると、限られた範囲でも素材の質感を引き立てやすくなります。
同素材でも樹種・グレードで変わる価格の差
同じ素材でも、グレードや加工方法によって価格差は大きくなります。無垢材なら節あり/節なし、幅狭/幅広、ソリッド/挽き板などの違いで単価が変わり、乾燥や含水率の管理がしっかりした高品質材ほど高価になります。漆喰や珪藻土も、仕上げのパターンや厚み、下地処理の丁寧さで手間が変わり、結果的に費用にも反映されます。
コストを上手に調整するには、「見える場所」から優先して素材を選ぶのがポイントです。玄関やLDKなど来客の目に触れる場所は上質素材を採用し、収納内部や水回りは清掃性・耐久性を重視して別素材に切り替えると、全体のバランスを取りやすくなります。また、リフォームや中古リノベーションで一部に無垢や漆喰を加えるのもおすすめです。使う面積を絞ることで、素材の良さを楽しみながら費用を抑えることができます。
自然素材の家の価格を無理なく抑える5つの工夫

素材の種類や施工箇所を変える以外にも、家づくりには様々な工夫を通じて費用を抑えやすくなります。ここでは、自然素材の家の価格を無理なく抑えるためのポイントを、具体的な実践ステップと注意点とともに解説します。
凹凸をなくしたシンプルな構造で建材・施工費を抑える
構造に凹凸や複雑な形状があると、建材が多く必要になったり施工が手間になったりしてコストが高くなります。設計段階で箱型に近い形状や直線的な屋根ラインを選ぶことが、コスト抑制の第一歩です。実際に取り入れる際には、間取り案を出す前に建築士と「屋根形状」「外壁の出入り」「バルコニーの有無」などを整理しましょう。注意点として、あまりに単純すぎるとデザイン性や快適性を損ねることがあるため、見た目や採光もあわせて検討が必要です。
間仕切りを減らし開放的な間取りでコスト削減する
間仕切り壁をたくさん設けると、壁材・下地・工事手間が増えます。開放的なLDKやワンフロア構成を取り入れることで、コストを抑えながら自然素材の魅力を活かせます。設計段階では「将来間仕切りできるオプション開口」にしておき初期はワンルームで使うという方法も有効です。注意点として、プライバシー確保や音の問題を後で調整しづらくなるので、必要な個室だけを明確にしておくことが大切です。
設備のグレードを選んでムダな費用を省く
自然素材にこだわると設備類もハイスペックを選びたくなりますが、すべてを最上位仕様にするとコストが跳ね上がります。冷暖房や換気、照明に関して「自然素材の性能を活かせる適正仕様」を建築士と相談して選びましょう。たとえば、無垢材の調湿性能を活かすなら、過度に高機能なエアコンより自然換気+補助機器という選択もありです。注意点として、安価すぎる設備を選ぶと快適性やメンテナンス性に影響するため、バランスが重要です。
リーズナブルな自然素材を選んで予算と機能を両立させる
無垢材や漆喰は素材の種類・グレードによって価格差があります。上質素材ばかりにこだわらず、たとえば国内産の無垢材や日本仕様の漆喰を活用することでコストを抑えられます。事前に素材リストを早期に作成し、樹種や塗り壁の種類を工務店と比較して「コスト/性能/メンテナンス性」で評価してみましょう。注意点として、あまりにも価格優先で素材選びをすると、仕上がりの質感や将来のメンテナンス頻度に影響します。
内装材を統一して工事の手間と材料費を削減する
内装材を複数種類にすると、収まり・施工手間・材料ロスが増えやすいためコストが上がる傾向にあります。できる限り床・壁・天井などの材料を統一または共通仕様にすることで、工事もスムーズになり費用を抑えられます。プランニング時点で「床材/壁材を3種類以内に絞る」「天井まで無垢材にこだわらないゾーンを設ける」などを決めておくと効果的です。注意点として、すべてを一種類に統一すると個性が出にくいため、アクセント部分だけ別仕様にしてメリハリをつける工夫が有効です。
自然素材の家の価格を下げるための補助金制度

家を建てる際には、国が実施する住宅向けの補助金や優遇制度を上手に活用することで、総費用を大きく抑えることができます。特に、自然素材を使った高性能な住まいは、環境配慮型の住宅として対象になるケースが多いのが特徴です。ここでは、2025年10月時点で利用できる主な補助金制度について解説します。
ZEH補助金
「ZEH(ゼッチ)」とは、高断熱化と太陽光発電によって、年間のエネルギー収支を実質ゼロに近づける住宅のことです。国のZEH補助金は、新築の戸建住宅を建てる個人や販売する法人が対象で、1戸あたり55万円が基本補助額、さらに高性能な「ZEH+」仕様では最大90万円程度が支給されます。断熱性能や省エネ設備、太陽光発電を組み合わせれば、自然素材の家でも対象となり、建築費の負担を大きく抑えることができます。
関連記事:GX志向型住宅とは?補助金の条件・申請方法・必要な設備までわかりやすく解説
長期優良住宅の優遇制度
「長期優良住宅」とは、耐震性・耐久性・省エネ性などに優れ、適切に維持管理される住宅を国が認定する制度です。長く安心して住み続けられる家を増やすことを目的としており、認定を受けた住宅には税制上の優遇措置が設けられています。主な優遇内容は、所得税(住宅ローン減税・投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減です。
適用期限は、住宅ローン減税が令和7年12月31日まで、不動産取得税と固定資産税が令和8年3月31日まで、登録免許税が令和9年3月31日までとなっています。特に新築の長期優良住宅では、固定資産税が5年間(マンションは7年間)軽減され、その後6年目(マンションは8年目)から通常の税額に戻ります。
自然素材の家づくりでも、耐震性や断熱性、維持管理の計画が基準を満たせば認定を受けられるため、設計段階で基準を意識しておくことで税負担を大幅に抑えられます。
関連記事:自然素材の家に使える補助金制度とは?|制度の種類・条件・注意点まで分かりやすく解説
子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、国交省と環境省が共同で行う補助制度で、子育て世帯や若者夫婦世帯の高性能住宅取得を支援します。対象はZEH水準住宅・長期優良住宅・GX志向型住宅で、補助額は40万〜160万円、古家を解体して建て替える場合は+20万円が加算されます。延床50〜240㎡の住宅が対象で、省エネ性能を満たせば自然素材の家も対象です。断熱性や耐久性を確保しながら、家族の暮らしと環境への配慮を両立できる制度です。
自然素材の家は地域の補助金も活用できることがある

国の補助金制度に加えて、各自治体でも独自に住宅支援制度を設けている地域があります。地域の木材や職人を活かした家づくりを支援するもので、活用できれば建築費をさらに抑えることが可能です。ここでは、自然素材の家づくりを後押しする代表的な地域補助制度を紹介します。
木の香る淡海の家推進事業|滋賀県
滋賀県では、県産木材「びわ湖材」の利用促進と森林保全を目的に「木の香る淡海の家推進事業」を実施しています。県内で住宅を新築・改築・増築する際、一定量のびわ湖材を使用すると助成を受けられます。
助成額は木材使用量に応じて30万〜50万円で、構造材として3〜7m³以上のびわ湖材を使うことが条件です。また、内外装の木質化リフォーム(上限20万円)や木塀設置(上限30万円)も対象となります。地域材を活かした家づくりを通じて、環境にもやさしい住まいを実現できる制度です。
香美市木材住宅支援事業|兵庫県香美市
高知県香美市では、市産木材の活用と定住促進を目的に「香美市木材住宅支援事業(香美Ing Wood House Support Project)」を実施しています。香美市内で木造住宅を新築・増改築する際、使用する市産木材の量に応じて最大200万円の補助を受けられます。
対象は主要構造部に香美市産木材を使用した住宅で、税の滞納がないこと、完成後10年以上居住することなどが条件です。さらに、高知県の「こうちの木の住まいづくり助成事業(積上補助タイプ)」の申請・受理が必須です。令和8年度まで実施予定で、申請締切は毎年3月1日です。
県産材利用住宅助成事業|岐阜県
岐阜県では、県産木材の利用促進を目的に「県産材利用住宅助成事業」を実施しています。県内で自ら居住する木造住宅を新築する施主を対象に、最大32万円(国補助併用時は最大17万6千円)を補助します。
対象は「ぎふ性能表示材」や「ぎふ証明材」など県認定木材を構造材の80%以上に使用した住宅で「ぎふの木で家づくり協力工務店」による施工が条件です。内装に県産材を使用すると加算があり、床や壁・天井などの使用面積に応じて支給額が増えます。また、令和4年以降に県外から転入した人は“移住定住枠”として申請可能です。先着順で、対象工事の完了期限は令和8年1月31日までです。
自然素材の家を建てた後に発生する特有の費用
![]()
自然素材の家は断熱性能や調湿性に優れ、日々の光熱費やメンテナンス頻度を抑えられるという大きなメリットがあります。一方で、素材そのものの特性を活かす分、一般的な住宅にはない特有の維持費が発生する点も知っておきたいところです。ここでは、自然素材の家を建てた後にかかる主なメンテナンス費用について解説します。
無垢材(床・建具)のメンテナンス費用
無垢材の床や建具は、調湿性や断熱性に優れ、時間とともに風合いが増していくのが魅力です。ただし、水分や傷に弱いため、3〜5年に一度を目安にオイル塗装を行うと長持ちします。自分で行う場合は5,000〜1万円程度で対応でき、オイルや道具もホームセンターで揃います。汚れや小傷は軽くサンドペーパーをかけてからオイルを塗り直せばきれいに整います。
関連記事:自然素材の家のメンテナンス方法を素材別で紹介!10年後や30年後にかかる費用も解説
漆喰・珪藻土の補修や塗り直し費用
漆喰や珪藻土は、室内の湿度を整える働きがある一方で、表面がデリケートなため定期的な点検が大切です。小さなひびや欠けなら、補修材を使えば1,000〜2,000円ほどで自分でも直せます。広範囲の塗り直しを業者に依頼する場合は、1㎡あたり3,000〜8,000円程度が目安です。部分補修をこまめに行えば、全体の再施工を長く先延ばしにできます。
防蟻・防湿など自然素材特有の対策費用
自然素材の家は、化学薬剤を使わず天然由来の材料で仕上げることが多いため、湿気対策やシロアリ防除に“自然系の処理剤”や“通気設計”を採用するケースがあります。こうした方法は人体や環境に優しい反面、効果が穏やかなので定期的な点検が欠かせません。工務店によっては、自然素材向けの防蟻保証や点検サポートを設けている場合もあるため、そうした体制が整った会社を選ぶと安心です。
自然素材の家は住んでからの光熱費を節約しやすくなる

関連記事:家の断熱性能と光熱費の関係|光熱費を抑えるための工夫とチェックポイントを紹介
滋賀周辺で自然素材の家を建てるなら株式会社スムースにお任せ

自然素材の家は、木や漆喰などの天然素材が持つ温もりや香り、調湿性を活かしながら、家族が心地よく健康的に暮らせる住まいです。素材の経年変化も味わいとして楽しめるため、長く愛着を持って住み続けることができます。
滋賀で自然素材の家を建てるなら、地域の気候に合わせた設計に強い株式会社スムースにお任せください。スムースでは、無垢材や漆喰など国産の自然素材を厳選し、断熱等級6・耐震等級3レベルを全棟で確保しています。さらに、腐らない木「緑の柱」を採用し、防蟻・防腐性能にも優れた構造を実現しています。
また、定期点検サービス「住むサポ」や最長20年の住宅保証で、建てた後の暮らしも安心して過ごせます。自然素材の心地よさと高い性能を両立した住まいづくりをお考えの方は、ぜひスムースにご相談ください。
動画引用元:YouTube
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)