冬場のヒートショック対策は断熱性能がカギ|家選びで知っておくべき基準を解説
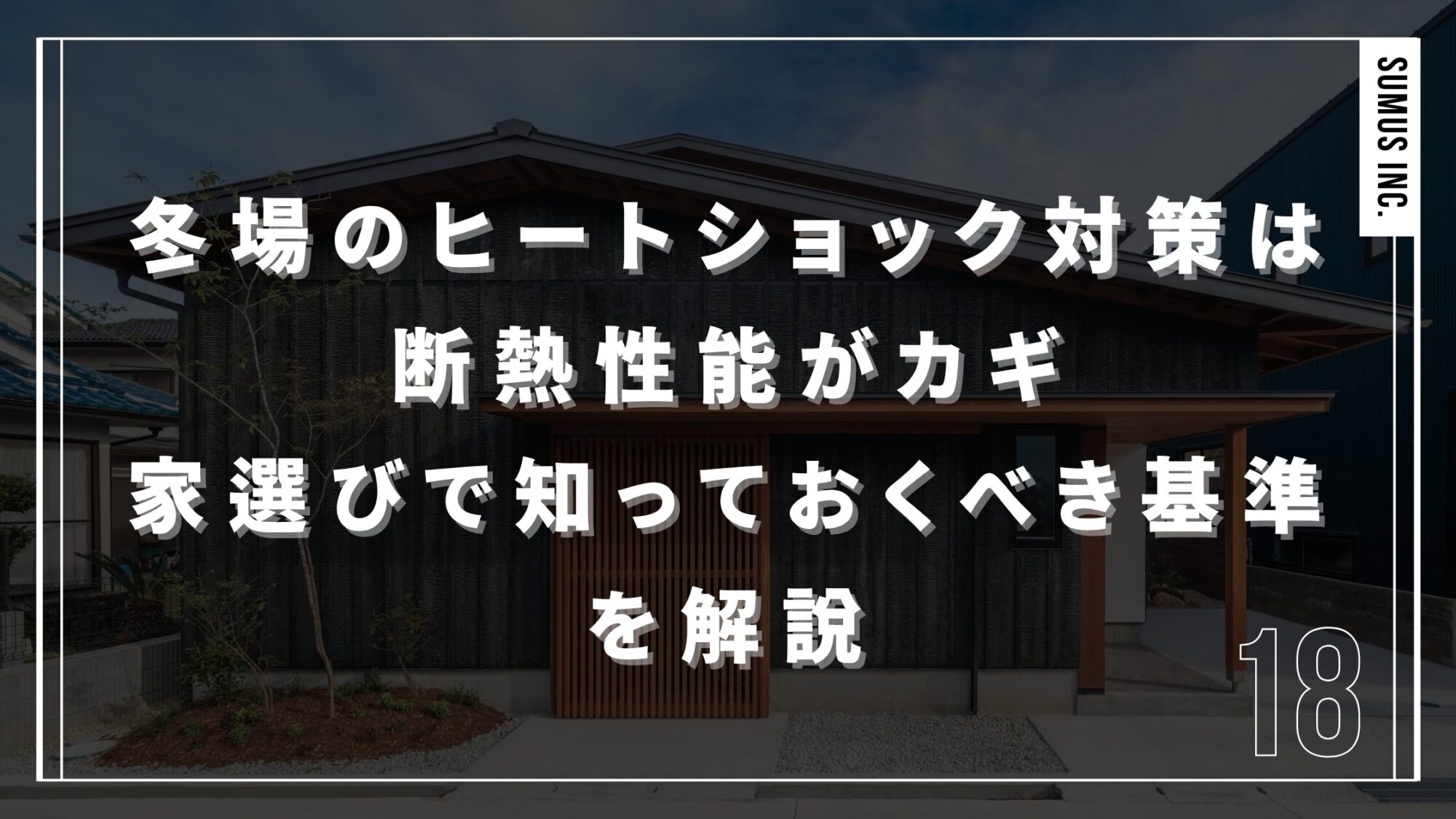
冬になると急激な温度変化による「ヒートショック」が問題になります。特に浴室や脱衣室は冷え込みやすく、血圧の急上昇や心筋梗塞のリスクが高まると指摘されています。実際、交通事故よりも多くの方が命を落としているともいわれ、家づくりを検討する際には軽視できません。
そこで注目すべきなのが「断熱性能」です。家全体の温度差を抑えれば、ヒートショックの危険を減らしつつ快適な暮らしを実現できます。この記事では、断熱等級やUA値を切り口に、ヒートショックを防ぐ家選びの基準をわかりやすく解説していきます。
ヒートショック死亡者数は交通事故の約5倍以上

寒い季節の入浴には、体に大きな負担を与える「ヒートショック」という危険があります。暖かい部屋から冷えた脱衣所や浴室へ移動し、さらに熱い湯船につかることで血圧が急激に変動し、失神や心筋梗塞、脳梗塞を引き起こすことがあるのです。厚生労働省研究班の調査では、入浴中に亡くなる方は年間約1万9,000人と推計され、交通事故死の5倍以上に上ります。
特に高齢者に多く、持病や前兆がなくても起こり得る点が大きなリスクです。寒い時期の入浴事故は家の中で突然発生し、重症化する割合も高いと指摘されています。こうした現状を知ると同時に、家づくりの段階から温度差を抑える工夫を取り入れることも欠かせない視点でしょう。
出典:冬季に多発する入浴中の事故に御注意ください!(消費者庁)
断熱性能の高い家に住むのがヒートショック対策として有効

ヒートショックを防ぐには、家の中の温度差をできるだけ小さくすることが大切です。特に脱衣室や浴室など、暖房を使わない空間が極端に冷えると、入浴時に血圧の変動が起きやすくなります。そこで有効なのが「断熱性能の高い家」に住むことです。
壁や窓、床、天井から熱が逃げにくくなれば、居室だけでなく廊下や水まわりも一定の温度を保ちやすくなり、急激な温度変化を抑えられます。結果としてヒートショックのリスクを軽減でき、安心して入浴できる環境につながるのです。さらに断熱性を高めることは、夏の暑さ対策や冷暖房費の節約、結露の抑制にも効果を発揮します。健康と快適さを両立できる住まいづくりの基本といえるでしょう。
ヒートショックを防ぐ家を断熱性能で見極める方法

快適に過ごせて冬場のヒートショックを防ぐうえで、断熱性能の高い家を選ぶことが重要なのは理解できても、実際にどう見極めればよいのか分からない方が多いのではないでしょうか。そんな時に判断の目安になるのが「断熱等級」です。これは国が定めた基準で、住宅の断熱性能を数値化したものです。ここでは等級4から7までの特徴を整理し、どのレベルで温度差を抑えられるのか解説します。
断熱等級4|室温低下が早く脱衣室・浴室が冷えやすい
断熱等級4は、かつては住宅の省エネ基準として標準的だったレベルですが、近年の気候変動や住環境の要求にはやや力不足という見方もあります。壁や天井、開口部の断熱やガラス選定は最低限の性能を満たしますが、暖房停止後の冷え込みは早く、脱衣室や浴室など暖房対象外の空間は室温が急降下しやすいのが特徴です。
特に日当たりが悪い間取りや寒冷方向の窓が多い家では、体感的な寒さが強く感じられやすいでしょう。また、2025年4月からは新築住宅・建築物に省エネ基準(断熱等級4相当)が義務化される方針もあり、断熱等級4は“最低限の基準”としての意味合いが強まってきます。
断熱等級5|居室と水まわりの温度差をある程度抑えられる
断熱等級5は、比較的新しく設けられた等級で、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー住宅)水準と整合性を持たせた基準とされています。 等級4よりも断熱・遮熱性能が向上するため、居室から廊下・トイレ・脱衣室への温度低下が緩やかになり、極端な寒暖差を軽減できる可能性があります。
ただし、等級5でも脱衣室や浴室を暖房しないと、やはり冷えが生じやすい間取りや断熱が弱い部分が足を引っ張ることがあります。断熱材の仕様・窓性能・断熱の連続性などの設計・施工品質が重要になる等級といえます。
断熱等級6|家全体の温度ムラが小さく冷えにくい
断熱等級6は、2022年に導入された上位ランクの一つで、HEAT20のG2水準に相当すると見なされることが多く、従来基準よりも厳しい断熱性能を求めるものです。この等級を満たす住宅では、冷暖房の一次エネルギー消費を従来と比較して約30%削減できるという見込みもあります。
実際の住み心地としては、リビング・居室・廊下・脱衣所など、家中の室温差が小さくなり、暖房を止めた後の冷え込みもゆるやか。結果として脱衣室・浴室での急激な温度変化が起きにくくなり、ヒートショックリスクが下がる傾向があります。断熱等級6を採用することで、冷暖房負荷の軽減や結露抑制、快適性の向上といった副次的な効果も期待できます。
断熱等級7|非暖房室も冷えにくく温度差が最小
断熱等級7は、現行制度で最上位に位置づけられる断熱水準です。2022年10月に導入され、HEAT20のG3レベルに相当するとされる性能を目指しています。この等級を満たす住宅では、外気や季節変動の影響をほぼ受けにくく、非暖房・非冷房の空間でも室温低下が抑えられます。
具体的には、朝夕の冷え込みや温度ムラがほとんどなく、居室と脱衣室、廊下・トイレ間の温度差が極めて小さい状態が期待されます。これにより、浴室への移動時や入浴時の温度ギャップも極めて緩やかになり、ヒートショック発生の可能性をさらに低減できる住宅になります。さらにこの等級の住まいは、冷暖房エネルギーを大幅に節約でき、年間を通じて快適性と省エネを両立させやすくなります。
関連記事:家の断熱材は何がいい?種類一覧と性能ランキングで徹底比較
UA値でわかる室温の冷えにくさとヒートショック対策

断熱等級とは別に、断熱性能を見極める重要な基準に「UA値(外皮平均熱貫流率)」があります。断熱等級が国の基準に基づく段階的なグレードであるのに対し、UA値は外壁や窓などからどれだけ熱が逃げやすいかを数値で示したものです。ここでは代表的なUA値ごとの特徴を整理し、ヒートショック対策の観点からどの水準を目指すべきかを解説します。
UA値0.87前後|暖房停止後すぐ冷え込みやすい
UA値0.87前後は旧省エネ基準に相当するレベルで、現在では最低限の性能とされています。暖房を切るとすぐに室温が下がり、浴室や脱衣室などの非暖房空間は一気に冷え込む傾向があります。その結果、入浴時にリビングとの温度差が大きくなり、血圧変動を招きやすい状態です。冬の快適さや安全性を考えると物足りなさが残る水準といえるでしょう。
UA値0.60前後|非暖房室の冷え込みを緩和
UA値0.60前後はZEH水準にあたり、新築住宅で多く採用されています。断熱性能が向上することで居室から廊下や脱衣室へ移動した際の温度差が緩和され、ヒートショックの危険をある程度抑えられるのが特長です。リビングだけでなく家全体に温もりが広がりやすく、過ごしやすさと省エネ性を両立できるバランスのよい水準といえるでしょう。
UA値0.46前後|脱衣室や廊下も冷えにくい
UA値0.46前後は断熱等級6に相当する水準で、非暖房室の冷え込みが小さく、家全体の温度が安定しやすくなります。暖房を切ってもしばらくは室温が保たれるため、浴室や廊下でも寒暖差を感じにくいのが魅力です。入浴前後の温度変化がゆるやかになり、ヒートショックを防ぎやすい住環境が整います。長く住むほど体への負担軽減や光熱費削減といった効果も実感しやすくなるでしょう。
UA値0.26前後|家全体の温度差がほぼない
UA値0.26前後は最高レベルの断熱性能を示し、外気の影響をほとんど受けにくい水準です。非暖房室も含め家全体がほぼ均一な温度を保つため、浴室や脱衣所での急激な冷え込みを心配せずにすみます。ヒートショックのリスク低減に加え、冷暖房費の大幅削減や夜間の快適な睡眠環境といった恩恵も得られます。健康と安心を重視する家庭にとって最も理想的な基準といえるでしょう。
関連記事:断熱等級とUA値で変わる!夏の暑さ対策に強い家を選ぶポイント
断熱性能と併せてできるヒートショック対策

ヒートショックを防ぐには、住宅の断熱性能を高めて室内の温度差を抑えることが基本ですが、日常の入浴習慣やちょっとした工夫でもリスクを下げられます。特に寒い季節は、脱衣室や浴室の環境を整えることや、入浴の仕方を見直すことが事故防止につながります。ここでは、家づくりとあわせて実践したい身近な対策を紹介します。
脱衣室・浴室を先に暖房して温度差をなくす
冬場はリビングと浴室・脱衣室との温度差が大きく、それがヒートショックの主な原因になります。入浴前に脱衣所や浴室を暖めておけば、血圧変動を起こしにくくなり、事故予防につながります。
浴室暖房乾燥機や小型のヒーターを活用するのはもちろん、シャワーを数分出してお湯の蒸気で浴室を温める方法も効果的です。断熱性能の高い家であれば、一度暖めた空気が逃げにくく、より少ないエネルギーで快適な環境を維持できます。
湯温は41℃以下・入浴は10分以内を目安に
お湯の温度が高いと血圧が急上昇し、心臓や血管に過度な負担がかかります。適切とされるのは41℃以下で、ぬるめのお湯にゆっくり入るほうが体にも優しいとされています。また、長時間の入浴は体内の水分を失わせ、血圧低下や脱水を招く原因になります。10分以内を目安にすることで、体を温めつつリスクを抑えることができます。家族が安心して入浴できるよう、温度設定や入浴時間を意識することが大切です。
入浴前後の水分補給と急な立ち上がりを避ける
入浴中は知らないうちに汗をかき、体の水分が不足します。そのままでは血液が濃くなり、血栓や血圧変動を起こしやすくなるため、入浴前後にはコップ1杯程度の水分補給を心がけましょう。また、浴槽から急に立ち上がると水圧が一気になくなり、血圧が急降下することがあります。
めまいや失神の危険を避けるためにも、手すりや浴槽の縁を支えにしながら、ゆっくりと立ち上がる習慣が重要です。高齢者がいる家庭では特に徹底しておきたいポイントです。
食後・飲酒後の入浴を避けて家族に声をかける
食事の後は消化のために血流が内臓に集中しており、入浴を重ねると血圧が大きく変動して倒れる危険があります。また、飲酒後の入浴も避けるべきです。アルコールは血管を広げ、利尿作用で脱水を進めるため、入浴によってさらに体への負担が増します。
高齢の家族が入浴する際は、できるだけ時間をずらすように声をかけると安心です。入浴前に「これからお風呂に入るよ」と知らせ合うだけでも、見守りにつながり、万が一の事態を早期に発見できます。
断熱性能にこだわると得られる他のメリット

ヒートショックを防ぐ観点から家の断熱性能を取り上げてきましたが、実際にはそれだけにとどまりません。断熱性を高めることは、暮らしの快適さや日々の安心にも直結します。ここでは、家づくりにおいて断熱性能にこだわることで得られる、健康や住まいに関わるさまざまなメリットを紹介します。
夏涼しく冬暖かいので光熱費を節約できる
断熱性能が高い家は外気の影響を受けにくいため、夏は日中に熱がこもりにくく、夜になっても蒸し暑さを感じにくい環境をつくれます。冬は暖房を止めても急に室温が下がらず、穏やかな暖かさが続くのが特長です。実際にZEH水準の住宅では、従来基準の家に比べて冷暖房費が年間で約30〜40%削減できるとされています。
延床30坪程度の戸建てなら、年間で4〜5万円ほど節約になるケースもあり、10年単位で考えると大きな差となります。快適さと省エネを同時に得られる点が、多くの人に選ばれる理由です。
関連記事:家の断熱性能と光熱費の関係|光熱費を抑えるための工夫とチェックポイントを紹介
結露やカビの抑制で家電や建材が長持ちする
室内外の温度差が大きいと、窓や壁に結露が発生しやすくなります。結露はカビの原因になるだけでなく、クロスや床材を劣化させ、住宅全体の寿命を縮める要因となります。断熱性能の高い家では表面温度が下がりにくいため、結露が発生しにくく、建材を長持ちさせられるのです。また、湿気が減ることで家電の故障リスクも下がり、結果的にメンテナンスや買い替えのコスト削減にもつながります。
18℃以上を維持しやすく体への負担を軽減
世界保健機関(WHO)は、冬の室温を18℃以上に保つことが健康の目安になるとしています。断熱性能の高い住まいなら、非暖房室も含めて温度差が小さく、家全体で18℃前後を維持しやすくなります。その結果、体が急激な寒暖差にさらされず、血圧の変動や冷えによる体調不良を防ぎやすくなります。高齢者だけでなく、小さな子どもや冷え性の方にとっても安心感のある環境を実現可能です。
断熱性能に優れた家は補助金や税制優遇の対象になる

断熱性能を高める工事や高性能住宅を建てる際、国や自治体の補助金や税制優遇を活用すれば初期費用の負担を軽減できます。これらの制度は、住宅の省エネ性能を一定以上にすることを条件とするものが多いため、計画段階で対象になるか確認することが重要です。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| GX志向型住宅補助金(子育てグリーン住宅支援事業) | 断熱等性能等級6以上などの高水準省エネ性能を満たした新築住宅に対して補助金が交付される制度。1戸あたり最大160万円の支給例あり。 |
| ZEH補助金・ZEH化促進支援 | ZEH(ネット・ゼロ・エネルギーハウス)水準相当の省エネ性能を備えれば、補助対象となる場合がある。 |
| 住宅ローン減税・税制優遇 | 省エネ性能を備えた住宅を取得すると、ローン残高の一定比率を所得税や住民税から控除できる制度。 |
| 住宅省エネ支援事業(断熱リフォーム補助) | 既存住宅の断熱改修(断熱材や窓交換など)に対して、工事費の一部を補助する制度。 |
| 地方自治体の独自補助制度 | 市町村や都道府県が実施する制度も多く、断熱改修や省エネ設備導入に対して助成金を出すケースがある。 |
こうした補助制度を活用できれば、断熱性能の高い家づくりへの初期投資を抑える助けになります。もちろん、制度は年度や地域ごとに異なるので、実際には最新の国交省・環境省・自治体の公式情報を確認し、工務店や設計者と相談しながら制度活用を検討するのが安心です。
関連記事:GX志向型住宅とは?補助金の条件・申請方法・必要な設備までわかりやすく解説
関連記事:自然素材の家に使える補助金制度とは?|制度の種類・条件・注意点まで分かりやすく解説
株式会社スムースは「断熱等級6 × UA値0.46」で室温差を抑えた家を実現
家づくりにおいて断熱性能は、快適さだけでなく健康や安全にも直結する重要な要素です。特に冬場のヒートショック対策には、家全体の温度差を小さく保つことが欠かせません。スムースではこの点に強くこだわり、常に高水準の断熱性能を備えた住宅を提供しています。
滋賀の工務店・スムースの住まいは、断熱等級6(HEAT20 G2水準)とUA値0.46を満たす設計を採用しています。これにより、リビングと脱衣室、浴室の温度差を抑え、ヒートショックのリスクを大きく減らすことができます。さらに、セルロースファイバーを使った断熱材は調湿性や防音性にも優れ、居心地のよさを長く支えます。
加えて、太陽熱を活用した全館空調システム「OMX2」や、空気循環を最適化する「OM AIR」を導入することで、家全体を効率よく快適な温度に保ちます。これらの技術により、光熱費を抑えながら健康で安心できる住環境を実現しています。
株式会社スムースでは、住宅見学会や建築技術に関する説明会などを定期的に行っています。今回の断熱性能だけでなく家に関するお悩みや不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
-
資料請求
資料請求はこちらから
-
0120-992-315
9:00~18:00(定休日 水曜/第1・3火曜日/祝日)